高市早苗 ガソリン減税 と103万円の壁引き上げの行方
高市内閣が掲げる「物価高対策」と「労働時間緩和」──その狙いとは?
2025年秋、物価高と実質賃金の停滞が続くなかで発足した高市内閣。就任会見で高市首相が最も強調したのは「物価高対策」でした。ガソリンの暫定税率を速やかに廃止し、パート労働者などに影響する「103万円の壁」を引き上げると明言。さらに冬場の電気・ガス料金支援や給付税額控除制度の早期設計にも言及しました。
同時に注目されたのが、働き方改革関連法の見直しに向けた「労働時間規制の緩和」検討です。長時間労働の是正と柔軟な働き方の両立という、相反する課題への挑戦ともいえます。
本記事では、高市内閣の経済政策と労働政策を総合的に分析し、「国民の生活をどこまで変えられるのか」を多角的に解説します。結論から言えば、今後の焦点は“スピードと実効性”です。政策がどれだけ早く、生活実感に結びつくかがカギを握ります。
ガソリン税廃止から始まる“即効性重視”の物価高対策

高市内閣の最優先課題は「物価高対策」です。2025年10月の就任会見で高市首相は、「国民の皆様が直面している物価高への対応を最優先で進める」と明言しました。その中心となるのが、ガソリンの暫定税率廃止です。
この暫定税率は、リッターあたり25.1円上乗せされる形で維持されてきました。原油価格の高止まりが続く中、これを廃止すれば1リッターあたり約20〜25円の値下げ効果が見込まれます。全国平均で見ると、1家庭あたり年間約1万〜1万5,000円の負担軽減となる計算です。
政府は今国会中の廃止法案成立を目指しており、2026年春にも実施が可能とみられます。エネルギー価格を直接引き下げることで、短期的に物価上昇を抑える「即効性」を狙うものです。
「103万円の壁」引き上げで家計と労働を両立
高市内閣が次に掲げるのが「103万円の壁」の引き上げです。この制度は、配偶者控除や社会保険料の負担発生を分ける所得ラインとして知られています。年収103万円を超えると税負担が増えるため、働く時間を抑える人が多く、“労働抑制”の要因となっていました。
政府は年末をめどに新たな制度設計をまとめ、段階的に上限を引き上げる方針です。仮に「130万円」や「150万円」への引き上げが実現すれば、パートやアルバイトなど短時間労働者の手取りが増え、労働参加率の上昇にもつながると期待されています。
専門家の間では、「労働市場の活性化には不可欠」との声がある一方で、「中小企業の人件費負担が増える懸念」も指摘されています。政府は財政支援策や社会保険制度の調整を同時に進める必要があります。
光熱費支援と給付税額控除で“冬の家計防衛”
物価高が家計を直撃する冬季に向け、政府は「電気・ガス料金の支援」も実施予定です。支援額や対象範囲はまだ調整中ですが、電力・都市ガス各社の基本料金や燃料費調整分を一定期間国が補助する形が検討されています。
さらに注目されているのが「給付税額控除(リファンダブル・タックスクレジット)」の導入です。これは、低所得層に対して“税額控除+現金給付”を組み合わせた制度で、所得税を納めていない層にも支援が届くのが特徴です。欧米では広く導入されており、日本では初の本格的な実施となる可能性があります。
“スピード感”を強調する高市首相の姿勢
これら一連の対策に共通するのは、スピード感をもって実行するという方針です。高市首相は「速やかに実施可能なものから順次着手する」と述べ、官僚機構への迅速な対応を指示しました。特にガソリン税廃止と103万円の壁引き上げは、2025年度内の実現を目指しています。
国民の多くは、対策そのものよりも“実感”を重視しています。街頭インタビューでは「給料が上がらないまま物価だけ上がる」「今すぐ助けてほしい」といった声が相次ぎました。つまり、高市内閣に求められているのは“スピードと実効性”です。経済政策が政治的スローガンで終わるか、実際の生活支援に変わるか──この数か月が正念場となります。
国民が求めるのは「速攻性」と「実感」──高市内閣への期待と不安
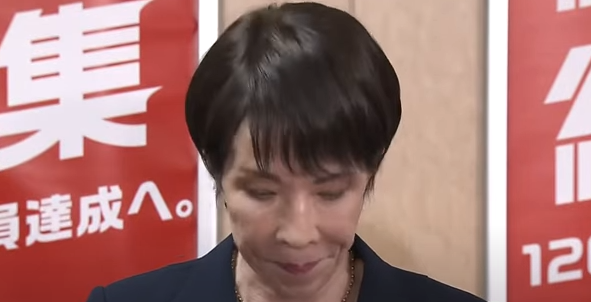
高市内閣が掲げる物価高対策に対し、国民の反応は「スピード感への期待」と「財源への不安」に二分されています。テレビの街頭インタビューでは、「毎日の生活に関わるものだから、できることから早くやってほしい」「ガソリン代や電気代が下がれば助かる」といった声が多く聞かれました。
特にエネルギー価格の高騰は、地方や車通勤世帯ほど影響が大きいとされます。リッター170円前後で推移するガソリン価格に対し、「月に1万円以上かかっている」「通勤コストが家計を圧迫している」といった実感が寄せられています。暫定税率の廃止によって“即効性のある負担軽減”を期待する声は強まっています。
「給料を上げて」──根本的な解決を求める声
一方で、物価高対策に対し「補助金よりも賃金を上げてほしい」という意見も少なくありません。ある主婦は「お米や野菜など、生活必需品の値上がりが止まらない。給料が上がらないままでは意味がない」と話します。実際、総務省の統計によると、2025年夏時点で実質賃金は前年比マイナス0.9%と、物価上昇に賃金が追いついていません。
経済アナリストの間でも、「一時的な支援では限界がある」「企業の賃上げを後押しする政策とセットで進めるべき」という指摘が出ています。特に中小企業における原材料費高騰と人件費負担の両立は大きな課題です。
「財源は大丈夫なのか?」という現実的な懸念
国民の関心は次第に「財源の確保」にも向かっています。ガソリン税廃止や給付型の控除制度には、年間数兆円規模の財政負担が発生する見込みです。街頭では「結局、後から増税されるのでは?」「国債頼みで将来世代にツケを回すのでは?」という不安の声も聞かれました。
財務省関係者によると、政府は特別会計の見直しや歳出改革で一定の財源を確保する方針ですが、社会保障費や防衛費の増加も重なり、財政余力は限られています。したがって、高市内閣の“スピード感”と“持続可能性”のバランスが問われる局面となっています。
「政治への信頼」を取り戻せるか
2025年は、岸田政権時代の「給付遅れ」「支援の複雑さ」への不満が記憶に新しい年です。高市内閣に対しては、「シンプルでわかりやすい支援を」「現場が混乱しない仕組みを」といった現実的な期待が寄せられています。
政治評論家の間では、「物価高対策は最初の試金石」「最初の100日で成果を出せなければ支持率は維持できない」と分析する声もあります。つまり、国民が求めているのは“早い・わかりやすい・実感できる”政策。高市内閣がその期待に応えられるかが、今後の支持率を大きく左右するでしょう。
「労働時間規制の緩和」指示──高市内閣が挑む働き方の再定義
高市内閣の経済政策と並行して注目されているのが、「労働時間規制の緩和」方針です。上野厚生労働大臣は就任後の記者会見で、「首相から、労働時間規制の緩和の検討を行うよう指示を受けた」と明かしました。高市首相はこれを“多様な働き方を踏まえたルール整備”と位置づけています。
この背景には、2019年に施行された「働き方改革関連法」があります。長時間労働を抑制する目的で、残業時間の上限を「月45時間・年360時間(原則)」とし、違反企業には罰則を科す内容でした。しかし施行から5年が経過し、現場からは「柔軟な働き方がしづらくなった」という声も上がっています。
「働いて働いて働いてまいります」──首相の発言の真意
高市首相は自民党総裁選直後、「今は人手が足りない。全員に馬車馬のように働いていただきます。私もワークライフバランスという言葉を捨てます」と発言し、波紋を呼びました。この発言を字面だけ捉えると“働きすぎ推奨”のように見えますが、背景には「人手不足の中で経済を回すための危機感」があります。
実際、建設業・運送業・医療業界などでは、時間外労働の上限規制がボトルネックとなり、業務が回らないケースが増えています。特に2024年以降の「物流2024年問題」では、労働時間削減が配送遅延や価格転嫁を引き起こすなど、副作用も顕在化しました。
労働時間緩和の“光と影”
労働時間規制の見直しには、明確なメリットとリスクがあります。 メリット: 生産性の高い人材が柔軟に働けるようになる。繁忙期対応の自由度が上がる。 リスク: 長時間労働の再発、過労死リスクの増大、労働者保護の後退。
とくに「裁量労働制」や「高度プロフェッショナル制度」など、成果型労働への移行は企業側に有利に働く一方で、現場の監督体制が追いつかない懸念があります。専門家の間では「規制緩和だけでなく、休暇取得の義務化や健康データの活用をセットで進めるべき」との声が多く上がっています。
“多様な働き方”をどう実現するか
高市内閣は「労働時間緩和」を、単なる長時間労働容認ではなく、テレワーク・副業・フレックスタイムの拡充といった“働き方の多様化”の一環と位置づけています。首相は「真に柔軟な働き方を選べる社会へ」と述べ、企業の自主性と労働者の選択を重視する姿勢を示しました。
ただし、制度の設計を誤れば「労働者保護が弱まり、低所得層に負担が集中する」危険性もあります。実際、街頭インタビューでは「働きやすくなった」「逆に働きづらくなった」と意見が分かれました。制度を緩めるだけでなく、企業の労務管理の透明化や、健康データを用いた過労防止が求められます。
働き方改革から“生産性改革”へ
高市内閣の狙いは、「働く時間を短くする」から「働き方の効率を上げる」へと、政策の軸を転換することにあります。過去の“時間削減型”の改革では、生産性向上や賃金上昇に直結しませんでした。今後は、AIや自動化を活用しながら、生産性を高めて労働時間を調整する“スマートワークモデル”が鍵となります。
つまり、単なる「規制緩和」ではなく、「働く人を守りながら効率を高める仕組み」が求められているのです。高市首相の決断が、疲弊した現場を救うのか、それとも再び長時間労働の時代に戻るのか──この政策は日本社会の転換点になる可能性があります。
働く現場で広がる二極化──「もっと働きたい」か「今のままでいい」か
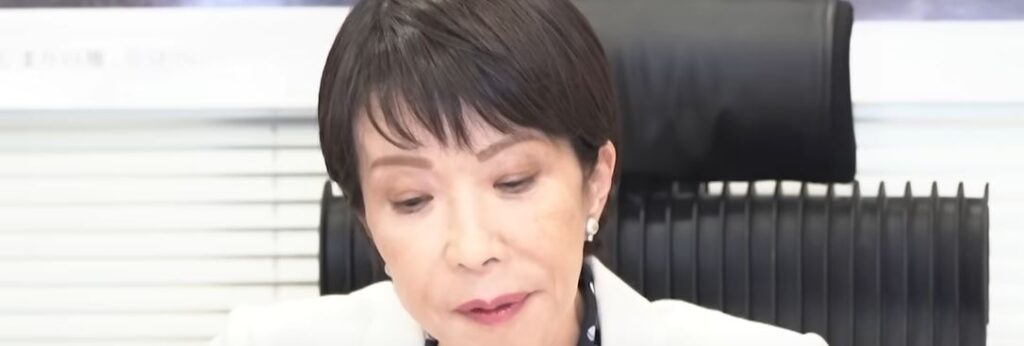
高市内閣が検討を進める「労働時間規制の緩和」は、働く現場に複雑な反応を生み出しています。街頭で意見を聞くと、「今の制度のほうが働きやすい」という声と、「もっと働けるようにしてほしい」という意見が真っ二つに分かれました。
ある会社員は「働きすぎの期間が続くと心身ともにきつい。今のままの制度がいい」と話し、逆に別の男性は「終わってない仕事を無理やり止めるのは非効率。もっと柔軟に働けるほうが助かる」と語ります。つまり、現場では“労働時間の上限”よりも“仕事の完結性”を重視する人が多いのです。
ワークライフバランスをめぐる意識の変化
2019年の働き方改革法施行以降、企業は残業削減や有給取得の義務化を進めてきました。しかし、その一方で「仕事が終わらないのに帰れと言われる」「業務が回らずストレスが増えた」という声も増えています。制度上は“働きやすくなった”はずが、現場では“働きづらくなった”と感じる人も少なくありません。
一方で、コロナ禍を経てリモートワークや副業が普及したことで、時間の使い方を自由に設計できる人も増えました。特にIT・クリエイティブ業界では「場所も時間も選べる働き方」が新しいスタンダードになりつつあります。働く人の価値観が多様化した今、単一の労働規制では限界が見えてきています。
「もっと働きたい」層の背景にある“経済的不安”
「もっと働きたい」という意見の背景には、経済的な不安があります。物価高で生活コストが上昇する中、パートや非正規労働者の中には「収入を増やしたいが、勤務時間を増やすと社会保険料負担が増えて手取りが減る」というジレンマを抱える人が多いのです。
特に「103万円の壁」や「130万円の壁」といった制度が、働く意欲を抑制してきました。高市内閣がこの壁を引き上げる方針を示したことで、「もっと働いて稼ぎたい」という層の期待が一気に高まっています。これは、単に“労働時間の問題”ではなく、“生活を守るための選択”でもあるのです。
「働きたくない」わけではない──日本の労働者心理
「長時間労働を望む人」は必ずしも“働き中毒”ではありません。多くは「仕事を途中で止めたくない」「責任を果たしたい」というプロ意識から来るもので、むしろ生産性や達成感を重視しています。一方で「家庭や健康を優先したい」という層も増えており、どちらも社会的に正当な価値観です。
このように、日本の労働者意識は「時間=働き方」ではなく、「成果と幸福度の両立」へと移りつつあります。高市内閣の“労働時間緩和”がこの変化を正しく受け止めることができるか──そこが今後の焦点となるでしょう。
“働く自由”を支える制度改革へ
経済政策と労働政策は本来、別々に語られるものではありません。働く人の意欲が経済を動かし、所得の増加が消費を支える。つまり、労働環境の最適化は日本経済の基盤そのものです。
労働時間緩和を「過労容認」ではなく「選択の自由」として設計できるかどうか。制度設計次第で、日本の労働文化は“我慢の時代”から“選べる時代”へと進化する可能性があります。高市政権の判断は、その分岐点に立っています。
「物価高対策」と「労働時間緩和」は両立できるのか?
高市内閣の経済政策は、国民生活を支える“物価高対策”と、経済基盤を強化する“労働時間規制の緩和”という二つの柱で成り立っています。しかし、この二つの政策は一見、相反する方向を向いているようにも見えます。物価高対策は「支出を抑える政策」、労働時間緩和は「生産を増やす政策」。果たして両立は可能なのでしょうか。
短期的効果:家計を守る即効性のある政策
まず短期的には、ガソリン税の廃止や光熱費支援などによって、家計の負担を直接的に軽減する効果が期待されます。これにより消費が下支えされ、景気の急激な落ち込みを防ぐ狙いがあります。日本経済研究センターによる試算では、ガソリン暫定税率の廃止によりCPI(消費者物価指数)は年間0.3〜0.5ポイント押し下げる可能性があるとされています。
しかし、これはあくまで“一時的な防波堤”に過ぎません。エネルギー価格や輸入コストが再び上昇すれば、再び物価は上昇します。したがって、短期の支援策と並行して、労働市場改革や生産性向上策を進めることが不可欠なのです。
中長期的課題:賃金と生産性の好循環をどう作るか
日本経済が長年抱えてきた課題は「賃金が上がらない」という構造的問題です。OECD加盟国の中でも、日本の実質賃金は過去30年間ほぼ横ばい。生産性の伸び悩みが最大の要因とされています。ここで鍵を握るのが、働き方の柔軟化とデジタル化です。
労働時間の規制を緩和し、生産性重視の働き方を推進すれば、企業はより柔軟な労働配分が可能になります。同時にAI・自動化・リスキリング(再教育)を組み合わせることで、従業員一人当たりの付加価値を高めることができます。結果として、企業利益と賃金上昇の両立が現実的になります。
財政とのバランス:支出拡大をどう持続可能にするか
ただし、ガソリン税廃止や給付税額控除などの施策は、国の財政に大きな負担を与えます。政府試算では、暫定税率を完全撤廃した場合、税収は年間約2兆円減少します。これを補うには、経済成長による税収増か、他の歳出削減が必要です。
高市内閣は「成長と分配の好循環」を掲げ、財政再建よりも経済再生を優先する姿勢を示しています。短期的には赤字を容認しつつ、中長期で税収増を狙う「拡張的財政戦略」です。ただし、インフレが長期化すれば、国債利回りの上昇リスクも無視できません。経済学者の間では、「拡張政策の出口戦略を明確にすべき」との声も強まっています。
生産性を高める“第三の矢”が鍵
経済対策と労働改革を両立させるには、「生産性革命」が欠かせません。政府は2026年度から、中小企業を対象としたDX(デジタルトランスフォーメーション)補助金の拡充を検討しています。自動化・AI導入・リモート体制の最適化などを支援し、労働時間を減らしながらも成果を維持する仕組みを目指しています。
また、働き方改革の第二段階として、「リスキリング支援」「副業促進」「地域雇用の流動化」なども進む見通しです。これらが機能すれば、労働者一人ひとりがより高い生産性を発揮し、経済成長と賃金上昇の両立が可能になります。
結論:政策の“順番”と“整合性”が問われる
物価高対策と労働時間緩和は、一方を欠いても成り立たない政策です。短期的な家計支援が“即効薬”なら、働き方改革は“体質改善薬”にあたります。重要なのは、この二つを同時進行で矛盾なく実行できるかどうか。
経済評論家の多くは、「支援のスピード」「政策の整合性」「実行力」の三拍子がそろわなければ、国民の生活実感にはつながらないと指摘しています。高市内閣に求められているのは、単なる“政策の羅列”ではなく、“持続的なビジョン”の提示です。2025年は、その成否を占う分水嶺となるでしょう。
高市内閣の経済政策は「実感」に届くのか──これからの焦点
ガソリン暫定税率の廃止、103万円の壁の引き上げ、電気・ガス料金支援、そして労働時間規制の緩和検討──。高市内閣の初動は、生活と経済の両面に切り込む“スピード重視型”政策として注目を集めています。就任からわずか数週間でここまで具体策を打ち出した首相は近年では珍しく、国民の期待も高まっています。
しかし、その成否は「実行力」と「持続性」にかかっています。ガソリン税廃止で一時的に家計は助かっても、財源が不明確なままでは長続きしません。また、労働時間緩和も、制度設計を誤れば再び“過労社会”を招くリスクがあります。
今後注目すべき政策スケジュール
- 📅 2025年11月: ガソリン暫定税率廃止法案の国会提出・審議開始
- 📅 2025年12月: 「103万円の壁」引き上げの制度設計と最終案決定
- 📅 2026年春: 光熱費支援および給付税額控除制度の試験導入
- 📅 2026年度以降: 労働時間規制緩和に関する労政審議会での最終議論・法改正検討
これらの政策がどの順番で、どのスピードで実現されるかが、内閣支持率の命運を握ります。特に「103万円の壁」見直しと「給付税額控除」は、低所得層や非正規労働者への影響が大きく、実施の仕方次第で評価が大きく分かれるでしょう。
国民に求められる“見極め”の視点
高市政権の掲げる「スピード」「柔軟性」「現場重視」は、これまでの日本政治に欠けていた要素です。しかし、政策のスピードが早すぎれば混乱を招く危険もあります。国民として重要なのは、単なる「支給」や「緩和」という言葉に惑わされず、“持続可能な支援かどうか”を見極める視点です。
また、労働時間の緩和が「働き方の自由」を広げるのか、「労働者保護の後退」につながるのか──その分岐点に私たちは立っています。経済と働き方、どちらも生活に直結するテーマであり、国民一人ひとりが当事者意識を持って議論を注視する必要があります。
総括:スピードと信頼の政治へ
高市内閣の政策は、短期的な救済と中長期的な改革を同時に進めるという難題に挑戦しています。そのバランスをどう取るかが最大の試練です。 物価高対策の“即効性”と、働き方改革の“構造的改善”がかみ合えば、日本経済は再び成長軌道に乗る可能性があります。
いま必要なのは、政治への信頼を取り戻す“結果”です。国民が「変わった」と感じられる成果をどれだけ早く届けられるか──それこそが高市政権の真価を問う試金石となるでしょう。
関連記事:
・物価高対策の行方:ガソリン税廃止は本当に実現するのか(日経新聞)
・103万円の壁、年末に向けて議論本格化(NHKニュース)
・働き方改革の5年、見直しの必要性と課題(東洋経済オンライン)
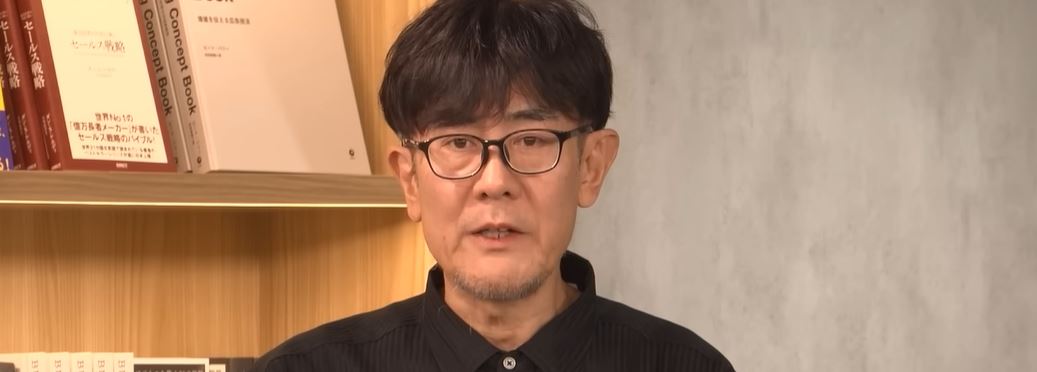
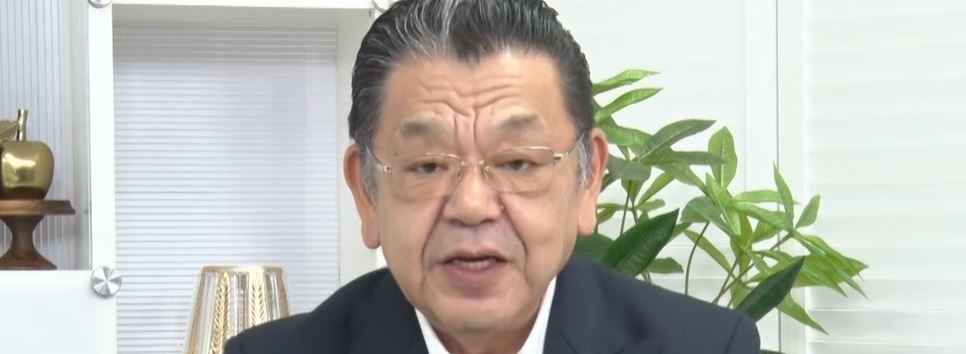




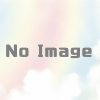
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません