総裁選 榛葉賀津也×高橋洋一 連立拡大「もし高市総理で玉木財務大臣なら?」「すごい球が飛んできましたね…」
今なぜ政局が動いているのか?

2025年の日本政治は、大きな転換点を迎えています。与党・自民党の支持率低下、野党勢力の分裂と再編、そして国民生活に直結する経済政策の遅れ──これらが重なり合い、まさに「政局の季節」が到来しているのです。
特に注目されているのが、国民民主党と日本維新の会、そして自民党の関係性です。これまで自民党一強体制が続いてきましたが、物価高や増税問題への不満が高まり、国民の目線は「誰が生活を守ってくれるのか?」へと移っています。政党間の数合わせ的な動きだけではなく、政策実現力が問われる局面になっているのです。
選挙結果がもたらした与野党の揺らぎ
2024年の衆議院選挙、そして2025年の参議院選挙では、自民党が議席を減らし、野党勢力が一定の存在感を示しました。特に維新は比例代表で躍進した一方、大阪以外の地域では組織力不足が露呈し、「全国政党」としての立ち位置が揺らいでいます。
一方、国民民主党は「政策実現型野党」としての立場を鮮明にし、ガソリン減税や103万円の壁問題など、生活者目線の政策を強く訴えてきました。しかし議席数が限られているため、単独での影響力は小さく、どの政党と手を組むかが最大の焦点となっています。
数合わせか、政策実現か
政局の動きを語るうえで外せないのが「数合わせ」という言葉です。国会では過半数を確保することが最優先とされるため、理念よりも議席の計算が優先されるケースが少なくありません。しかし、現在の日本において国民が求めているのは単なる数合わせではなく、家計を支える具体的な政策なのです。
例えば、51年続くガソリン税の暫定税率、いわゆる「ガソリン減税」の実現は、物価高に苦しむ国民にとって大きな救いとなります。また「103万円の壁」問題は、パートやアルバイトで働く人々の収入制限を生み、労働意欲を削いできました。これを是正できるかどうかは、国民生活を左右する重要なポイントです。
公明党の動きもカギを握る
さらに、長年にわたり自民党と連立を組んできた公明党の動向も無視できません。公明党は支持母体を背景に安定した票を確保してきましたが、物価高や社会保障の課題への対応が後手に回れば、支持層の離反を招く可能性があります。自民党にとっても公明党は不可欠なパートナーであり、維新や国民民主党を巻き込んだ新たな枠組みづくりにおいて、公明党のスタンスは極めて重要です。
政局の背景にある「生活者の声」
結局のところ、政局がいかに複雑であっても、その根底にあるのは国民の生活をどう守るかという一点に尽きます。株価や地価が上昇しても、手取り収入が増えず、社会保険料の負担が重くのしかかる現状では、国民は政治への不信感を募らせています。与野党が数合わせで動くのか、それとも政策を実現して国民生活を改善するのか──この分岐点に、日本政治は立たされているのです。
次章では、こうした政局の中心にいる国民民主党の動きと、その苦悩について詳しく見ていきます。
第2章:国民民主党の立ち位置と苦悩

現在の日本政治において、最も注目されている政党のひとつが国民民主党です。玉木雄一郎代表のもと、同党は「対決より解決」を掲げ、政策実現型の野党として存在感を高めてきました。特にガソリン減税や所得税控除の拡充、103万円の壁の是正といった生活者に直結する政策を積極的に提案しており、国民からの期待も少なくありません。
自民党との距離感
国民民主党の最大の特徴は、野党でありながらも是々非々のスタンスを貫いている点です。実際、与党・自民党が提出する予算や法案の中でも「国民生活に資する」と判断すれば賛成に回る一方、理念や政策が合わなければ反対を貫いてきました。
この柔軟な姿勢は「与党寄り」との批判を受けることもありますが、一方で現実的な政策実現力を示すものでもあります。例えば、ガソリン税の暫定税率廃止や103万円の壁の見直しといった課題は、国民民主党が自民党との交渉で強く主張し続けてきたテーマです。
維新との関係性
もう一つの重要な軸が日本維新の会との関係です。維新と国民民主党は、ガソリン減税や所得税控除の拡大などで共通点が多く、政策面では比較的歩調を合わせやすい立場にあります。特に「手取りを増やす」「中間層を支援する」という方向性では一致しており、共闘の可能性も指摘されています。
ただし、維新は大阪を拠点とする政党であり、全国展開を進める中で自民党との関係にも揺れ動いています。そのため、国民民主党と維新の距離は近いものの、「連立」という形で明確に足並みを揃えられるかどうかは依然として不透明です。
党内の多様な意見
国民民主党の内部にも、さまざまな意見が存在します。前原誠司氏や新馬幹事長といったベテラン議員は、自民党や維新との連携に前向きな姿勢を見せる一方で、党の独自性を失うことへの懸念も根強いのです。
特に「自民党との合流」を巡っては党内でも温度差が大きく、これが国民民主党の立ち位置を難しくしています。国民からすれば「結局どの党と組んで政策を実現してくれるのか?」が重要であり、党内調整に時間を割きすぎれば支持を失いかねません。
支持基盤の課題
国民民主党は「中道」を掲げる政党であるため、幅広い有権者層にアピールできます。しかし、その反面で明確な支持基盤が弱いという課題を抱えています。自民党のように組織票を持たず、維新のような大阪での強固な地盤もありません。そのため、選挙ごとに浮動票をどれだけ取り込めるかが勝敗を左右するのです。
実際、2024年の衆議院選挙では政策面での発信力を強めたものの、議席数の大幅な増加にはつながりませんでした。このことは、国民民主党が「政策を訴えるだけでは不十分」であることを示しています。
「政策実現型野党」としての信頼回復
国民民主党の強みは、何よりも現実的な政策提案と実行力です。玉木代表自身も繰り返し「数合わせの政治ではなく、国民のための政策実現を優先する」と強調しています。これは多くの有権者にとって共感できるメッセージであり、他の野党が「反対のための反対」に陥る中で、差別化につながっています。
しかし一方で、与党に近すぎれば「結局は自民党の補完勢力」とみなされ、野党としての存在感を失うリスクもあります。このジレンマこそが、国民民主党の最大の苦悩なのです。
まとめ
国民民主党は現在、与党との協力か、野党としての独自性かという難しい選択を迫られています。自民党との関係を深めれば政策実現の可能性は高まる一方、党の独自色は薄れます。逆に、維新や立憲民主党との連携に重きを置けば、政局上の影響力は限定的になります。
このように、国民民主党は「政局」と「政策」の間で揺れ動きながら、自らの存在意義を模索しているのです。次章では、もう一つのキープレイヤーである日本維新の会に焦点を当て、そのジレンマを掘り下げていきます。
第3章:維新のジレンマ:大阪中心か全国政党か

日本維新の会は、ここ数年で急速に存在感を増してきた政党です。特に大阪を拠点にした政治改革の実績や「身を切る改革」といったスローガンが支持を集め、2024年の衆議院選挙でも比例代表で大きな成果を上げました。しかし、その一方で「大阪中心政党」から「全国政党」へ脱皮できるのかという課題に直面しています。
大阪での強固な支持基盤
維新の最大の強みは、言うまでもなく大阪での圧倒的な支持基盤です。大阪府知事や大阪市長を長く輩出し、大阪都構想の是非を問う住民投票など、大阪政治に深く関わってきました。この地盤があるからこそ、国政選挙においても安定した議席を確保できているのです。
大阪での維新支持は、従来の自民党や公明党の勢力を凌駕するほど強固であり、「維新がなければ大阪の政治は語れない」とまで言われています。しかし、この大阪中心主義こそが、全国展開を進める上での最大のジレンマとなっています。
非大阪の議員たちの不安
維新の議員には、比例代表で当選した非大阪出身の議員が多く含まれています。彼らは大阪以外の地域で支持基盤を固めようとしていますが、選挙戦では自民党や立憲民主党との競合が激しく、苦戦を強いられるケースが目立ちます。
特に問題となるのは、自民党との「合流」や「連立」の可能性です。大阪では維新が自民党と対立関係にあるため、地元有権者は強く反発する可能性があります。一方で、全国的には維新が自民党と協力することで政策実現の道が開けるという期待もあります。この矛盾が党内で深刻な溝を生んでいるのです。
政策面での強みと限界
維新は「改革政党」として、行政のスリム化や身を切る改革を掲げてきました。また、教育無償化や規制緩和など、国民に直接メリットをもたらす政策を提案している点は高く評価されています。特にガソリン減税や103万円の壁問題では国民民主党と歩調を合わせる場面も多く、国民生活への実効的な提案をしてきました。
しかし、維新が全国で支持を広げるには「大阪改革モデル」だけでは不十分です。地方ごとに抱える課題は異なり、大阪で有効な政策がそのまま全国に通用するとは限りません。この点が、維新が「全国政党」として成長するための壁になっています。
連立への姿勢の揺らぎ
維新はこれまで「第3極」を掲げ、自民党・立憲民主党と一線を画す立場を維持してきました。しかし、2025年現在、自民党との「政策連携」や「連立参加」の可能性が取り沙汰されています。
大阪発祥の維新にとって、自民党との協力は選挙戦略上のリスクが高い一方、全国的な政策実現力を高めるには避けて通れない選択肢です。党内では「政策実現を優先すべきだ」という現実派と、「大阪での支持を裏切るわけにはいかない」という慎重派が対立しており、明確な方向性を打ち出せていません。
維新の強みと課題の対比
| 維新の強み | 維新の課題 |
|---|---|
| 大阪での圧倒的な支持基盤 | 全国的な支持拡大が進まない |
| 行政改革・教育無償化などの明確な政策 | 大阪以外での政策適用に課題 |
| 国民民主党との政策協調 | 自民党との関係を巡る党内の意見対立 |
| 「第3極」としての存在感 | 連立に参加すれば独自性を失うリスク |
まとめ
日本維新の会は、今まさに大阪中心政党としての強みと、全国政党を目指すジレンマの狭間に立っています。大阪での圧倒的支持を維持する一方で、全国の有権者にどうアピールするのかが今後の課題です。
また、自民党や国民民主党との関係をどう整理するかは、党の存在意義そのものを左右します。維新がこのジレンマをどう乗り越えるのかは、政局の行方を占う上で極めて重要なポイントとなるでしょう。
次章では、連立の行方を大きく左右する「公明党の動き」について掘り下げていきます。
第4章:公明党のキープレイヤー性
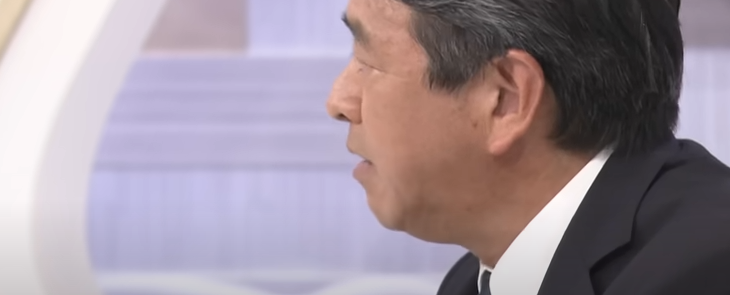
日本の政局において、長年にわたり自民党と連立を組んできた公明党は、まさに「キャスティングボート」を握る存在です。1999年に自民党と連立を開始して以来、公明党は与党内で安定した役割を果たし続けてきました。支持母体である創価学会の組織票を背景に、選挙戦においても大きな影響力を発揮し、自民党にとって欠かせないパートナーとなっています。
公明党が果たしてきた役割
自民党が単独で安定多数を確保できない場面において、公明党は「連立の安定装置」として機能してきました。特に比例代表での確実な得票力は、議席数の計算に直結するため、政権運営の基盤を支える存在となっています。
また政策面では、教育無償化や子育て支援、社会保障の充実など、生活者目線の政策を積極的に提案してきました。これは公明党の「福祉・生活重視」の理念に基づくものであり、自民党が経済政策に傾きがちな中でバランスを取る役割を果たしてきたのです。
物価高と支持層の不満
しかし2025年現在、公明党もまた支持層の不満という大きな課題に直面しています。物価高、社会保険料の増加、生活費の圧迫──これらの問題に対して、公明党が十分に成果を示せていないとの声が高まっているのです。
創価学会の支持者層は中間層や生活者が多く、ガソリン減税や103万円の壁といった家計直結の政策には強い関心を持っています。そのため、もし公明党がこれらの政策実現に後ろ向きと見なされれば、支持離れにつながる可能性があります。
自民党との関係維持か、野党との連携か
公明党にとって最大の悩みは、自民党との関係を維持するのか、それとも他の政党との連携を模索するのかという選択です。これまでの歴史を考えれば、自民党との連立を手放す可能性は低いと考えられます。しかし、もし自民党が国民民主党や維新と新たな枠組みを模索する場合、公明党の立場が相対的に弱まる懸念もあります。
逆に、公明党が国民民主党や維新と政策協調を進めれば、与党内での発言力を高められる可能性もあります。特にガソリン減税や社会保障分野では、維新や国民民主党と重なる部分も多いため、政局次第では「自民+公明+維新+国民民主」という大連立的な枠組みも現実味を帯びてくるのです。
公明党の政策と国民生活
公明党はこれまで、軽減税率の導入や教育無償化など、生活者に直接恩恵をもたらす政策を実現してきました。これにより「庶民の味方」というイメージを築いてきましたが、近年はその効果が薄れてきているとの指摘もあります。
物価高や増税が国民生活を直撃する中で、公明党が具体的にどのような政策を実現できるかが、今後の支持率を大きく左右します。特にガソリン税や103万円の壁といった課題は、公明党が「生活者の政党」であることを証明する試金石となるでしょう。
公明党の立場を整理する
| 強み | 課題 |
|---|---|
| 創価学会を背景とした強力な組織票 | 物価高への対応不足による支持層の不満 |
| 自民党との長年の連立経験 | 国民民主・維新との関係で立場が揺らぐ可能性 |
| 教育無償化や子育て支援など生活者重視の政策 | 独自性が薄れ「自民党の補完勢力」と見られるリスク |
まとめ
公明党は現在、自民党との連立を維持しつつ、生活者目線の政策をどう実現するかという難しい立場にあります。政局が動く中で、公明党の選択次第では与党内のパワーバランスが大きく変わる可能性があり、その動向は今後の日本政治において極めて重要です。
次章では、国民生活に直結する政策テーマであるガソリン減税と暫定税率問題について掘り下げ、各党の立場と影響を詳しく解説していきます。
第5章:ガソリン減税と暫定税率問題

日本の家計を直撃する負担のひとつがガソリン価格の高騰です。2025年現在も原油価格の変動や円安の影響により、ガソリン価格は高止まりを続けています。その中で注目されているのが、51年間にわたり維持されてきたガソリン税の暫定税率問題です。
暫定税率とは何か
ガソリン税には本則税率のほかに「暫定税率」が上乗せされています。この暫定税率は1970年代のオイルショックを契機に導入され、道路整備などの財源を確保するために一時的に設定されたものでした。しかし、当初「暫定」とされた税率は実質的に固定化され、半世紀以上にわたり国民の負担として残り続けています。
暫定税率分を含めたガソリン税は、1リットルあたり約53.8円に達しており、消費税も含めるとガソリン価格の約半分が税金という状況です。つまり、ガソリン代が高いのは国際価格の要因だけではなく、日本独自の税制構造にも原因があるのです。
各党の立場
ガソリン減税については、各政党が異なる立場を取っています。
- 国民民主党: ガソリン税の暫定税率廃止を強く主張し、「51年続いた不合理を是正する」と訴えています。生活者目線で最も積極的な立場です。
- 日本維新の会: 国民民主党と同様に減税に前向きであり、特に「手取りを増やす政策」の一環としてガソリン税引き下げを推進しています。
- 自民党: 財源不足を理由に慎重姿勢を崩さず、「一時的な補助金」で対応する方針を取ってきました。結果として根本的な減税には踏み込めていません。
- 公明党: 生活者重視の立場から「負担軽減」には理解を示しますが、減税による財政悪化への懸念を抱えており、明確な姿勢は示していません。
- 立憲民主党: ガソリン減税を掲げる場面もありますが、財源論が不透明で実現性が疑問視されています。
ガソリン減税の効果と限界
ガソリン税の暫定税率を廃止すれば、1リットルあたり約25円程度の値下げ効果が見込まれます。これは家計に直結するだけでなく、物流コストの低下を通じて物価全体の抑制にもつながる可能性があります。
例えば、月に50リットル給油する家庭では、年間で1万5000円以上の負担軽減効果があります。物流業界や運送業者にとってはさらに大きなコスト削減となり、物価高対策としても有効です。
しかし一方で、ガソリン税収は年間で約2.5兆円規模に上り、その多くが道路整備や一般財源に充てられています。暫定税率を廃止すればこの財源が失われ、社会保障やインフラ整備に影響を与える可能性があるのです。この「財源問題」が、減税に慎重な政党の最大の論拠となっています。
補助金依存の問題点
自民党政権はこれまで「ガソリン補助金」によって価格を抑える政策を取ってきました。しかし補助金は財政負担が大きく、しかも一時的な効果しかありません。根本的な解決策にはならず、補助金が切れれば再び価格が跳ね上がるという悪循環が繰り返されています。
この点で、国民民主党や維新が掲げる「暫定税率廃止」は、持続的な解決策として注目されています。単なる価格調整ではなく、構造的な税制改革を目指すものであり、国民生活へのインパクトは極めて大きいといえます。
国民の声と政治の責任
物価高やガソリン代の高止まりは、日常生活に直結する大問題です。特に地方や車依存度の高い地域では、家計に与える影響が都市部以上に深刻です。国民からは「いつまでガソリン税を取り続けるのか」という強い不満が寄せられています。
結局のところ、ガソリン減税は「国民生活を優先するか、それとも財政維持を優先するか」という政治の根本的な姿勢を問うテーマなのです。
まとめ
ガソリン税の暫定税率は、本来「一時的措置」であるにもかかわらず、半世紀以上にわたり維持されてきました。今、これを廃止できるかどうかは、日本政治の信頼回復に直結する問題です。国民民主党や維新が掲げる「減税路線」と、自民党・公明党が取る「財源重視路線」のせめぎ合いは、今後の政局の大きな争点となるでしょう。
次章では、同じく家計に直結するテーマである「103万円の壁と所得税控除問題」について掘り下げていきます。
第6章:103万円の壁・所得税控除問題

日本の労働市場で長年議論されてきたテーマのひとつが、いわゆる「103万円の壁」です。パートやアルバイトなど非正規で働く人々にとって、この壁は「これ以上働くと手取りが減ってしまう」という不合理な制度上の障害となってきました。2025年現在、この問題は依然として多くの家庭に影響を及ぼしています。
103万円の壁とは何か
103万円の壁とは、配偶者控除に関連する制度です。配偶者の年収が103万円以下であれば、世帯主の所得税が控除される仕組みになっています。しかし、年収が103万円を超えると控除が受けられなくなり、世帯全体での税負担が増えてしまうのです。
さらに近年では「130万円の壁(社会保険加入要件)」や「150万円の壁(配偶者特別控除の減額開始)」など、複数の「年収の壁」が存在しています。結果として、多くの労働者が「働きすぎると損をする」という状況に追い込まれています。
なぜ問題なのか
この制度の最大の問題点は、労働意欲を削いでしまうことです。特にパートや非正規労働者の多くは家庭を支える重要な役割を担っていますが、年収制限のために働きたくてもシフトを増やせない現実があります。
例えば、年収が104万円に達すると控除が打ち切られ、実質的に「働いた分が手取りに反映されない」現象が生じます。これは家計にとっても不利益であり、また人手不足に悩む労働市場全体にとっても非効率です。
各党の立場
「103万円の壁」問題は国民生活に直結するため、各党がさまざまな提案を行っています。
- 国民民主党: 103万円の壁を撤廃し、控除対象額を178万円まで引き上げると主張。玉木代表は「家計を支え、働きたい人が働ける社会を実現する」と強調しています。
- 日本維新の会: 同様に控除額の引き上げを提案。特に「労働参加を促す」ことを重視し、少子高齢化社会における労働力確保の観点からも必要としています。
- 自民党: 制度の見直しには前向きとしつつも、財源や社会保険制度との整合性を理由に大幅な改革には消極的。補助金や一時的な救済措置で対応してきました。
- 公明党: 子育て世帯や生活者支援の観点から「年収の壁」解消を掲げていますが、具体的な控除額の引き上げ案については自民党との調整が必要な状況です。
- 立憲民主党: 「所得税控除の抜本改革」を訴えていますが、詳細なシミュレーションや財源確保策は曖昧なままです。
政策が遅れてきた背景
なぜこれほど長い間、103万円の壁が放置されてきたのでしょうか。理由のひとつは、制度改正による財政負担です。控除を拡大すれば、国の税収は減少します。また、社会保険制度との関係も複雑であり、単純に控除額を引き上げれば解決するわけではありません。
さらに、従来は「専業主婦世帯」が標準的な家族モデルとされていたため、女性がパートで年収103万円程度に抑えて働くのが前提とされてきました。しかし、共働き世帯が主流となった現代において、この制度は時代に合わなくなっています。
103万円の壁解消の効果
もし控除額を引き上げたり制度を撤廃したりすれば、労働参加率の向上が期待できます。特に女性やシニア層が制限なく働けるようになれば、人手不足の解消につながり、日本経済全体にもプラス効果をもたらすでしょう。
また、家計にとっても「働いた分だけ手取りが増える」という当然の仕組みが実現されます。これは物価高に直面する現在の日本において、国民が最も望んでいる改革のひとつといえます。
103万円の壁とガソリン減税の共通点
興味深いのは、ガソリン減税と103万円の壁解消が「手取りを増やす」政策として共通している点です。どちらも国民生活に直結し、国民民主党や維新が積極的に訴えているテーマです。
一方で、自民党や公明党は財源や制度維持の観点から慎重姿勢を崩しておらず、ここに与野党の明確な政策スタンスの違いが表れています。
まとめ
「103万円の壁」問題は単なる税制の話ではなく、労働市場のあり方や家計の安定に直結する大きなテーマです。国民民主党や維新が掲げる抜本改革は国民生活を改善する可能性を秘めていますが、実現には財源や社会保険制度との調整が不可欠です。
次章では、こうした政策論争が「数合わせの連立」か「国民生活のための政策実現」かという大きな政局の対立構図にどう結びついていくのかを考察していきます。
第7章:数合わせの連立か?国民のための政策か?
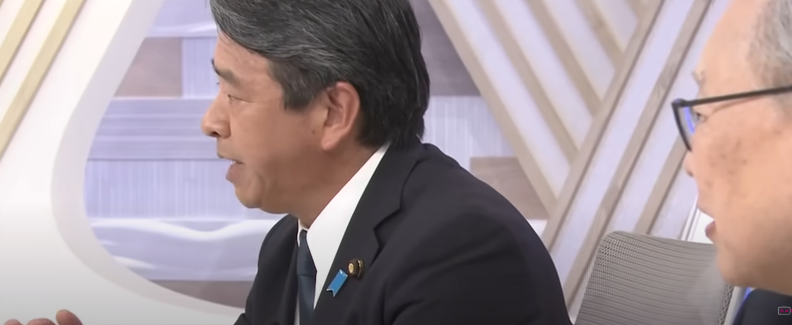
日本政治において、選挙のたびに繰り返される言葉のひとつが「数合わせ」です。国会では過半数を確保しなければ法案を通すことができないため、政党は理念や政策よりも「どこと組めば議席数を確保できるか」という計算に走りがちです。しかし、この数合わせの政治が国民生活を置き去りにしてきたことは否定できません。
連立の歴史と数合わせの実態
自民党と公明党の長期的な連立関係は、典型的な数合わせの象徴といわれます。自民党にとって公明党の組織票は不可欠であり、公明党にとっては与党にいることで政策を実現できるというメリットがあります。しかし、両者の政策理念は必ずしも一致しておらず、妥協の産物としての政策が多く見られます。
この構造は、与党だけでなく野党にも見られます。立憲民主党と共産党の選挙協力は「政権交代」を目指した戦略的なものですが、実際の政策では大きな隔たりがあります。つまり、理念や政策ではなく「票を得るための計算」が優先されているのです。
国民民主党と維新の姿勢
ここで注目されるのが、国民民主党と日本維新の会です。両党はガソリン減税や103万円の壁といった生活直結型の政策を掲げ、「数合わせではなく政策実現を優先する」と訴えています。玉木雄一郎代表は「連立に参加するかどうかではなく、国民の生活を守る政策を実現できるかが基準だ」と繰り返し発言しており、これが多くの有権者の共感を呼んでいます。
維新もまた「身を切る改革」や「教育無償化」を掲げ、数合わせではなく政策ベースでの連携を重視しています。両党に共通するのは「国民生活を第一に考える」というスタンスであり、これは自民党や公明党が財源論を優先して慎重姿勢を取る姿勢とは対照的です。
民意と数合わせの乖離
数合わせによる政局は、しばしば民意との乖離を生みます。例えば、参議院選挙で与党が議席を減らしたにもかかわらず、国会内で連立を組むことで多数派を確保し、あたかも「国民の支持を得たかのように振る舞う」ケースがあります。これは有権者にとっては違和感を覚える状況であり、政治不信を招く要因となります。
一方、国民が本当に求めているのは、生活が楽になる実感です。ガソリン代の負担が減る、手取り収入が増える、教育費が軽減される──これらが実現すれば、国民は「政治が動いた」と感じるでしょう。しかし、数合わせに終始して政策が後回しになれば、国民の不満はさらに高まります。
与野党の責任
ここで問われるべきは、与党と野党それぞれの責任です。与党は「安定多数」を理由に、数合わせのための連立を続けてきました。しかし、数を確保するだけでは政策の中身が伴わず、国民の信頼を失っています。
一方、野党は「自民党一強体制に対抗するため」という名目で共闘を進めてきましたが、理念や政策の違いを乗り越えられず、結局「反自民」というスローガン以上のものを提示できていません。これでは有権者にとって選択肢としての魅力が乏しくなってしまいます。
数合わせから政策中心へ
今後の日本政治が信頼を取り戻すためには、数合わせの論理から脱却し、政策中心の政治へと移行することが不可欠です。ガソリン減税や103万円の壁の解消といった課題は、政党間の駆け引きではなく、国民生活を改善するために最優先で取り組むべきテーマです。
国民民主党や維新のように「連立に入らなくても政策が実現すれば協力する」という柔軟な姿勢は、そのひとつのモデルといえるでしょう。理念や立場にこだわりすぎず、国民のためになる政策を優先することこそが、政治に求められている役割です。
まとめ
「数合わせの連立か?国民のための政策か?」という問いは、日本政治の根本的な課題を映し出しています。数合わせに終始すれば、国民の不信感はさらに深まり、政治離れが進むでしょう。しかし、政策を中心に据えた連携を進めれば、国民生活を改善し、政治への信頼を回復できる可能性があります。
次章では、これまでの政局と政策を総括し、「政局と政策の両面から見た今後のシナリオ」を提示します。
第8章:まとめ──政局と政策の両面から見た今後のシナリオ

ここまで、国民民主党・日本維新の会・自民党・公明党の動き、そしてガソリン減税や103万円の壁といった生活直結の政策課題を見てきました。最終章では、これらを総合的に整理し、今後の日本政治が取りうるシナリオを提示します。
シナリオ1:自民+公明による現状維持型連立
最も現実的なのは、これまで通り自民党と公明党が連立を維持するシナリオです。自民党にとって公明党の組織票は不可欠であり、公明党にとっても与党に残ることは政策実現のための生命線です。
ただしこの場合、ガソリン減税や103万円の壁といった大胆な改革は進みにくく、補助金や部分的な見直しで対応する「小出しの政策」が続く可能性が高いでしょう。結果として、国民生活の改善スピードは遅く、政治不信がさらに深まるリスクがあります。
シナリオ2:自民+維新+国民民主による大連立
次に考えられるのが、自民党・維新・国民民主の大連立シナリオです。この場合、ガソリン税の暫定税率廃止や103万円の壁撤廃といった「手取りを増やす政策」が一気に進む可能性があります。特に維新と国民民主は政策的に親和性が高く、自民党がそれを受け入れれば実現力は一気に高まります。
しかし一方で、大阪での維新の支持層や、国民民主党の「独自性」を求める声との板挟みになるリスクも大きいです。また、公明党との関係が崩れる可能性もあり、政局は不安定化する恐れがあります。
シナリオ3:非自民連携による新しい野党ブロック
立憲民主党、維新、国民民主党などが連携して「反自民ブロック」を形成する可能性もゼロではありません。選挙協力を通じて議席を増やし、自民党に対抗する構図です。
しかし、この場合は政策の方向性に大きな違いがあります。立憲民主党と維新は理念的に相容れない部分が多く、「反自民」でまとまっても政策実現には至らない可能性が高いです。数合わせにはなっても、国民が求める「生活改善」には結びつきにくいでしょう。
シナリオ4:政策ごとの部分連携
最も現実的かつ国民にとって望ましいのは、政策ごとの部分連携です。たとえば、ガソリン減税や103万円の壁撤廃では国民民主党と維新が主導し、自民党や公明党も一部譲歩して実現するという形です。
この場合、連立に縛られることなく、国会ごとに政策を実現できるため、「数合わせ」よりも「国民生活」に直結した成果を出せる可能性があります。玉木代表が掲げる「連立に入らなくても政策が実現すれば協力する」という柔軟なスタンスは、この方向性を象徴しています。
今後の焦点:政策実現力と国民の信頼
いずれのシナリオにおいても、最終的に問われるのは政策実現力と国民からの信頼です。ガソリン減税や103万円の壁撤廃といった政策は、国民生活を直接改善できる具体策であり、これを実行できるかどうかが今後の政党評価を大きく左右するでしょう。
また、「数合わせ」での政局ゲームを繰り返せば、政治不信が深まり、投票率の低下を招きます。逆に、生活改善につながる政策が実現すれば、国民は政治を「自分ごと」として捉え直す可能性があります。
まとめ
2025年の日本政治は、「数合わせの政局」から「政策中心の政治」へと移行できるかどうかの岐路にあります。国民民主党と維新が掲げる「手取りを増やす」政策は、多くの国民が待ち望むものであり、これを実現できる政党や枠組みこそが今後の信頼を勝ち取るでしょう。
政局は複雑ですが、最終的に問われるのは単純です。国民生活を本当に改善できるのは誰か?──その答えが、次の選挙と日本の未来を決定づけるのです。







ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 総裁選 榛葉賀津也×高橋洋一 連立拡大「もし高市総理で玉木財務大臣なら… […]
[…] 総裁選 榛葉賀津也×高橋洋一 連立拡大「もし高市総理で玉木財務大臣なら… […]
[…] 総裁選 榛葉賀津也×高橋洋一 連立拡大「もし高市総理で玉木財務大臣なら… […]