高市早苗内閣の支持率60%超!財務省封じと減税路線で経済再生へ
【緊急朗報】高市早苗内閣の支持率が驚異の60%超!財務省を封じる新経済戦略の全貌
10月21日に発足した高市早苗内閣。その直後に実施された世論調査では、支持率がなんと60%を突破したと報じられています。
これは前政権よりも約10ポイント高い異例の数字であり、国民の期待が「確実な変化」を求めている証拠です。
注目すべきは、単なる人気の高さではありません。高市政権は発足直後から「財務省の支配構造を打破し、積極財政へ舵を切る」という明確なビジョンを掲げました。
須田慎一郎氏の分析によれば、政務調査会・経済財政諮問会議・人事配置のすべてが「減税と景気回復」を前提に設計された前例のない布陣だといいます。
本記事では、なぜ今このタイミングで支持率が急上昇したのか、そして財務省を封じる高市政権の“真の狙い”を深掘りします。
高市早苗内閣の支持率が60%超え!国民が求めた「真の転換点」

10月21日に発足した高市早苗内閣は、発足直後の世論調査で支持率60%超という驚異的な数字を記録しました。
この結果は、単なる新政権へのご祝儀相場ではありません。むしろ、長年の「停滞」への不満と、「変化への渇望」が一気に表面化した象徴と見るべきです。
国民が求めているのは、言葉だけの改革ではなく、生活実感を伴う“経済回復”です。
物価上昇・実質賃金の低下・社会保障負担の増加に苦しむ中で、「積極財政」「減税」というキーワードを明確に打ち出した高市政権は、まさに期待の受け皿となったのです。
これまでの政権は「財政健全化」という名目で支出を抑え、景気を冷やす政策を続けてきました。
しかし、高市首相はその流れを逆転させ、「成長による財政再建」という新しい方程式を掲げました。
国民にとって、それは「我慢の時代」から「再生の時代」への転換を意味します。
さらに今回、連立のパートナーが公明党から日本維新の会へと変わったことも注目点です。
維新は地方分権・規制改革・減税志向を掲げており、この組み合わせが新政権の支持を押し上げた最大要因だと考えられます。
つまり、支持率60%という数字の裏には、単なる人気ではなく、「政策内容への期待」と「既得権構造への反発」という、国民の明確な意思が表れているのです。
自民×維新連立体制の衝撃!日本政治の「新バランス」が動き出した
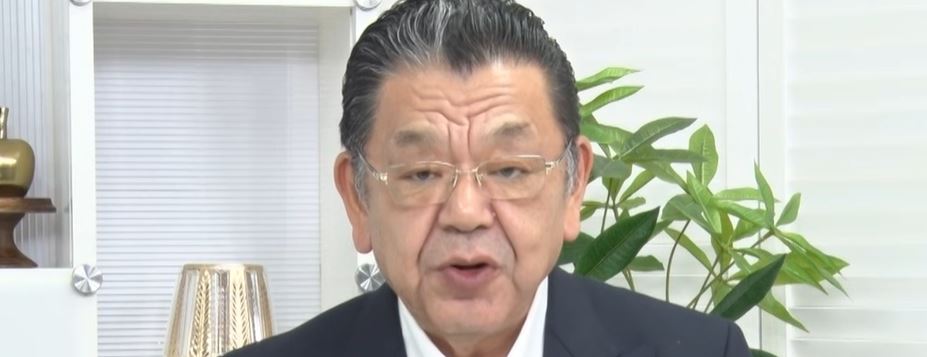
今回の高市早苗内閣で最も注目されている変化の一つが、自民党と日本維新の会による新たな連立体制です。
これは単なる政権維持のための数合わせではなく、明確な「政治改革の意思表示」と言えます。
公明党との連立が長年続いた結果、自民党内では政策決定のスピードが鈍化し、官僚主導の政治が常態化していました。
一方、維新は「既得権打破」「小さな政府」「減税」「デジタル行政」といったキーワードで国民の支持を伸ばしてきた政党です。
この維新とのタッグこそが、財務省依存の政治構造を変える最大の一手になると専門家の間でも注目されています。
実際、今回の世論調査では「この新しい連立を評価する・どちらかといえば評価する」と回答した人が60%を超えました。
つまり国民の過半数が、「自民×維新」の新体制に希望を見出しているのです。
背景には、地方からの変革期待があります。
維新の強みは「地方発の改革力」。
国の中央集権構造を変え、地域経済を活性化させる視点が、今の日本には最も不足していました。
高市政権はそこに維新の“実行力”を融合させることで、長く停滞していた政策運営に新しい風を吹き込もうとしているのです。
この連立は、「旧来型自民」と「挑戦型維新」の融合による“改革連立”。
まさに日本政治の「リセットボタン」が押された瞬間だといえるでしょう。
積極財政路線とは?財務省主導政治との決別を意味する高市政権の選択
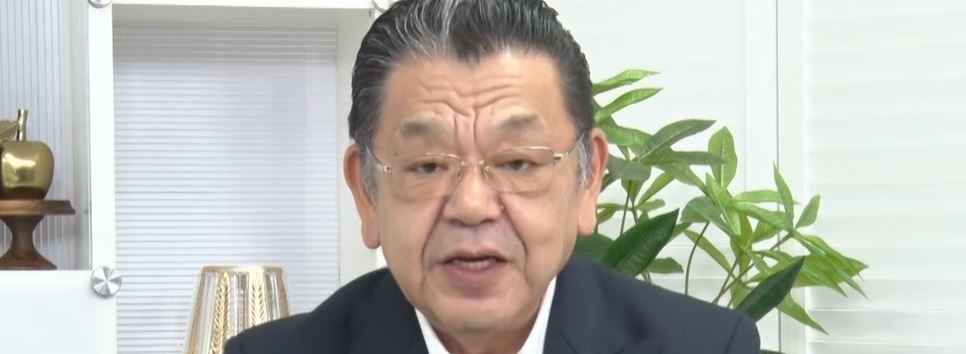
高市早苗政権を語るうえで欠かせないキーワードが「積極財政」です。
これは単なるバラマキ政策ではなく、明確な経済哲学の転換を意味します。
これまで日本の財政運営は「財務省主導」で行われ、“財政健全化”という名目のもとで、歳出削減と増税が繰り返されてきました。
しかし、その結果どうなったでしょうか。
国民の可処分所得は減り、消費は冷え込み、GDPは実質的に30年近く横ばいのままです。
つまり、緊縮財政は国を豊かにするどころか、「経済の萎縮」を生み出してきたのです。
高市首相は、この構造的な失敗を直視しました。
そして掲げたのが、「責任ある積極財政」という新しい方針です。
この考え方は、“必要なときに必要な分だけ大胆に支出し、成長によって財政を立て直す”というもので、安倍政権時代の「アベノミクス」をより現実的に進化させたモデルとも言えます。
注目すべきは、高市政権が「財務省の論理」に依存せず、政治主導で予算を設計しようとしている点です。
経済財政諮問会議の構成を見ても、財務官僚の影響力を最小限に抑え、民間出身の経済人や実務経験者を積極的に登用しています。
この方針転換は、単なる財政政策の変更ではありません。
「誰が国家の舵を取るのか」という、日本政治の根幹を揺るがす決断です。
政治家が再び主導権を取り戻し、財務官僚に“予算を握らせない”仕組みを築く。
これこそが、須田慎一郎氏の言う「財務省封じ」の本質なのです。
積極財政は短期的にはリスクを伴います。
しかし、それを恐れては何も変わらない。
高市政権は、30年の停滞を断ち切るために、ついに“禁断のスイッチ”を押したと言えるでしょう。
減税シナリオの全貌!高市政権が描く「経済再生ロードマップ」
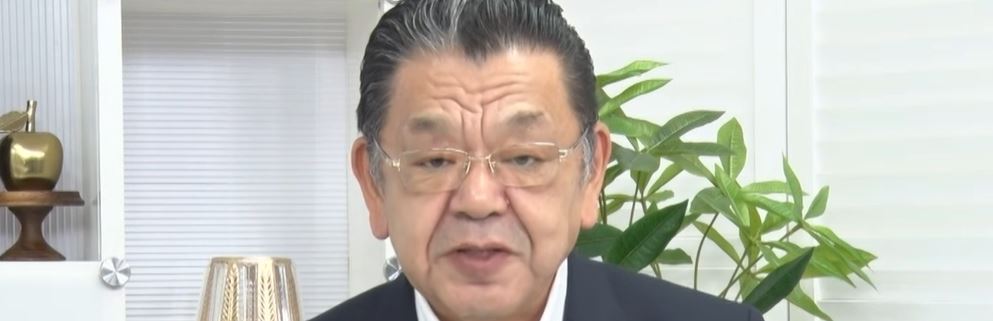
高市早苗政権の真価は、これから実行される減税政策によって試されます。
須田慎一郎氏の分析によれば、今回の政権は「減税を実現できる構造」を意図的に設計しており、単なる選挙向けのスローガンではないのです。
まず最初に着手が見込まれているのが、ガソリン税の暫定税率廃止です。
エネルギー高騰による物価上昇が家計を圧迫する中、年内実施を目指す方針が検討されています。
これにより輸送コストが低下し、物価の安定と消費の刺激が期待されます。
次に焦点となるのが、いわゆる「年収の壁」問題です。
現行の103万円・130万円の所得制限が、女性や若年層の就労意欲を削いでいる現実があります。
これを178万円まで引き上げ、労働市場の活性化を狙う構想が進行中です。
さらに、将来的には消費税減税も視野に入っています。
積極財政議連がかつて提言した「軽減税率8%対象品のゼロ%化」を高市首相自身が支持しており、政権内でも再び検討が始まっています。
ただし、これは短期的な実施ではなく、景気回復の度合いを見ながら段階的に進める“中期プラン”と考えられます。
この政策群の狙いは明確です。
「可処分所得を増やし、民間主導の成長を促す」。
それこそが、高市政権の描く“経済再生の王道”なのです。
一方で、財務省を中心とする緊縮派の抵抗は避けられません。
だからこそ、高市首相は政務調査会・経済財政諮問会議の両輪を使い、政治主導で政策を通す仕組みを整えたのです。
この戦略が機能すれば、日本の税制は「増税依存」から「成長志向」へと大転換を遂げることになるでしょう。
財務省を封じる権力構造の再設計!高市政権が仕掛けた人事の妙
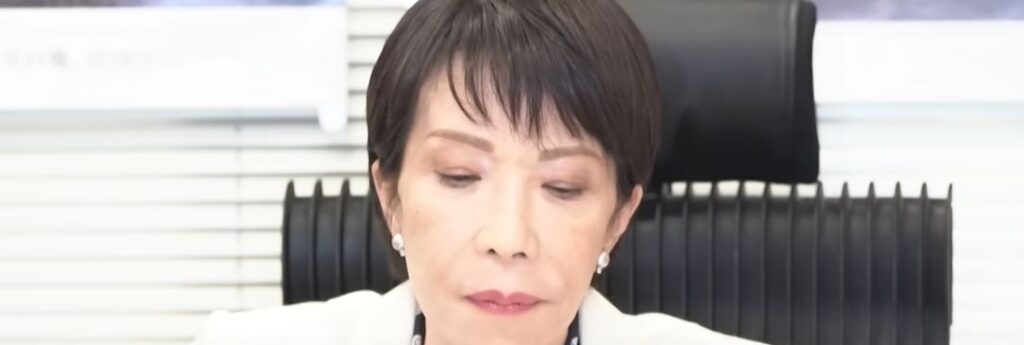
高市早苗政権の最大の特徴は、表向きの政策以上に「人事配置の戦略性」にあります。
須田慎一郎氏が指摘するように、今回の内閣人事は「財務省支配からの脱却」を目的として緻密に組み立てられています。
その中核を担うのが、政務調査会長・小林鷹之氏、経済財政政策担当大臣・城内実氏、そして財務大臣・片山さつき氏です。
この3人はいずれも「財務省主導政治の構造改革」を掲げており、官僚任せの予算編成を断ち切る布陣となっています。
特に政務調査会長の小林鷹之氏は、政策決定プロセスの透明化を重視し、“政治家が主導する政策立案”を掲げる改革派。
財務省の意向が通りづらくなるよう、各省庁間の調整メカニズムを再構築しています。
一方、経済財政政策を統括する城内実氏は、責任ある積極財政を推進してきた中心人物の一人。
彼の起用によって、経済財政諮問会議は財務官僚ではなく、政治主導で議題設定・方針策定を行う場へと変貌しました。
さらに、財務大臣に就任した片山さつき氏は、財務省OBでも派閥官僚でもない異色の存在。
彼女は“財政民主主義”を信条とし、財務省内部の硬直した審議会構造を見直す意向を明確にしています。
これらの人事は単なるポストの交代ではなく、「権限の流れを政治家側へ戻すための再設計」です。
予算を決める権利を誰が持つのか──その主導権を財務省から取り戻す。
この構造改革こそが、高市政権の“見えざる革命”なのです。
日本経済再生の鍵は「実行力」──高市政権が迎える最大の試練

高市早苗内閣が掲げる積極財政と減税路線は、長く続いた日本の停滞を断ち切る可能性を秘めています。
支持率60%超という数字は、国民が“我慢の政治”ではなく、“行動の政治”を望んでいることを明確に示しています。
しかし、その道は決して平坦ではありません。
最大の壁は、依然として財務省の抵抗と、既得権益層による“水面下の牽制”です。
財務官僚は、緊縮財政の枠組みを守るために制度と慣習を駆使し、減税議論を封じ込めてきました。
この「見えない抵抗」を打ち破るには、政治的リーダーシップと世論の後押しが不可欠です。
一方で、もし高市政権が掲げる改革が実現すれば、日本経済は30年ぶりに本格的な成長局面を迎えるでしょう。
ガソリン税の廃止、年収の壁の引き上げ、そして消費税の段階的減税。
これらが実現すれば、可処分所得が増加し、消費と投資の好循環が生まれます。
結果として税収も自然に増える──まさに「成長による財政再建」のモデルが現実味を帯びるのです。
ただし、もう一つのリスクは「期待先行」です。
国民の期待が高すぎれば、実現の遅れが失望に変わる危険があります。
高市政権に求められるのは、スピード感ある実行と、結果を可視化する戦略的な広報です。
つまり、これからの政治は「何を言うか」ではなく、「何を成し遂げるか」で評価される時代へと移行します。
財務省を封じ、経済の血流を取り戻せるか──。
この挑戦が成功すれば、日本は再び“成長する国家”へと生まれ変わるでしょう。
「政治が経済を動かす」──。
その原点を取り戻す闘いが、いま始まったのです。

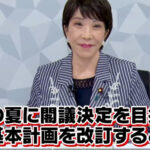




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません