「年少扶養控除の復活」国民民主党が改正案提出へ|子育て支援の第一歩
年少扶養控除の復活とは?—政策の概要と目的
国民民主党・新緑風会は、2025年10月、所得税法改正案と地方税法改正案の2本を国会に提出しました。目的は、かつて廃止された「16歳未満の年少扶養控除」を復活させることです。
この控除制度は、子どもを育てる家庭の所得税や住民税の負担を軽減する仕組みで、廃止以降は「子育て世帯の不公平感」を指摘する声が強くありました。全国の遊説や選挙活動でも、「年少扶養控除を戻してほしい」という要望が多数寄せられており、今回の法案提出はその声に応える形となりました。
提出者は国民民主党の議員2名、賛同者は23名。党としては、「子育て世代の経済的負担を軽くし、働く親を支える」ことを狙いとしています。さらに、この法案は単なる税制改正ではなく、政府が掲げる「異次元の少子化対策」を現実的な形で支える政策として注目されています。
具体的には、対象を0〜15歳の子どもとし、所得税では38万円、地方税では33万円の扶養控除を新たに設ける内容です。所得税法の改正は2026年1月1日から、地方税法の改正は2027年1月1日から施行予定です。
この動きは、子育て世代の家計に直接的な恩恵をもたらす可能性があり、同時に「子どもを育てることが不利にならない社会」への転換点と位置づけられています。
「年少扶養控除」廃止の経緯—なぜ失敗とされたのか

「年少扶養控除」とは、16歳未満の子どもを扶養する家庭に対して、税負担を軽減する仕組みとして設けられていた制度です。しかし、2010年度の税制改正で、当時の民主党政権により廃止されました。理由は、「子ども手当(現・児童手当)」の創設に伴い、現金給付で子育て支援を行うという方針に転換したためです。
当時は「所得控除よりも直接給付の方が公平」との考え方が主流でしたが、結果的に、共働き世帯や中間所得層の負担増を招くことになりました。特に、子どもが複数いる家庭ほど税負担が重くなり、「子どもを持つほど損をする」という皮肉な状況が生まれたのです。
さらに、児童手当の支給額は一律であり、所得制限も導入されたため、一定以上の所得層では恩恵が限定的でした。そのため、「手当も控除も減った」「実質的に増税になった」との不満が広がり、年少扶養控除の廃止は“子育て罰”とまで呼ばれるようになりました。
こうした経緯を踏まえ、国民民主党は今回の法案を「過去の誤りを正す第一歩」と位置づけています。単に控除を戻すだけでなく、子育て世代の生活実感に寄り添った再設計を目指す点が大きな特徴です。
少子化が深刻化する現在、働く親たちが「報われる」と感じられる制度への転換は、税制面からの少子化対策としても大きな意味を持ちます。
復活案の狙いと意義—“働いても報われる社会”へ

今回の「年少扶養控除復活法案」は、単なる税制の見直しにとどまりません。国民民主党が掲げる狙いは、「働いても報われない」現状を変えることにあります。
現在の日本社会では、共働きが当たり前になっている一方で、子どもを育てながら働く家庭ほど出費がかさみ、税・社会保険の負担も増しています。特に16歳未満の子どもを持つ家庭は、教育費・生活費・保育料などが集中する時期にありながら、税制上の恩恵が薄いという現状があります。
年少扶養控除を復活させることで、こうした家庭の手取り収入を直接的に増やすことができます。例えば、所得税の控除額38万円・地方税33万円の合計71万円が対象となれば、年収600万円前後の家庭で実質的に数万円単位の減税効果が見込まれます。
この政策の意義は、単なる減税ではなく、「子どもを持つことが経済的に不利にならない社会」を実現する点にあります。国民民主党は、少子化対策を本気で進めるには、家庭の経済的安心が不可欠だと主張しています。
また、今回の法案は「高校生年代の控除削減方針」との整合性も意識しており、全体のバランスを取りながら制度の再構築を図る狙いがあります。政府が掲げる「異次元の少子化対策」を、より現実的で効果的な形にするための一手といえるでしょう。
つまり、この改正案は、「子育て罰の是正」から「子育て報酬の社会」へという転換を目指す、象徴的な政策なのです。
所得税法・地方税法の改正内容を詳しく解説

今回の法案は、国民民主党・新緑風会による所得税法改正案と地方税法改正案の2本立てです。どちらも「0〜15歳の子ども」を扶養する家庭を対象に、税負担を軽減することを目的としています。
所得税法改正案の内容
所得税法改正案では、16歳未満の子ども1人あたり38万円の扶養控除を復活させます。これは2010年まで存在していた水準と同じです。控除が復活すれば、課税所得から38万円が差し引かれるため、所得税の税率が10%の家庭なら、およそ3万8千円の減税効果となります。
施行時期は令和8年(2026年)1月1日を予定。年末調整や確定申告の際に、16歳未満の扶養親族を再び控除対象に含める形になります。
地方税法改正案の内容
一方で、地方税法の改正では、住民税における控除額を33万円と設定。施行時期は所得税より1年遅れの令和9年(2027年)1月1日です。これは、前年の所得を基に課税される仕組みのため、実際の適用時期に1年のズレが生じます。
税収減と財源補填の仕組み
2つの改正による税収減は、合わせておよそ4,710億円と試算されています。この規模の減税は自治体財政にも影響しますが、法案には「財政補填は国が責任を持って行う」ことが明記されており、地方自治体へのしわ寄せを防ぐ仕組みが組み込まれています。
生活者にとっての意味
この控除復活により、家庭の税負担は実質的に軽減されます。たとえば子どもが2人いる場合、所得税と住民税を合わせて年間7万円前後の減税が期待できます。教育費や食費が高騰する中で、この金額は決して小さくありません。
つまり、この法案は「少子化対策」と「家計支援」を両立させる現実的な政策として、多くの子育て世代にとって大きな関心を集めています。
子育て世代の家計に与える影響—試算と実例

「年少扶養控除」の復活は、子育て世帯の税負担を直接的に軽減します。では、実際にどれくらい家計に影響するのでしょうか?ここでは、年収別・子ども人数別にシミュレーションを行い、具体的な数字で見ていきます。
年収別の減税シミュレーション
| 年収(給与所得者) | 子どもの人数(16歳未満) | 所得税+住民税の減税効果 |
|---|---|---|
| 400万円 | 1人 | 約5万5,000円 |
| 600万円 | 1人 | 約6万5,000円 |
| 600万円 | 2人 | 約13万円 |
| 800万円 | 2人 | 約14万5,000円 |
上記の通り、年収600万円前後の共働き世帯では、子どもが2人いる場合におよそ13万円前後の実質減税となる試算です。これは、年間で教育費の教材費や給食費、あるいは習い事1〜2か月分に相当する金額です。
共働き世帯・一人親家庭にも恩恵
この改正のメリットは、専業主婦世帯だけでなく共働き家庭や一人親家庭にも等しく適用される点にあります。特に、児童手当では所得制限があるため、一定の所得を超える家庭は支援が薄くなっていました。しかし、所得控除の形であれば、子どもの人数に応じて減税効果が得られます。
たとえば、共働きで夫婦それぞれが扶養控除を申告できるケースでは、世帯全体でより大きな手取り増が期待できます。一人親家庭にとっても、手取りの増加は生活の安定につながり、教育投資にも回しやすくなるでしょう。
物価高への対抗策としても
近年の物価高や光熱費の上昇を踏まえると、年少扶養控除の復活は「子育て世帯の防衛線」としても意味を持ちます。単なる減税ではなく、家計の安定を支える実質的な支援策といえます。
家計に余裕が生まれれば、消費や教育への支出も活発になり、地域経済への波及効果も期待されます。つまり、今回の法案は子育て世帯だけでなく経済全体にプラスの効果をもたらす可能性があるのです。
他党の動きと今後の見通し

国民民主党が提出した「年少扶養控除復活法案」は、子育て世帯を中心に大きな反響を呼んでいます。注目すべきは、この動きが与党や他の野党との間でも連携の可能性を生みつつあることです。
公明党との協議と連携
公明党はかねてより「子育て支援の充実」を党の柱として掲げており、国民民主党とは税制面での協議を継続しています。実際、昨年の税制改正でも公明党の主導で扶養控除削減を食い止めた経緯があり、今回の復活案にも一定の理解を示しています。
国民民主党の玉木代表は、公明党の岡本政調会長と連携を進めており、今後、両党が共同提出に踏み切る可能性もあります。少子化対策を政治の最重要課題と位置づける点で、両党の方向性は一致しています。
与党・野党の反応
自民党内部でも、「年収の壁」対策を進める中で、扶養控除の在り方を見直す議論が進んでいます。特に、共働き世帯への支援強化を求める声が強く、国民民主党の提案を参考にする動きも出ています。
一方で、立憲民主党や日本維新の会も「子育て世帯への負担軽減」を訴えており、党派を超えた協議の場が生まれつつあります。今後、複数政党が合意形成を進めれば、国会での成立可能性も現実味を帯びてきます。
今後のスケジュールと展望
法案の成立を目指すのは、現在開かれている臨時国会(2025年秋)です。国民民主党は、来年度の税制改正時期に合わせて、2026年1月の所得税施行に間に合わせたい考えです。
実現すれば、2027年度の住民税にも順次反映され、全国の子育て世帯に影響が広がります。政治的な駆け引きはあるものの、少子化の危機が深刻化する今、「子育て世帯の支援」という目的で一致できるかどうかが鍵となります。
世論の動向
世論調査では、「年少扶養控除を復活すべき」という意見が6割を超える調査結果も出ています。これは、家計の負担増を実感する家庭が多く、現金給付だけでは支援が足りないという社会的背景を反映しています。
この流れを受けて、他党も「税制を通じた子育て支援」の重要性を再評価しており、今後の国会論戦の焦点の一つになることは間違いありません。
まとめ—子育て世代に本当に必要な税制とは

国民民主党が提出した「年少扶養控除の復活法案」は、単なる税金の見直しではなく、「子どもを育てる家庭をどう支えるか」という社会全体の在り方を問う政策です。
少子化が進み、共働き世帯が増える中で、「子育て世帯の税負担が重すぎる」という声は年々強まっています。児童手当などの現金給付も大切ですが、それだけでは中間所得層の家庭を十分に支えられていません。今回の法案は、その隙間を埋めるように税制面から家計を支援するアプローチを取っています。
特に、所得税38万円・住民税33万円という控除額は、子どもの人数が多い家庭ほど効果を実感できる内容です。物価上昇や教育費の負担が続く今、「減税=子育て支援」という形で支援策を多層化することは現実的かつ有効な選択と言えるでしょう。
また、この法案は「国が財政補填を担う」と明記しており、地方自治体への負担を防ぐ点でも評価されています。単なるポピュリズム的な減税ではなく、持続可能な制度設計を意識している点も特徴的です。
今後の焦点は、与野党間での合意形成と、2026年度からの施行に向けたスケジュール調整です。公明党や維新、自民党との協議が進めば、実現への道は見えてくるでしょう。
子育ては「個人の責任」ではなく「社会全体で支えるもの」。
その理念を税制の仕組みで実現しようとする今回の法案は、まさに“真の異次元の少子化対策”への一歩といえます。
今後も「年少扶養控除の復活」をめぐる議論から目が離せません。子育て世代にとって本当に報われる社会を実現するために、政治の動きを注視していく必要があります。
関連記事:
▶ 日経新聞|年少扶養控除復活をめぐる与野党協議
▶ 読売新聞|国民民主党「子育て罰」是正の税制提案
▶ NHKニュース|子育て支援と税制改正の最新動向
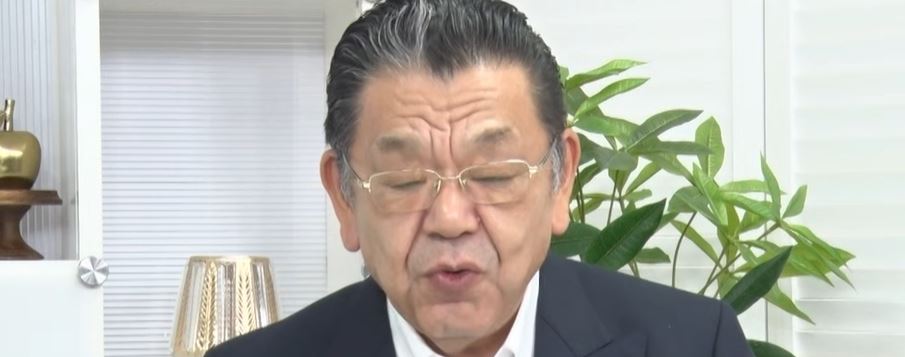



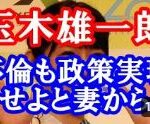
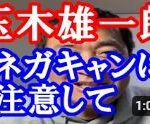

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません