東京株終値4万8580円 最高値更新 高市政権への期待が
アバン:高市早苗、自民党初の女性総裁誕生——永田町の空気が変わった
2025年9月、自民党総裁選の結果が報じられた瞬間、
永田町の空気が一変した。
「勝ったのは、高市早苗。」
その一報は、与野党の議員たちだけでなく、永田町記者クラブ全体を震撼させた。
前政権・石破茂内閣の求心力が急速に失われ、
党内保守派が結束して高市氏を押し上げた今回の総裁選。
長らく“ポスト石破”として囁かれながらも、
財務省や公明党の支持を失った石破派が瓦解する形での政権交代となった。
この瞬間、日本の政治は大きく舵を切った。
女性初の自民党総裁という象徴的なニュースであると同時に、
それは「戦後政治の均衡」が音を立てて崩れる転換点でもあった。
背景:石破政権の失速と“保守回帰”の機運
岸田後の「調整型政治」への限界
石破茂内閣が発足したのは2023年秋。
岸田政権末期の迷走を受け、「国民に寄り添う穏健政治」を掲げて登場した。
だが、結果的に石破政権は、官僚主導・財務省寄りの政策を踏襲。
増税、エネルギー政策の後退、中国との距離の曖昧さ——
どれもが支持層を失望させた。
特に2024年の「防衛費抑制」と「所得税見直し」は決定的だった。
保守層は「国家を守らず、国民を締めつける政権」と批判を強め、
石破内閣の支持率は30%を割り込む。
高市待望論の再燃
その空白を突いたのが高市早苗氏だった。
総務相、経済安全保障担当相としての経験を背景に、
「強い国家」「財政再建より経済成長」「中国依存脱却」を訴える。
特にSNS上では「真正保守の復権」を求める声が拡大し、
自民党内でも若手議員を中心に高市支持が広がった。
そして2025年夏、自民党総裁選での圧勝劇につながる。
本題①:高市政権誕生が映す「表の動き」
連立の亀裂、公明党の苦渋
高市総裁誕生の直後、最も揺れたのは公明党だった。
石破政権下で連立を維持してきたが、
高市氏の「防衛力強化」「教育改革」「ジェンダー政策見直し」路線は
創価学会支持層の理念と真っ向からぶつかる。
2025年10月現在、公明党は「政策協定の見直し」を表明。
与党協議の継続を模索しつつも、
次期衆院選では“選挙区調整の見直し”をちらつかせている。
野党の反応とメディアの論調
立憲民主党は「危険な国家主義の台頭」と批判を強め、
共産党も「戦後民主主義の否定」との声明を発表。
一方、国民民主や維新の会は「現実的な保守改革」として、
高市政権への協調姿勢を示している。
メディアの論調は分裂した。
主要紙は「保守回帰への懸念」を表明するが、
一部経済誌や海外メディアは「日本の政治的安定化」を評価。
高市政権の登場は、国内外の政治地図を塗り替えつつある。
本題②:永田町の裏で蠢く権力構造
財務省・外務省との静かな攻防
高市政権の誕生で、最も大きく変わるのが「官僚主導の構造」だ。
石破政権が依存していた財務省主導の政策決定を見直し、
内閣府主導の「成長戦略会議」を設置。
これは、財務省の増税路線を牽制する明確な動きと見られている。
一方で外務省との関係は微妙だ。
高市氏が米中対立の中で「対米強化・対中警戒」を打ち出す中、
外務官僚の一部が「外交バランスの崩壊」を懸念している。
自民党内の再編——「保守連合」誕生へ
党内では、旧安倍派を中心に「高市シフト」が進行中。
これに麻生派の一部、若手議員グループが合流し、
実質的な“保守連合”が形成されつつある。
一方、石破派や宏池会系の中道議員は、
「再び党内二極化が進む」と危機感を強めている。
次の焦点は、衆院解散とその後の政界再編だ。
本題③:国民生活への影響——期待と不安の交錯
経済政策「大胆な減税と国内回帰」
高市政権の経済方針は明確だ。
- 所得税の段階的減税
- 防衛産業・半導体・エネルギー分野への重点投資
- 財政健全化よりも「経済安全保障」を優先
この方針に、企業経営者や中小企業は歓迎の声を上げる一方で、
財政再建を重視する専門家からは「バラマキ」との批判も。
生活者の実感
物価高は依然として続くが、
ガソリン補助金やエネルギー価格抑制策により
家計の負担感はやや緩和傾向にある。
一方で、教育・福祉分野の支出抑制が懸念されており、
「強い国家」と「優しい社会」の両立が課題となる。
視点転換:海外の評価と国際比較
米国メディアは「日本版サッチャーの登場」と報道。
高市氏の明確な安全保障姿勢は、
東アジアの緊張を背景に歓迎されている。
しかし、中国・韓国の反応は冷ややかだ。
中国外務省は「対立を煽る政治家」と牽制し、
韓国メディアも「戦後最も保守的な政権」と批判的に論じる。
一方、ヨーロッパでは「民主主義国としての自立」として
好意的な評価が増えている。
国際社会でも、高市政権は“評価の分かれる改革者”として注目されている。
結論:戦後政治の終わりと新しい保守の形
高市早苗政権の誕生は、単なる人事の変化ではない。
それは、「戦後政治の延長線上」からの脱却宣言でもある。
戦後80年、日本は常に「調整と妥協」の政治を続けてきた。
だが、グローバル競争、少子高齢化、安全保障の危機。
もはや“中庸の政治”では対応できない。
高市政権の挑戦は、その“過渡期の現実”を象徴している。
右傾化か、再生か——。
評価は歴史が下すだろう。
エピローグ:新時代の始まりに、私たちはどう向き合うか
女性宰相の誕生は、日本社会にとって歴史的な瞬間だ。
だが、それは同時に「誰が日本を導くのか」を改めて問う出来事でもある。
政治家任せにせず、国民一人ひとりが
「どんな国をつくりたいのか」を考える時が来ている。
激動の2025年。
日本はいま、戦後体制の幕を下ろし、新たな時代へ踏み出そうとしている。




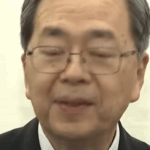
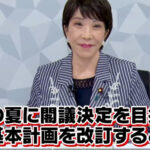
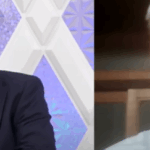
ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 東京株終値4万8580円 最高値更新 高市政権への期待が […]