【青山繁晴氏の見解】自公連立崩壊の危機と“玉木雄一郎内閣”誕生
第1部:現在の政局概要と首班指名選挙の仕組み
2025年10月現在、日本の政治情勢は極めて緊迫しています。本来であれば10月15日に実施される予定だった「首班指名選挙(しゅはんしめいせんきょ)」が、わずか数日のうちに延期される可能性が浮上し、永田町全体が騒然としています。背景にあるのは、公明党を中心とする与党内の対立、そして野党勢力による思わぬ連携の動きです。
まず「首班指名選挙」とは、衆議院および参議院の議員が国のリーダー=内閣総理大臣を選ぶために行う重要な選挙です。憲法第67条に基づき、衆議院・参議院の両院でそれぞれ投票が行われ、最終的には衆議院での結果が優先されます。衆議院の過半数は233票。つまり、233名の支持を得られなければ、首相にはなれません。
今回の焦点は、自民党の高市早苗新総裁がこの233票を確保できるかどうかにあります。自民党単独の議席は196議席。連立を組む公明党の31議席を加えても、227議席と過半数に6票足りません。わずか6票の差ですが、これが政権の存続を左右する重大な分岐点となっています。
さらに、衆議院で過半数を獲得できなければ、決戦投票が行われます。この決戦投票では「過半数」ではなく「より多くの票を得た候補」が首相に選ばれる仕組みになっています。つまり、公明党がどちらにつくか、また維新や国民民主がどの陣営を支援するかで、日本の次期首相が誰になるかが大きく変わるのです。
今回の首班指名選挙は、単なる形式的な「指名」ではなく、政権交代の可能性を秘めた実質的な「政権選択選挙」となりつつあります。自民党が政権を維持できるか、それとも野党連合による新体制が誕生するのか。政治の表舞台では見えない「水面下の駆け引き」が、今まさに加速しているのです。
実際、永田町では「17日にずれ込むのではないか」という情報が急速に広まりつつあります。選挙の延期は単なる日程変更ではなく、与野党間の調整の結果として発生する政治的判断です。公明党が与党としての立場を維持するのか、それとも独自の道を歩むのか──この選択が、今後の日本政治の方向を大きく左右します。
このように、首班指名選挙とは単なる儀式ではなく、「政治力の試金石」であり、各党の思惑や理念が交錯する舞台でもあります。2025年の選挙は、戦後政治史の中でも極めて稀な“緊迫した選挙”になることが予想されます。
第2部:公明党離脱の可能性とその影響
今回の政局で最も注目されているのが、公明党が自民党との連立を解消するのではないかという動きです。長年続いた「自公連立」が揺らぐ可能性が現実味を帯びてきました。これは単なる政党間の不和ではなく、政権の存続そのものを左右する重大な分岐点です。
もともと自民党と公明党は、政策的な違いを抱えながらも「選挙協力」という実利的な目的で連立を維持してきました。特に小選挙区制度の下では、公明党の組織票が自民候補の勝敗を左右するほどの影響力を持ってきました。しかし近年、公明党の支持母体である創価学会内部での高齢化や活動低下が指摘され、組織力そのものに陰りが見え始めています。
そうした中で、公明党内では「これ以上、自民党の保守政策に引きずられるわけにはいかない」という声が強まっています。特に高市早苗氏が総務大臣時代から続けてきた靖国神社参拝や、外国人受け入れに対して厳しい姿勢を取っている点について、公明党は外交的・人道的観点から強い懸念を表明しています。
公明党の斎藤鉄夫代表は2025年10月初旬の記者会見で、「靖国参拝はこれまでも外交問題に発展してきた。国際社会の信頼を損なう懸念がある」と述べ、明確に高市政権との距離を置く発言をしています。また、高市氏が強調する「スパイ防止法」「外国人受け入れ制限」「防衛強化」などの政策についても、公明党は「平和主義の理念と相容れない」として慎重な姿勢を崩していません。
このような政策的な乖離が進む中で、公明党が自民党から離脱する可能性が急速に高まっています。もし実際に離脱となれば、衆議院で自民党は過半数を割り込みます。196議席の自民に対し、公明党の31議席が抜けると、単独では到底政権を維持できません。結果として、首班指名選挙では野党連携側が233票を超え、政権交代の現実味が一気に増すのです。
この点について、青山繁晴参議院議員も「公明党が野党側に回れば、わずか1議席の差で野党が過半数を超える」と指摘しています。つまり、公明党が自民党を離れるだけで、政権の主導権が一瞬にして逆転する可能性があるということです。
さらに注目すべきは、公明党が「どこと組むか」という次の選択です。実は現在、維新の会と国民民主党の間で「玉木雄一郎代表を次期首相候補に推す」という構想が水面下で進んでいます。もし公明党がこれに加われば、立憲民主党・維新・国民民主・公明の連携によって、衆議院で234議席という過半数を実現する計算になります。
公明党が野党側につくというシナリオは一見非現実的に思えるかもしれません。しかし、これまでの政治史を見れば、政権維持よりも「理念の整合性」を優先して連立を離脱した前例も少なくありません。かつての細川連立政権や民主党政権誕生の際も、同様の「政策転換の潮流」があったのです。
仮に公明党が正式に連立離脱を表明した場合、高市政権は少数与党として発足せざるを得ません。その場合、政権運営は極めて不安定となり、予算審議や法案審議のたびに野党との個別交渉が必要となります。さらに、参議院でも自民党単独で過半数を確保していないため、法案成立率は大幅に低下し、事実上の「ねじれ国会」状態に陥る可能性が高いと見られます。
公明党の離脱は、自民党にとって単なる数の問題ではなく、長年築いてきた「安定政権の象徴」を失うことを意味します。逆に、公明党にとっても「政権与党」という立場を失うリスクがあり、この決断は極めて重いものとなります。
いずれにせよ、今後の焦点は「高市政権がどのように公明党との関係修復を図るのか」、そして「公明党が連立維持か、理念重視の独自路線か」をどう判断するかにかかっています。連立の行方次第で、首班指名選挙の結果は180度変わる可能性があるのです。
第3部:維新・国民民主の動きと“玉木雄一郎総理”誕生の可能性
公明党の動向と並んで注目されているのが、日本維新の会と国民民主党の急接近です。今回の首班指名選挙では、この両党が「野党再編」の軸となり、さらには玉木雄一郎代表を首相候補に推す動きが水面下で進行していると報じられています。
政治評論家・青山繁晴氏も自身の発信で、「維新を中心に国民民主党の玉木氏を押し立てる構想が進んでいる」と指摘。これが実現すれば、立憲民主党や公明党を含めた“新連立政権”の誕生という前代未聞の展開もあり得る状況です。
実際、維新と国民民主党の関係はここ数年で急速に接近しています。両党とも「現実的な中道改革路線」を掲げており、旧民主党出身者を中心に政策的親和性が高いとされます。特に、経済政策や地方分権、教育改革といった分野では共通点が多く、「反自民」ではなく「改革保守」という立ち位置を取っている点が特徴です。
維新の藤田文武幹事長は、2025年10月上旬のインタビューで「野党が政権を取るためには、理念を超えて現実的な連携を模索する必要がある」と発言。玉木雄一郎代表のリーダーシップを評価する姿勢を明確にしています。また、国民民主党側も「是々非々で政権に向き合う」という方針を繰り返し表明しており、両党の歩調が一致しつつあるのは明らかです。
この「維新・国民民主連携」の背景には、自民党と公明党の関係悪化が大きく影響しています。仮に公明党が与党を離脱した場合、衆議院で自民党は過半数を割り込みます。そのとき、維新と国民民主が中心となって「新たな中道連立構想」を打ち出すことは、政治的にも極めて現実的な選択肢になります。
具体的な数字を見てみましょう。衆議院の過半数は233議席。現在の各党の議席数は以下の通りです。
- 自民党:196議席
- 公明党:31議席
- 立憲民主党:97議席
- 維新の会:41議席
- 国民民主党:13議席
- その他(れいわ・参政・保守など):約10議席
もし、公明党が野党側に回り、維新・国民民主・立憲と連携した場合、合計で234議席に到達します。つまり、わずか1議席差で野党側が過半数を超えることになるのです。この構図が実現すれば、「玉木雄一郎総理」の誕生が一気に現実味を帯びてきます。
玉木氏は元財務官僚であり、経済・外交両面に精通した実務型政治家として知られています。国民民主党の代表として「現実的な改革」「国益を守る政治」を掲げ、自民党との対立よりも政策協調を重視してきた姿勢は、維新や公明党にも受け入れやすいとされています。
さらに注目すべきは、玉木氏が掲げる「中道保守」の政治哲学です。これは単なるリベラルでもなく、極端な右派でもない、“現実的な国益路線”であり、国民の支持を幅広く取り込める可能性を秘めています。もし維新・公明・立憲・国民が合流し、玉木氏を中心とした新政権を樹立すれば、戦後日本の政治再編における「第三の道」が開かれることになります。
ただし、この連携にはいくつかの課題も残されています。まず、維新と立憲民主党の関係は必ずしも良好ではありません。特に大阪・関西圏では選挙区の争奪戦が激しく、地方レベルでの協力体制構築は容易ではないでしょう。また、公明党にとっても、創価学会の支持層が「自民党離脱」をどう受け止めるかは極めてセンシティブな問題です。
一方で、維新・国民民主両党の若手議員の間では「このまま自民党に任せておけない」という危機感が広がっています。特に維新内部では、大阪都構想をはじめとした地方行政改革を国政レベルで実現するために、「政権与党入り」への野心を持つ議員も増えています。彼らにとって、玉木氏のような現実主義的なリーダーは、連携相手として理想的なのです。
このように、「玉木雄一郎総理誕生」の可能性は単なる噂ではなく、議席構成と政策親和性の両面から見ても十分にあり得るシナリオです。もしこの構図が現実となれば、日本の政治地図は戦後最大級の変化を迎えることになるでしょう。
そして何より重要なのは、国民がこの動きをどう受け止めるかです。政治が理念ではなく「結果」を求められる時代において、現実的な改革を掲げる新勢力が台頭するのは必然の流れとも言えます。次期首班指名選挙は、単なる政党間の闘いではなく、「国の方向性を決める国民的選択」になるかもしれません。
第4部:今後の展望と高市政権のリスク
首班指名選挙を目前に控えた2025年10月現在、日本の政局は混迷を極めています。高市早苗氏が自民党総裁に就任して以降、政権運営の舵取りはかつてないほど難しい局面に立たされています。その最大の要因は、連立パートナーである公明党が「離脱を検討している」という事実にほかなりません。
公明党がもし正式に連立解消を表明すれば、自民党は衆議院で過半数を割り込みます。これにより、予算案や法案審議のたびに野党の協力が不可欠となり、政権の安定性は著しく低下します。特に防衛・外交分野の重要法案では、国民民主党や維新との個別交渉が不可避となるでしょう。
こうした政治的リスクを回避するため、自民党内ではすでに複数の対応策が検討されています。その一つが「新たな連立構想」です。公明党の代わりに、政策的に近い国民民主党や、保守色を強める賛成党・日本保守党との協力を模索する動きが出ています。これにより、自民党が掲げる「保守中道」「現実的改革」の路線を維持しつつ、右派層の支持を再び取り戻す狙いがあります。
実際、国民民主党の玉木雄一郎代表は「是々非々で政策に臨む」と繰り返しており、連立交渉の余地は十分にあります。また、賛成党や日本保守党も、移民政策の見直しやスパイ防止法制定といった保守的政策を強く支持しており、高市政権との親和性が高いとされています。
もう一つのシナリオが「解散総選挙」です。高市政権が発足から短期間で国会運営に行き詰まった場合、「国民に信を問う」という形で総選挙に踏み切る可能性も否定できません。特に、現在の日経平均株価は過去最高の4万8000円台に達しており、経済指標上は自民党に追い風が吹いています。株価の高止まりと円高の安定が続く今のうちに解散すれば、自民党が単独過半数を回復できる可能性もあると見られています。
しかし、ここにもリスクは存在します。近年の若年層や都市部有権者の間では、「自民党=既得権益」という印象が根強く、無党派層の約6割が「政権交代を望む」と答えた世論調査結果も出ています(2025年10月、共同通信調べ)。この傾向が続けば、解散総選挙が逆に政権崩壊の引き金となる可能性も否定できません。
また、高市政権の政策課題も山積しています。特に「スパイ防止法」の制定、「外国人政策の見直し」、「防衛費の倍増」など、いずれも賛否が分かれるテーマです。これらの法案を強行すれば野党との対立が激化し、逆に譲歩すれば保守層の支持を失うという、非常に難しいバランスを迫られています。
さらに、外交面でも中国・韓国との関係悪化が懸念されています。高市首相が就任後も靖国神社を参拝する意向を示したことで、近隣諸国からの反発が強まっており、公明党が「外交問題化を懸念している」として離反を示唆しているのもこの点が大きいと見られます。
一方で、もし自民党が公明党と決別し、保守路線を明確化すれば、右派系有権者や新興保守政党からの支持を再び集めることができます。特に、賛成党や日本保守党といった新勢力は、ここ数年で急速に勢力を拡大しており、ネット世論ではすでに「自民+賛成+保守党の新連立」を求める声も高まっています。
青山繁晴氏は最新の見解で、「高市政権が公明党との関係に固執すれば、かえって保守層を失うリスクがある」と警鐘を鳴らしています。その上で、「もし離脱が避けられないなら、理念を同じくする新勢力と共に“真の保守政権”を築くべきだ」と提言しています。
結論として、今後の焦点は3つに集約されます。
- 公明党が連立を維持するか、それとも離脱して野党側につくか。
- 自民党が国民民主や新保守勢力との新連立を構築できるか。
- 高市政権が解散総選挙を選ぶか、政権内での再編を図るか。
このいずれのシナリオを取るにせよ、日本政治は今、戦後最大級の転換点に立っています。高市政権が掲げる「国を守る政治」「現実的な改革」が形だけで終わるのか、それとも真の政治刷新につながるのか──その行方は、今後数週間の公明党の判断と、国民の支持動向にかかっています。
そして何より、政局の混乱を超えて問われているのは、「誰が首相になるか」ではなく「どんな日本を創るか」です。理念と現実の間で揺れる政治の中で、国民一人ひとりが“未来を選ぶ”意識を持つことこそ、真の民主主義の原点と言えるでしょう。


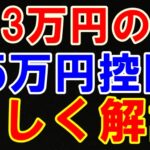



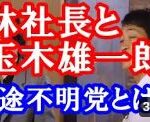
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません