自民・公明連立崩壊の危機?維新と国民が仕掛ける政界再編
自民・公明連立の綻びが表面化
2025年秋、政界の注目は「自民・公明連立の行方」に集まっている。高市早苗氏の新政権発足を目前に控え、公明党が連立継続に慎重な姿勢を見せているためだ。連立政権を支えてきた自民・公明の関係に、かつてない緊張が走っている。
公明党が抱える不満と「距離感」
自民党と公明党の連立は、1999年の小渕恵三内閣から25年以上続いてきた。しかし、公明党内部では近年「自民党の右傾化」や「政策調整の軽視」への不満が高まっている。特に高市氏が強く主張してきた靖国参拝やスパイ防止法制定など、安全保障色の強い政策は、公明党の支持母体である創価学会との思想的な隔たりを生んでいる。
さらに2025年10月に予定されている首班指名選挙を前に、自民党と公明党の協議が難航。日程の変更まで取り沙汰される異例の展開となった。青山繁晴参議院議員も自身のチャンネルで「水面下では公明党が野党側と接触している」と指摘しており、永田町では「連立解消の可能性」が現実味を帯びている。
背景にある支持基盤の変化
公明党の強みは、長年にわたって培われた全国的な組織票にある。しかし近年、創価学会員の高齢化や若年層の政治離れにより、その組織力は徐々に低下しているとされる。かつてのように「選挙の要」として自民党を支えるほどの動員力が減少しているのが現実だ。
一方で、自民党内部でも「公明党への過度な配慮が改革の妨げになっている」との声が出始めている。特に安全保障・移民・教育分野では、公明党との調整が遅れ、政策実行のスピード感を失う場面も多い。高市氏が掲げる「国家の安全と自立」を軸とした政策を貫くには、従来の連立構造が限界に近づいているとの見方もある。
安倍・菅政権との違い:高市政権の独自色
安倍・菅政権下では、公明党との関係は実務的に安定していた。特に外交・防衛政策においては、最終的に調整が図られ、表面上の衝突は避けられていた。しかし、高市政権ではそのバランスが崩れ始めている。高市首相は「外交で妥協しない」「国益を最優先にする」と明言しており、その断固とした姿勢が公明党の慎重論と真っ向から対立しているのだ。
また、公明党代表・斉藤鉄夫氏は、高市氏が閣僚時代から続けてきた靖国参拝に対して「外交上の問題を引き起こす懸念がある」と異例の批判を行った。これにより、両党間の関係はさらに冷却化。連立解消を含む選択肢が現実的なテーブルに乗り始めている。
「政策連立」から「理念連立」への転換期
もともと自民・公明の関係は「政策のすり合わせによる実務連立」だった。しかし今後は、理念・価値観の不一致がより深刻化する可能性がある。高市政権が推し進めようとしている防衛力強化・外国人政策の見直し・スパイ防止法などは、公明党の掲げる「平和主義」と相容れない部分が多い。
このため、政権内部ではすでに「公明党を含まない新たな連立構想」も検討されているという。候補に挙がるのが、国民民主党や賛成党、日本保守党との政策連携だ。これらの党は、高市氏の保守路線に一定の理解を示しており、将来的な政権再編の中心軸となる可能性もある。
政権の転換点に立つ自民党
公明党との関係が揺らぐなか、自民党は「連立維持」か「自立路線」かの選択を迫られている。仮に公明党が離脱すれば、衆議院での過半数(233議席)維持は危うくなる。だが、保守層の結集や新党との協力によって、単独過半数を取り戻す戦略もあり得る。
いずれにせよ、今回の綻びは単なる政党間の軋轢ではなく、戦後日本の政治構造そのものを揺るがす可能性を秘めている。長年続いた「自公体制」の終焉が、現実のシナリオとして浮かび上がってきたのだ。
次章では、この動きの裏で静かに進む「維新と国民民主による逆転シナリオ」について詳しく見ていく。
維新と国民民主が描く逆転シナリオ
自民・公明の連立が揺らぐなか、静かに台頭しているのが日本維新の会と国民民主党だ。両党はこれまで野党として自民党に対峙してきたが、近年の政策協議を通じて、現実的な連携関係を築きつつある。2025年の首班指名選挙を前に、水面下で「政権奪取の布石」を打っているとの見方も強まっている。
玉木雄一郎氏を中心とした「野党再編構想」
この動きの中心にいるのが、国民民主党代表の玉木雄一郎氏である。温厚で現実的な政治スタンスを持つ玉木氏は、野党の中でも「与党との協調を辞さない pragmatist(現実主義者)」として知られる。青山繁晴参議院議員によれば、維新の一部議員が「玉木氏を次期首相候補として推す」構想を検討しているという。
衆議院の議席数を単純に合算すると、立憲民主党・国民民主党・維新を合わせて約200議席となる。過半数の233議席には届かないものの、ここに公明党が加わるだけで234議席に達し、過半数を超える計算になる。この「1議席差の攻防」が、まさに現在の政局の最大の焦点なのだ。
維新が描く「現実的保守」戦略
維新は当初、高市政権の誕生を歓迎していた。大阪を拠点とする維新は、自民党と政策的に近い部分も多く、特に経済・行政改革の分野で協調の余地があった。しかし、維新内部では「大阪都構想の再起動」や「地方分権の拡大」をめぐって自民党との摩擦が生じており、関係は微妙に変化している。
さらに、奈良県知事選挙で維新系候補が高市氏が支持した候補を破ったことが両者の関係を悪化させた。維新の吉村洋文代表は「高市政権が公明党に依存している限り、改革は進まない」と周囲に漏らしており、政界再編への布石を打つ構えを見せている。
藤田文武幹事長が握るカギ
維新の藤田文武幹事長は、政策通として知られる存在であり、与野党双方とのパイプを持つ。彼は以前から「政策本位の連携」を掲げており、イデオロギーよりも実務を優先する立場だ。藤田氏は水面下で国民民主党・立憲民主党の幹部と接触し、「玉木雄一郎氏を首相に推す場合、維新が支援に回る」可能性を探っている。
この動きが現実化すれば、衆議院での多数派構成は一変する。自民党が公明党を失った場合、233議席に届かず、逆に野党連携が過半数を獲得することになる。まさに「1票差の政変」が起きる瞬間だ。
「理念」より「政権交代」――野党の共通目標
維新・国民民主・立憲の三党に共通するのは、「理念よりも政権交代を優先する」という現実的な発想だ。特に玉木氏と藤田氏は、「反自民」ではなく「政権を動かせる野党」になることを目指している。この柔軟さが、公明党との連携にも現れている。
公明党にとっても、野党連携への参加は「完全な敵対」ではない。自民党との関係を維持しながらも、政策ごとに柔軟に立ち位置を変える「中道軸」として存在感を高めることができる。こうした戦略的曖昧さこそ、公明党が長年政権の一角を担ってきた理由でもある。
玉木氏の“キングメーカー”化
政治評論家の間では、玉木雄一郎氏が「キングメーカー(政権の決定権を握る人物)」になるとの見方も出ている。彼が野党間の調整役として信頼を得ている点に加え、経済政策・外交・安全保障でも中道的で現実的な提案を行っているからだ。
たとえば玉木氏は、エネルギー安全保障の観点から原発再稼働の必要性を訴え、また物価高騰対策として消費減税を提案している。これらの政策は、自民党右派や維新の一部とも一致しており、「政策連携の基盤」として機能しうる。
水面下で進む“野党内閣構想”
永田町関係者の証言によると、維新・国民民主・立憲の一部議員の間では、すでに「野党内閣構想」が検討されているという。首相に玉木雄一郎、副総理に維新の藤田文武、外相に立憲の泉健太――といった人事案まで具体的に議論されているとの情報もある。
この構想の背後には、「自民・公明体制に代わる新しい政権モデルを国民に提示する」という狙いがある。つまり、単なる政権奪取ではなく、日本政治の新しい枠組みを再定義しようという意図だ。
現実味を帯びる「逆転劇」
仮に公明党が野党側についた場合、衆議院での勢力バランスは完全に逆転する。さらに参議院でも、公明党が立憲・維新・国民と協調すれば、過半数を超える107議席体制が成立する。この「政権交代のシミュレーション」は、単なる机上の空論ではなく、すでに複数の党で想定されている現実的なシナリオだ。
こうした状況下で、維新と国民民主は「改革型の連立」を掲げ、既存の自公連立とは異なる政治手法を打ち出そうとしている。それが実現すれば、戦後政治の最大の地殻変動になることは間違いない。
次章では、この政変の中心に立たされている高市政権のリスクと閣僚人事の行方について掘り下げていく。
高市政権のリスク:閣僚人事と連立崩壊の連動
新政権発足に向けて注目を集めている高市早苗首相だが、閣僚人事をめぐる動きが政権の安定を左右する重要な要素になりつつある。特に、公明党の動向が読めない中での人事判断は、連立の継続か崩壊かを分ける“時限爆弾”のような意味を持つ。
閣僚人事が引き起こす「連立不信」
高市政権の閣僚人事は、自民党内外から「大胆すぎる」との声が上がっている。特に注目されているのは、外務・防衛・法務といった安全保障関連のポストだ。高市首相がこれらのポジションに保守系議員を多数起用したことで、公明党は「バランスを欠く」と不快感を示している。
公明党関係者によれば、「安全保障政策での意見交換の場が減った」「重要ポストに意見を反映できない」との不満が噴出しているという。こうした不信感が積み重なり、連立解消論に拍車をかけている。
高市首相が描く「自立路線」
高市早苗首相は、これまでの自民党政権が取ってきた「連立による安定」よりも、「自主独立の政治」を志向しているとされる。彼女の政治哲学は明確だ――「国家の安全と自立を最優先にする」。この理念が、外交・防衛・経済安全保障の分野で一貫している点は、国内外から高く評価されている。
しかし同時に、この姿勢が公明党との対立を決定的にしている。靖国参拝やスパイ防止法の制定、外国人政策の厳格化など、公明党が慎重な立場を取る政策を高市政権は次々と打ち出している。公明党代表・斉藤鉄夫氏が「高市政権の政策には大きな疑問がある」と発言したのは、こうした背景によるものだ。
「閣内協力」から「閣外協力」へ?
政権内では、公明党を閣内から外し、政策協力のみにとどめる「閣外協力」案も検討されている。これはかつての細川連立政権(1993年)の形に近いモデルで、政策ごとに賛同を得る形だ。しかし、これは実質的な「連立崩壊」と同義であり、衆議院での過半数確保が極めて困難になるリスクを伴う。
一方で、高市政権に近い保守派議員の中には、「公明党に配慮して国家安全保障が遅れるなら、いっそ単独政権で構わない」との強硬意見もある。彼らは、連立よりも政策の一貫性を重視しており、短期的な議席減少よりも、長期的な国益を優先すべきだと主張している。
政権運営の焦点:人事と信頼関係
政治の世界では、「人事は最大のメッセージ」と言われる。高市首相が誰を閣僚に登用し、誰を外すかは、そのまま政権の方向性を示すサインになる。特に、公明党出身者を要職から外すような人事を行えば、それは事実上の連立解消宣言となる。
一方で、公明党の意向を尊重し、1~2名の閣僚ポストを割り当てる形を取れば、表面的な連立維持は可能だ。だが、それでも根本的な理念の違いは埋まらず、政権の不安定要因が残り続ける。
自民党内の「連立維持派」と「自立派」
自民党内部でも意見は割れている。茂木敏充幹事長や岸田文雄前首相らは「連立維持派」として、公明党との協調を続ける方針を支持している。一方で、安倍派・高市派・麻生派の一部は「自立派」として、公明党に依存しない政権運営を模索している。
この構図が、次の衆議院解散・総選挙における最大の争点になる可能性が高い。つまり、「安定を取るか、改革を取るか」という選択である。
支持率と経済指標が後押しする「強気の高市政権」
興味深いのは、こうした政治的混乱の中でも、内閣支持率が45〜48%前後で安定している点だ。さらに、日経平均株価は史上最高値の4万8000円台を記録し、経済的な追い風が政権を支えている。これが「解散総選挙カード」を切る現実的な選択肢として浮上している理由である。
もし高市政権がこのタイミングで解散に踏み切れば、世論の支持を背景に自民党単独過半数を狙う可能性がある。そうなれば、公明党との連立に依存しない“純粋保守政権”が誕生するシナリオも見えてくる。
閣僚人事がもたらす「政治再編の引き金」
結局のところ、閣僚人事は単なるポスト争いではない。誰がどのポジションに就くかによって、政権の方向性も、連立の存続も変わる。高市首相が「改革と信念」を優先すれば公明党との溝は深まり、逆に「安定と妥協」を選べば保守層の支持を失う。まさに“政治の二律背反”が現れている局面だ。
次章では、連立崩壊後のシナリオ――すなわち「単独政権」「新連立」「解散総選挙」という3つの道筋について展望していく。
日本政治の今後:単独政権か、新たな連立か
公明党の離脱が現実味を帯びる中で、永田町では「次の政権の形」をめぐる議論が本格化している。高市早苗首相率いる自民党が、今後どのような選択を取るのか。その一手が、日本の政治構造を大きく変える分岐点になる可能性がある。
シナリオ①:自民党の「単独政権」路線
まず最も注目されるのが、自民党単独政権の可能性だ。高市政権は現在、国民の支持率を背景に、単独での政権運営を現実的な選択肢として視野に入れている。背景には、経済の安定と外交面での存在感の向上がある。
日経平均株価は過去最高水準の4万8000円台を維持し、円安基調のなかで輸出関連産業が好調だ。内閣支持率も40%台後半と比較的高く、解散総選挙を打てば「保守層結集」によって単独過半数の獲得を狙えるという見方が党内に広がっている。
この路線のメリットは、政策決定のスピードと一貫性が高まることだ。高市首相が掲げるスパイ防止法制定・移民政策の見直し・防衛費の増額など、保守的かつ実行力のある政策が実現しやすくなる。
ただし、課題も多い。公明党の協力を失えば、参議院での法案可決が難しくなるほか、地方選挙での組織票が減るリスクも大きい。そのため、「単独政権」は高市政権にとって大胆かつ危険な賭けでもある。
シナリオ②:維新・国民民主との「新連立構想」
次に現実味を帯びているのが、維新・国民民主との新連立だ。この構想は、既存の自公体制に代わる「政策連携型連立」として注目されている。自民党内の一部保守派、特に若手議員の間では、「改革志向の維新」と「現実路線の国民民主」との協力を前向きに評価する声が増えている。
この新連立では、理念よりも「政策実行力」に重きを置く。経済改革・行政スリム化・教育支援・防衛強化など、3党が合意可能な領域は多い。特に国民民主の玉木雄一郎代表が首班候補として支持を集めていることは、高市政権にとっても無視できない現実だ。
政治評論家の間では、この枠組みを「現実保守連立」と呼ぶ声もある。自民党が公明党に代えて維新・国民民主と協調すれば、保守中道を中心とした安定政権が誕生する可能性があるのだ。
シナリオ③:解散総選挙という“最終手段”
3つ目の選択肢は、解散総選挙による信を問う戦略だ。高市首相は、党内外からの圧力が強まれば、国民に直接支持を求める「解散カード」を切る可能性がある。現在の世論調査では、「高市政権を支持する」が40%台後半に達しており、追い風の中で選挙を行えば勝算は高い。
仮に選挙で自民党が大幅に議席を伸ばせば、公明党に頼らない新体制を築くことができる。逆に議席を減らせば、高市政権の求心力が低下し、政界再編が一気に進むだろう。まさに「勝てば続投、負ければ再編」というゼロサムの決断になる。
政界再編のカギを握る「中道保守層」
今回の政変の中心には、イデオロギーよりも「実利と現実」を重視する中道保守層がいる。彼らは、極端なリベラルでも右派でもなく、「安全保障と経済のバランス」を求める層である。維新や国民民主が支持を拡大しているのは、この中道保守層をうまく取り込んでいるからだ。
自民党がこの層を再び取り戻せるかどうかが、今後の日本政治の命運を分けるだろう。特に若年層や都市部の有権者は、「イデオロギーより成果」を重視する傾向が強くなっており、政党間の再編が進む可能性も高い。
「戦後体制の終焉」と「新しい政治秩序」
長年続いた自公連立は、戦後日本政治の安定装置だった。しかし、その安定が制度疲労を起こしつつある今、政治の新しい秩序が求められている。高市政権の登場は、その転換点を象徴していると言える。
日本政治は、これから「安定と変革」「理念と現実」の間で揺れ動くだろう。だが、その中で問われるのはただ一つ――誰が国家の未来を真剣に考え、責任を持って行動するのかという点である。
自民党が自立を選ぶのか、あるいは新連立に踏み出すのか。いずれの道を選んでも、日本政治は確実に次のステージへと進む。その一歩が、2025年秋、主犯指名選挙の場で明らかになるだろう。
この記事の結論:
連立崩壊はもはや「可能性」ではなく「現実的シナリオ」。 高市政権は今、戦後政治を再定義する重大な岐路に立っている。
――この動きの行方を追い続けることが、私たち有権者にとっての最大の政治関心となる。
- 高市早苗の政策ビジョンとは?防衛・経済・外交の3本柱を徹底解説
高市政権の核心である「国家の安全保障」「経済安全」「外交戦略」をわかりやすくまとめました。 - 公明党離脱の真相|連立解消の可能性と創価学会の組織力低下
25年続いた自公連立がなぜ揺らいでいるのか。創価学会の支持構造と内部事情を分析。 - 玉木雄一郎が狙う新政権構想|国民民主党の現実路線と維新連携の真意
次期首相候補と目される玉木氏の政治戦略と、維新との政策連携の全貌を解説。 - 日本維新の会の改革路線とは?都構想から国政戦略まで
維新が描く“ポスト自民”の青写真を分析。大阪から全国へ、改革の波はどこまで広がるか。 - 自民党内の保守再編が進行中|連立崩壊後の勢力図を予測
自民党内で台頭する“自立派”と“連立維持派”の対立構造をわかりやすく整理。





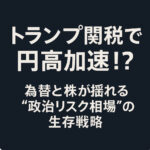

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません