高市早苗が永田町で集中攻撃?発言騒動と全国紙記者の噂、週刊誌報道に見る情報戦・ネガティブキャンペーンの裏側
自民党総裁選の幕開けと情報戦の激化
2023年9月22日、自民党総裁選がついに本格的な選挙戦へと突入しました。総裁選は自民党の次期総裁を選び、日本の総理大臣を事実上決定する重要な政治イベントです。そのため、各候補者が掲げる政策やビジョンに注目が集まるのはもちろんですが、裏ではさまざまな情報戦やネガティブキャンペーンが繰り広げられることでも知られています。
政治の世界において「選挙戦」とは単なる政策論争にとどまりません。特に総裁選のように党内の権力闘争が絡む場面では、候補者同士が直接討論するだけでなく、メディアを通じた印象操作やスキャンダル報道なども大きな役割を果たします。これは単なる偶発的なニュースではなく、戦略的に仕掛けられる「情報戦」の一部であることが少なくありません。
今回の総裁選においても、序盤から「情報のぶつかり合い」が鮮明になっています。特に注目すべきは、ある候補者に対して集中的に批判や疑惑が投げかけられているという点です。実際、政治評論家やジャーナリストの間でも「今回の総裁選は政策論争以上に情報操作がカギを握る」と指摘されています。
なぜ情報戦が激化するのか?
総裁選の結果は、日本の政治の方向性を大きく左右します。経済政策、外交・安全保障、社会保障といったテーマだけでなく、党内の派閥バランスや選挙後の人事にまで影響が及ぶため、各陣営が勝敗にこだわるのは当然です。その結果、候補者本人の政策や実績以上に、「イメージ」や「スキャンダル」が票の行方を左右するケースが多く見られます。
情報戦が激化するもう一つの理由は、SNSやネットメディアの存在です。従来であれば新聞やテレビが世論形成の主役でしたが、現在はTwitter(X)、YouTube、ブログといった新しい媒体が一気に情報を拡散させます。そのスピードは従来の比ではなく、たとえ小さな発言やミスであっても一瞬で「炎上」し、候補者の致命傷になりかねません。
今回の総裁選の特徴
今回の自民党総裁選では、序盤から「誰が次期総理にふさわしいか」という政策論争が注目される一方で、水面下では激しい駆け引きが進んでいます。特定の候補者に関するスキャンダル情報やネガティブな噂が飛び交い、週刊誌やネットニュースがそれを取り上げることで、党員や国民の印象形成に強い影響を与えています。
重要なのは、これらの情報が「事実」かどうかよりも、「どう報じられ、どう受け取られるか」という点です。事実でなくても、十分に拡散されれば候補者のイメージダウンにつながり、その結果として支持率や票の行方が変わる可能性があります。まさに現代の政治は、政策論争と同じくらい「情報の戦い」が重要になっているのです。
情報戦の典型的な手法
- スキャンダルの暴露: 過去の発言や人間関係を掘り起こし、マイナスイメージを与える。
- 発言の切り取り: 本来の文脈を無視し、失言や問題発言として拡散する。
- 根拠の薄い噂の流布: 「辞任するらしい」「内部対立がある」といった噂を広め、混乱を誘う。
- SNSでの炎上誘導: ハッシュタグや拡散を使い、特定候補を攻撃するムードを作り出す。
こうした手法は、候補者の支持を削ぐだけでなく、支持者の士気を低下させる効果も狙っています。つまり情報戦は単なる報道合戦ではなく、心理戦の側面も持ち合わせているのです。
まとめ
総裁選の幕が開いたばかりの現段階から、既に激しい情報戦が繰り広げられています。候補者の政策や実績はもちろん重要ですが、それ以上に「どのように見られるか」「どのように報じられるか」が勝敗を左右する現実があります。次章では、この情報戦の中で特に集中攻撃を受けている高市早苗陣営について、詳しく掘り下げていきます。
高市早苗陣営が攻撃対象に

総裁選が始まると同時に、各候補者の立ち位置が鮮明になり、支持層の広がりや派閥の動きが注目されます。その中で特に目立つのが、高市早苗候補に対する集中的な攻撃です。高市氏は過去の総裁選でも存在感を発揮し、今回も有力候補の一人として名前が挙がっています。彼女の政策や姿勢は、保守層からの強い支持を得ており、また女性初の総理候補という点でも大きな注目を集めています。
一方で、高市候補の台頭を脅威と感じる勢力も少なくありません。派閥力学においても、既存の有力候補と票の取り合いになる可能性が高いため、序盤から徹底的に高市陣営を揺さぶろうとする動きが見られます。これは単なる選挙戦の一部というより、明確に「高市潰し」を狙った戦略的行動だと考えられます。
なぜ高市早苗が狙われるのか
第一に、高市候補は国民的な知名度が高く、政策も明確でブレがないことが特徴です。特に安全保障や外交政策では毅然とした立場をとっており、一部からは「日本の安全を守る強いリーダー」と評価されています。この存在感が、他の候補者にとっては脅威となるのです。
第二に、高市氏は女性候補としての象徴性を持っています。自民党は長年「男性中心」のイメージが強かった政党ですが、そのイメージを変えうる人物が高市氏です。そのため「次期総理候補の本命を脅かす存在」として、排除の対象にされやすいという側面もあります。
序盤から見られた攻撃
総裁選序盤、高市陣営の記者会見で発生した「発言騒動」をきっかけに、メディアや一部の記者からの批判が一気に高まりました。この出来事そのものは小さなものでしたが、それを過剰に取り上げて問題化する動きが見られたのです。ここには「高市陣営を揺さぶる意図」が透けて見えると言えるでしょう。
また、特定の全国紙記者が「陣営の幹部が辞任する」という根拠のない噂を流布し、週刊誌まで巻き込んで拡大する事態に発展しました。これは典型的なネガティブキャンペーンの手法であり、高市陣営の信頼性を傷つける狙いがあったと考えられます。
影響と今後の懸念
こうした攻撃は、一見すると小さな出来事を大げさに報じているだけのように見えます。しかし実際には、有権者や党員の心理に「不安」や「不信感」を植え付ける効果があります。特に総裁選のように短期決戦となる選挙では、わずかなイメージダウンが勝敗を分けることも珍しくありません。
つまり、高市陣営に対する攻撃は今後も続く可能性が高いのです。単なる一過性の批判ではなく、組織的かつ戦略的に仕掛けられている点を見逃してはなりません。次章では、その発端となった「記者会見での発言騒動」について詳しく見ていきます。
記者会見での発言騒動

高市早苗陣営に対する攻撃のきっかけとなったのが、2023年9月19日に行われた記者会見での出来事です。この会見では、高市候補の政策発表が行われ、その後に記者からの質疑応答が行われました。司会を務めたのは高市陣営の事務局長を務める北川衆議院議員でしたが、ここでの発言が思わぬ波紋を呼ぶことになったのです。
問題となった発言の経緯
質疑応答の際、北川氏は記者を指名する場面で「一番奥の顔が濃い方」「その手前の顔が白い方」と表現しました。本人としては会場の雰囲気を和ませる意図があったとも考えられますが、この発言が「不適切で差別的」と受け取られる可能性があるとして批判が広がりました。
特に現代社会では、人種や外見に関わる発言は敏感に捉えられます。この「顔の濃い・白い」という表現が、いわゆる「ルッキズム(外見差別)」にあたるのではないかという指摘が出たのです。
会場での反応
発言の直後、会場にいた高市候補自身も「顔が濃いって、そんなこと言うんですか」と軽くたしなめるようにコメントしました。場の雰囲気は一時的に和やかになったものの、発言の問題性が指摘される余地を残す結果となりました。
メディアの扱い方
その後、この発言は一部のメディアや記者によって大きく取り上げられました。本来なら「ちょっとした不適切発言」として処理されてもおかしくない内容ですが、これを機に「高市陣営に問題がある」「幹部が辞任するのではないか」といった噂が広まっていったのです。
ここには明らかに「小さな発言を大きな問題へとすり替える」意図が働いていました。特に全国紙の記者が積極的に噂を拡散したことが、後に週刊誌の取材へとつながり、騒動を拡大させる要因となったのです。
発言の真意と限界
北川氏本人としては、長年記者クラブでのやり取りを重ねる中で、顔馴染みの記者を軽くいじるような感覚で発言した可能性があります。しかし、プライベートな場なら許される言葉も、公的な記者会見の場では不適切とされかねません。本人も後日SNSで謝罪文を発表し、軽率だったことを認めています。
しかし問題は、その「軽率な発言」自体よりも、それを利用して陣営全体を揺さぶろうとする動きにありました。小さな一言が、政治的な武器として大きく拡大解釈されていく。この構図こそが、今回の総裁選における情報戦の典型的な一例なのです。
まとめ
記者会見での発言騒動は、一見すると単なる失言に過ぎません。しかし、それが特定の勢力によって大きく拡散され、政治的に利用されることで、高市陣営に対する攻撃材料として利用されました。次章では、この騒動を拡大させた「全国紙記者と週刊誌の動き」について詳しく解説します。
メディアと記者の動き

記者会見での「顔が濃い」「顔が白い」という発言が報じられると、すぐさま一部の記者が動きを見せました。特に注目すべきは、ある全国紙の記者がこの出来事を大きく取り上げ、各方面に「高市陣営の事務局長が辞任するらしい」といった噂を流布し始めた点です。この記者の発言が一種の“火種”となり、週刊誌メディアが取材に動くきっかけとなりました。
全国紙記者の役割
通常、全国紙の記者は事実確認を重視する立場にあります。しかし今回は、事実に基づく証拠よりも「憶測」が先行して広められたように見えます。記者クラブや政界関係者の間で「事務局長辞任説」が出回ったことで、長田町全体に不安と憶測が広がり、高市陣営に対する疑念が強調されました。
週刊誌の動き
この噂を聞きつけたのが、週刊文春や週刊新潮といった影響力の大きい週刊誌です。両誌は政治スキャンダルの追及に積極的で、世論に大きな影響を与える力を持っています。彼らが動き出すことで、単なる「噂」が「報道」へと変わり、事態は一気に深刻化しました。
実際に週刊誌の記者たちは「北川氏が辞任するのではないか」「発言は人権問題につながるのではないか」という観点で取材を開始したとされています。これにより、高市陣営の信頼性を疑問視する声が拡大し、選挙戦において大きなダメージを与える可能性が浮上しました。
情報の連鎖拡大
今回のケースは、情報がどのように拡大していくのかを示す典型例です。
- 記者会見での不用意な発言
- 全国紙記者による憶測の流布
- 週刊誌が取材に着手
- SNSやネットニュースで拡散
この流れによって、もともとは些細な発言が「陣営の存続に関わる大問題」であるかのように扱われるのです。現代の情報社会では、このような「小さな火が一気に大炎上に変わる」事態が珍しくありません。
攻撃の意図
重要なのは、これらの動きが単なる偶発的な報道ではなく、戦略的な意図を持って仕掛けられた可能性が高いという点です。特に総裁選のような党内選挙では、候補者のイメージを少しでも傷つけることが、派閥間の力学に大きな影響を及ぼします。全国紙記者や週刊誌の動きは、その情報戦の一環として理解するべきでしょう。
まとめ
全国紙記者が流した噂をきっかけに、週刊誌が動き出し、世論を巻き込む形で騒動は拡大しました。この一連の流れは、高市陣営に対する計画的な揺さぶりと見ることもできます。次章では、実際の事実関係について冷静に検証し、この騒動がどのように「作られた問題」であったのかを明らかにしていきます。
メディアと記者の動き

記者会見での「顔が濃い」「顔が白い」という発言が報じられると、すぐさま一部の記者が動きを見せました。特に注目すべきは、ある全国紙の記者がこの出来事を大きく取り上げ、各方面に「高市陣営の事務局長が辞任するらしい」といった噂を流布し始めた点です。この記者の発言が一種の“火種”となり、週刊誌メディアが取材に動くきっかけとなりました。
全国紙記者の役割
通常、全国紙の記者は事実確認を重視する立場にあります。しかし今回は、事実に基づく証拠よりも「憶測」が先行して広められたように見えます。記者クラブや政界関係者の間で「事務局長辞任説」が出回ったことで、長田町全体に不安と憶測が広がり、高市陣営に対する疑念が強調されました。
週刊誌の動き
この噂を聞きつけたのが、週刊文春や週刊新潮といった影響力の大きい週刊誌です。両誌は政治スキャンダルの追及に積極的で、世論に大きな影響を与える力を持っています。彼らが動き出すことで、単なる「噂」が「報道」へと変わり、事態は一気に深刻化しました。
実際に週刊誌の記者たちは「北川氏が辞任するのではないか」「発言は人権問題につながるのではないか」という観点で取材を開始したとされています。これにより、高市陣営の信頼性を疑問視する声が拡大し、選挙戦において大きなダメージを与える可能性が浮上しました。
情報の連鎖拡大
今回のケースは、情報がどのように拡大していくのかを示す典型例です。
- 記者会見での不用意な発言
- 全国紙記者による憶測の流布
- 週刊誌が取材に着手
- SNSやネットニュースで拡散
この流れによって、もともとは些細な発言が「陣営の存続に関わる大問題」であるかのように扱われるのです。現代の情報社会では、このような「小さな火が一気に大炎上に変わる」事態が珍しくありません。
攻撃の意図
重要なのは、これらの動きが単なる偶発的な報道ではなく、戦略的な意図を持って仕掛けられた可能性が高いという点です。特に総裁選のような党内選挙では、候補者のイメージを少しでも傷つけることが、派閥間の力学に大きな影響を及ぼします。全国紙記者や週刊誌の動きは、その情報戦の一環として理解するべきでしょう。
まとめ
全国紙記者が流した噂をきっかけに、週刊誌が動き出し、世論を巻き込む形で騒動は拡大しました。この一連の流れは、高市陣営に対する計画的な揺さぶりと見ることもできます。次章では、実際の事実関係について冷静に検証し、この騒動がどのように「作られた問題」であったのかを明らかにしていきます。
事実関係の検証

ここまで見てきたように、記者会見での発言がきっかけとなり、全国紙記者による噂の拡散、そして週刊誌の取材へと事態がエスカレートしました。しかし、実際の事実関係を冷静に検証すると、報じられた内容と現実との間には大きな乖離があることが明らかになっています。
北川事務局長の辞任は事実か?
もっとも大きな噂は「高市陣営の事務局長・北川議員が辞任するのではないか」というものです。しかし、取材や当人の発言からも、この情報は根拠がなく事実ではないことが確認されています。北川氏自身が辞任を否定しており、陣営内部でもそのような動きは一切ありませんでした。つまり、「辞任説」は完全な憶測であり、意図的に広められた虚偽情報と考えられます。
発言を受けた記者の反応
もう一つ注目すべきは、当の発言を受けた記者本人の反応です。高市陣営の会見で「顔が白い」と指名された日本経済新聞の記者は、周囲の知人に対し「特に気にしていない」と語っていたことが確認されています。つまり、当事者自身が問題視していないにもかかわらず、外部が騒ぎ立てて大きな問題へと仕立て上げていたのです。
また、もう一人「顔が濃い」と表現された記者についても、抗議や不満を表明する動きは見られず、少なくとも本人たちが深刻な被害を感じていた様子はありません。ここからも、この騒動が外部によって拡大された「作られた問題」であることが浮き彫りになります。
北川氏の謝罪と対応
騒動を受け、北川氏は自身のSNS(X)において謝罪文を発表しました。その内容は以下のようなものでした。
この度の自民党総裁選挙における高市候補の記者会見で司会を務めた私の不適切な表現により、ご不快な思いをされた皆様に心よりお詫び申し上げます。関係の記者の方々には直接ご容赦いただきましたが、SNSでのご報告が本日となりましたことも重ねてお詫びいたします。今後は言動に細心の注意を払い、活動を続けてまいります。
この謝罪文に対しては「誠実な対応だ」と理解を示す声がある一方、「軽率だった」と批判する声もありました。しかし、少なくとも記者本人たちは謝罪を受け入れており、問題はすでに収束していたと言えます。
騒動の実態
整理すると、事実関係は次の通りです。
- 北川事務局長が辞任するという事実はない
- 発言を受けた記者本人たちは問題視していない
- 北川氏は謝罪文を公表し、当事者も了承している
つまり、この騒動は「当事者不在のまま、外部が勝手に騒ぎ立てた」ケースだったのです。政治的な思惑を持つ記者やメディアが、選挙戦の材料として事実を歪めて拡散した典型的な事例といえるでしょう。
まとめ
事実確認をすればするほど、今回の騒動は大きな問題ではなかったことが分かります。辞任説は虚偽であり、当事者も問題視していない。それにもかかわらず、報道や噂によって「重大問題」に仕立て上げられたのです。次章では、こうした「小さな問題を大きく見せる」ネガティブキャンペーンの実態について掘り下げていきます。
ネガティブキャンペーンの実態

総裁選の舞台裏で繰り広げられる「情報戦」は、候補者同士の政策論争以上に影響を及ぼすことがあります。その代表的な手法が「ネガティブキャンペーン」です。今回の高市早苗陣営への攻撃も、まさにその典型例だといえるでしょう。小さな問題を大きく取り上げ、あたかも深刻な失態であるかのように見せる。これがネガティブキャンペーンの本質です。
ネガティブキャンペーンとは何か
ネガティブキャンペーンとは、相手候補の弱点や失言を誇張・拡大し、支持を削ぐことを目的とした戦術です。アメリカ大統領選挙などでも頻繁に行われ、日本の政界でも党内選挙を中心に使われています。その効果は即効性があり、わずかな印象操作で有権者や党員の判断を揺さぶることが可能です。
具体的な手法には以下のようなものがあります。
- 失言の切り取り: 文脈を無視し、差別的・不適切に見えるように加工する。
- 根拠のない噂の拡散: 「辞任」「内部対立」などを吹聴して不安を煽る。
- 第三者による批判の演出: 記者や有識者の声を利用して問題を拡大する。
- SNSでの炎上誘導: ハッシュタグやまとめサイトを通じて印象を拡散する。
高市陣営に仕掛けられた手口
今回のケースでは、北川事務局長の「顔が濃い」「顔が白い」という発言が切り取られ、差別的な表現だと大きく取り上げられました。本来であれば、当事者が気にしていないことであり、謝罪も行われて決着していたはずの問題です。しかし、それを利用して「事務局長が辞任するのでは」といった虚偽情報が流され、週刊誌報道にまで発展しました。
この流れは、まさにネガティブキャンペーンの典型パターンです。小さな問題を膨らませ、事実よりも「印象」で相手を不利に追い込む。特に総裁選のような短期決戦では、この手法が効果的に作用するのです。
心理的効果とダメージ
ネガティブキャンペーンは単なる報道以上に、心理的な効果を持ちます。支持者に「大丈夫だろうか」という不安を与え、 undecidedな層には「問題のある陣営かもしれない」という疑念を植え付けます。結果として、投票行動に影響を与えるのです。
また、候補者本人や陣営スタッフの士気を下げる効果も無視できません。騒動対応に時間と労力を割かれ、政策の訴求力が弱まる。こうして本来の選挙戦から注意を逸らすことも、ネガティブキャンペーンの狙いの一つです。
なぜ高市氏が標的になるのか
高市氏が集中的に攻撃を受ける背景には、彼女の存在感の大きさがあります。女性初の総理候補としての注目度、保守層からの強い支持、そして本命候補に対抗しうる実力。これらの要素が揃っているからこそ、他陣営にとっては「潰すべき脅威」と見なされるのです。
まとめ
ネガティブキャンペーンは、選挙戦における常套手段の一つです。今回の高市陣営への攻撃も、その枠組みの中で理解することができます。事実ではなく印象を武器にし、小さな出来事を選挙戦全体を揺さぶる材料へと変えていく。次章では、高市候補がなぜ「本命候補にとって最大の脅威」とされるのか、その存在感について掘り下げていきます。
高市早苗候補の存在感と脅威
今回の総裁選において、高市早苗候補は明らかに「台風の目」となっています。過去の総裁選でも一定の支持を獲得してきた彼女は、今回さらに存在感を増し、主要候補の一角として注目されています。その存在は単なる話題性にとどまらず、本命候補たちにとって実際的な脅威となっているのです。
女性初の総理候補としての注目
まず、高市氏が持つ象徴的な意味があります。自民党は長年「男性政治家中心」の体制を続けてきましたが、高市氏はそのイメージを刷新しうる存在です。「日本初の女性総理大臣」の可能性を秘めることで、国民的な関心を集め、党内外からの支持を拡大する要素となっています。この象徴性は他の候補にはない強みであり、同時に脅威でもあります。
保守層からの強い支持
高市氏は政策面でも一貫して保守的な立場をとっており、安全保障や外交における強硬姿勢は保守層からの絶大な支持を受けています。特に中国や北朝鮮との関係において毅然とした発言を行ってきたことは、国民の安心感につながり、「日本を守るリーダー」としての評価を確立しています。この確固たる支持基盤が、党内のパワーバランスに大きな影響を与えるのです。
政策の明確さと信頼感
高市氏は経済政策や社会保障においても、明確なビジョンを打ち出しています。特に「生活の安全保障」を掲げ、国民生活の安定を重視する姿勢は幅広い層に響いています。政策がわかりやすく、ぶれない点は、他の候補との差別化ポイントとなっており、有権者や党員に「信頼できる候補」という印象を与えています。
なぜ本命候補にとって脅威なのか
高市候補の存在は、本命とされる候補者にとって大きな障害となります。その理由は以下の通りです。
- 支持層の重複: 保守層の票が分散し、本命候補の得票が減少する可能性がある。
- 国民的人気: 世論調査で一定の支持を持つことで、党内の議員票にも影響を与える。
- 選挙戦の焦点化: 高市氏への攻撃が増えるほど、逆に注目度が高まり、存在感が増す。
攻撃されるほど強くなる存在感
皮肉なことに、高市氏が攻撃されるほど、その存在感は強まっています。メディアで取り上げられる機会が増えること自体が知名度の向上につながり、また「不当な攻撃を受けている」という印象が支持者の結束を強める効果を生んでいます。つまり、ネガティブキャンペーンは短期的にはダメージを与えるものの、長期的には逆効果となるリスクも抱えているのです。
まとめ
高市早苗候補は、女性初の総理候補としての象徴性、保守層からの厚い支持、そして明確な政策を武器に、党内外で強い存在感を示しています。彼女が「本命候補にとって最大の脅威」とされる理由はここにあります。次章では、この総裁選の裏側でうごめく情報操作や今後の展開について掘り下げていきます。
永田町の裏側と今後の展開
ここまで見てきたように、今回の自民党総裁選は単なる政策論争ではなく、情報戦・ネガティブキャンペーンが色濃く反映された戦いとなっています。特に高市早苗候補に対する攻撃は、事実関係が薄いにもかかわらず、メディアや一部の記者の働きかけによって大きく拡散し、世論形成に影響を与えようとするものでした。こうした構図は、長田町における政治の裏側を浮き彫りにしています。
情報操作の実態
長田町では、派閥の思惑や政局の力学によって、意図的な情報操作が行われることが珍しくありません。今回の件でも、全国紙の記者が「辞任説」を流布し、週刊誌がそれを報じる形で騒動が拡大しました。そこには明確に「高市陣営を不利に追い込む」という目的が透けて見えます。つまり、情報は単なる事実の伝達ではなく、政治的な武器として活用されているのです。
永田町に充満する悪意
総裁選は党内の権力闘争の場であり、勝敗がその後の人事や派閥の力関係を大きく左右します。そのため、ライバル候補を少しでも弱体化させるために、根拠の薄い噂や誇張されたスキャンダルが利用されることは珍しくありません。今回のように、当事者が問題視していない出来事であっても、それを膨らませて攻撃材料にする動きは、長田町では日常茶飯事なのです。
今後の展開と警戒点
今回の騒動は最終的に大きな問題には発展しないと見られていますが、今後も同様の「情報攻撃」が繰り返される可能性は高いでしょう。特に高市候補のように本命候補に対抗しうる存在は、陣営の結束を乱すためのターゲットになりやすいと考えられます。小さな出来事であっても、SNSや週刊誌を通じて大きなスキャンダルに仕立て上げられる可能性は常にあるのです。
また、こうした情報戦の中で、有権者や党員が冷静に事実を見極められるかどうかも重要なポイントになります。表面的な報道に流されず、一次情報や候補者本人の発言を確認する姿勢が求められます。
まとめ
自民党総裁選の裏側には、表に見える政策論争だけでなく、水面下での情報操作やネガティブキャンペーンが渦巻いています。高市早苗候補に対する攻撃はその典型例であり、今後も同様の戦術が繰り返される可能性があります。総裁選の行方を占う上で重要なのは、こうした裏側の動きも含めて冷静に見極めることです。
有権者として、そして国民として、私たちは「事実」と「情報操作」を区別し、政治の本質を見抜く力を持つことが求められています。今回のケースは、その必要性を改めて示す一件となったのではないでしょうか。
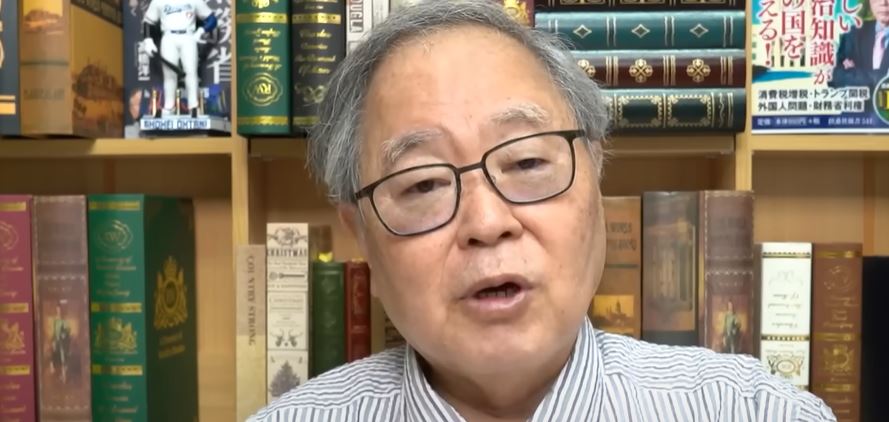


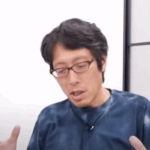



ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] […]