高市早苗 政策 核融合──成長戦略か、技術ポピュリズムか
高市早苗が掲げる“核融合国家”構想──夢か現実か、政策の正体を読み解く
「日本の未来は、核融合に懸かっている」──2025年、自民党総裁選の有力候補・高市早苗が放ったこの言葉は、ネットでも大きな反響を呼んだ。だが、果たしてその夢のようなエネルギー戦略は、本当に実現可能なのか。この記事では、高市早苗の核融合政策を軸に、日本のエネルギー戦略の現状、可能性、リスクを総合的に検証していく。
① 導入:なぜ今“核融合”が注目されているのか
地球温暖化、原油価格の乱高下、そしてロシア・ウクライナ戦争を機に表面化したエネルギー安全保障。こうした状況下で、世界中が新たな「脱炭素×自立型エネルギー」の切り札を探している。
そこに登場するのが「核融合」だ。従来の原子力発電(核分裂)とは異なり、核融合は水素などの軽い原子核を融合させ、膨大なエネルギーを生み出す仕組み。理論上、CO2を排出せず、爆発のリスクも低い“夢のエネルギー”とされている。
そんな中、強く核融合政策を推し進めようとしているのが高市早苗だ。だが本当に、それは日本のエネルギー問題を救う道なのか?あるいは、また一つの“政策ロマン”に過ぎないのか?
② 背景:日本と核融合のこれまで
日本は世界でも有数の核融合研究国である。1970年代から研究を重ね、核融合科学研究所(岐阜県土岐市)をはじめ、大学・国立研究機関で先進的な取り組みを継続してきた。
また国際共同研究「ITER計画」にも早期から参加。フランスに建設中の実験炉には、日本からも技術者と資金が投入されている。
さらに2024年には、日本政府が民間支援を目的とする「J-Fusion」発足。これにより、産学官一体となった核融合開発の加速が目指されている。
だが、商業化にはまだ課題が山積。多くの専門家が「本格稼働は早くても2050年以降」と慎重だ。そうした中で、高市早苗はこのスケジュールを大胆に“前倒し”しようとしている。
③ 高市早苗の核融合政策──大胆な国家主導型モデル
高市早苗の核融合構想は、次のような特徴を持っている:
- 「危機管理投資」枠として核融合を明記:安全保障や災害に強い国家を目指す中で、核融合を中核に据える。
- 2030年代に実証炉を稼働:政府のスケジュールより10〜15年早く、核融合実用化を目指す。
- 民間企業・大学への大胆な投資:税制優遇や補助金などで、核融合ベンチャーを国内に集積させる。
- 原子力・再エネとの“技術分担”論:太陽光偏重を見直し、原発と核融合で“基幹エネルギー”を構成する。
こうした政策は、ただのエネルギー政策ではなく、「成長戦略」「技術立国」「経済安全保障」の一部として語られている。
④ だが、それは現実的なのか──専門家の懸念
技術的・経済的な壁は非常に高い。まず、核融合発電の実証炉は未だ世界のどこにも存在しない。建設だけで1兆円規模、運用には特殊材料・冷却装置・燃料管理などが必要となる。
加えて、燃料となる「トリチウム」は放射性物質であり、漏洩や安全基準に関する議論も未整備だ。完全に“クリーン”とは言い切れない部分もある。
コスト面では、太陽光や風力が年々価格を下げている中、核融合は「極端に高く、不確実」な投資先という指摘もある。技術のブレークスルーがなければ、税金投入が“無駄金”になるリスクも。
⑤ 国民生活への影響──負担と期待
もし核融合開発に国家が本格的に舵を切れば、数兆円規模の国費投入が避けられない。高市構想はこれを“成長投資”と位置付けるが、当然ながら財源は税金か国債だ。
その影響として、次のようなことが起こりうる:
- 社会保障・教育予算が圧迫される
- 他のエネルギー分野(再エネ、蓄電)への投資が減少
- 都市部と研究拠点(地方)との格差が拡大
一方、核融合が成功すれば「安定電源×低価格×低炭素」という理想の電力が実現するかもしれない。だがそれは、10年、20年先の話だ。
⑥ 他の視点:世界と日本のギャップ
欧米では、核融合は民間主導でのブレークスルーに期待が寄せられている。米国ではヘリオン・エナジー、コモンウェルス・フュージョンなどが巨額の資金調達を行っている。
一方、日本では官主導、かつ保守的な研究開発体制が目立ち、スピード感や競争力に乏しいとの指摘もある。
また、欧州は並行して風力・蓄電・再エネ電力網の整備を進めており、「核融合一本足打法」のリスクを回避している。
⑦ もし実現すれば──仮想未来シナリオ
2035年、日本初の核融合実証炉が稼働──電力の5%を供給。安全性が確認され、商用炉建設が始まる。
2040年代、発電コストが下がり、電力自由化市場にも参入。電力料金は現在の2〜3割減少。
日本は技術輸出国となり、アジアやアフリカに核融合設備を提供。エネルギー外交で主導権を握る──。
これは確かに魅力的な未来だ。だが、このシナリオが実現する保証はどこにもない。

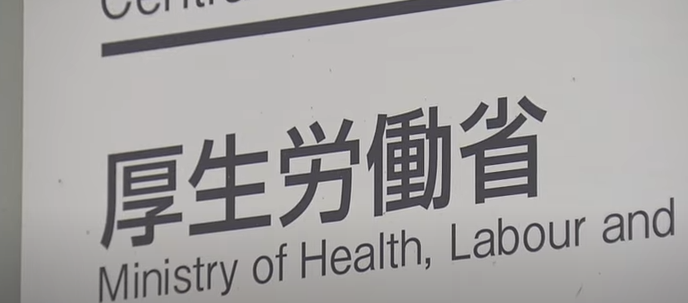
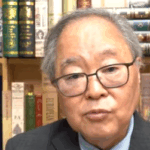




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません