小泉進次郞氏 企業の食事補助に対する非課税枠引き上げに前向き「 骨太 に明記し必ず実現」
小泉進次郎氏が食事補助の非課税枠引き上げに前向きな姿勢を示す
2025年現在、日本では物価高騰や生活費の上昇が続き、家計を直撃しています。特に食費の負担増は多くの家庭にとって大きな課題となっており、従業員の福利厚生として企業が提供する「食事補助制度」に注目が集まっています。
こうした中、自民党の小泉進次郎氏が、企業が従業員に提供する食事補助に対する非課税枠の引き上げに前向きな姿勢を示しました。同氏は政府の経済財政運営の基本方針である「骨太の方針」にこの政策を盛り込み、必ず実現する意志を表明しています。
現在、企業が従業員に提供する社員食堂の利用補助や食事券、デリバリー型の食事支援などには一定の非課税枠が設けられています。しかし、この非課税枠は長年据え置かれており、物価上昇に追いついていないのが現状です。そのため、従業員の実質的な負担軽減につながる制度の見直しが急務となっています。
今回の小泉氏の発言は、単なる一議員の提案にとどまらず、政府の方針に盛り込むことを明言した点に大きな意味があります。もし実現すれば、企業と従業員双方にとってメリットがあり、経済全体の活性化にもつながる可能性があります。
このニュースはビジネス界や労働市場、さらに家計を支える一般家庭にとっても大きな注目を集めています。本記事では、食事補助の非課税制度の仕組みや、非課税枠引き上げの意義、企業と従業員への影響、そして今後の展望について詳しく解説していきます。
「食事補助」「非課税枠」「骨太の方針」「小泉進次郎」といったキーワードは、今後の社会や経済政策を理解するうえで重要なトピックとなるでしょう。ここからは、その詳細を順を追って見ていきます。
食事補助の非課税制度とは?
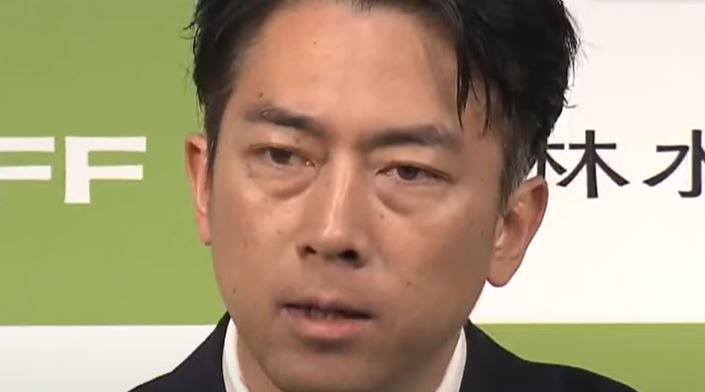
小泉進次郎氏が注目する「食事補助の非課税枠引き上げ」は、現在すでに存在する制度を拡充する形で検討されています。では、そもそも企業が従業員に提供する「食事補助」とはどのような制度であり、現行の非課税枠はどのように定められているのでしょうか。本章では、制度の基本を整理しながら解説していきます。
食事補助制度の基本
食事補助とは、企業が従業員の食費を軽減するために提供する福利厚生の一つです。代表的なものには、以下のような形式があります。
- 社員食堂の提供:企業内に設けられた社員食堂で安価に食事を提供する。
- 食事券・クーポン:提携店舗やコンビニなどで利用可能な食事券を配布。
- 宅配弁当の補助:オフィスに宅配される弁当代を会社が一部負担。
- 外部サービスの利用補助:フードデリバリーや宅配食事サービスを福利厚生として利用。
これらの制度は、従業員の生活支援だけでなく、職場での栄養バランス改善や健康経営の推進にもつながるため、多くの企業で導入されています。
非課税枠の仕組み
企業が従業員に食事補助を提供する場合、一定の条件を満たせば所得税や社会保険料の対象外、つまり非課税として扱われます。これが「食事補助の非課税枠」です。
具体的には、国税庁が定める基準により、従業員が支払う金額と企業が負担する金額のバランスによって非課税の可否が判断されます。例えば、社員食堂の場合、従業員が食費の半額以上を負担していれば、企業の補助分は課税対象外になります。また、食事券などの場合は、1食あたり一定額以下であれば非課税として認められる仕組みです。
現行制度の課題
現行の非課税枠は長年変更されておらず、インフレや食材費の高騰には対応できていません。そのため、企業が補助を増やしたくても、非課税枠を超えれば給与とみなされ、従業員に所得税や社会保険料の負担が発生してしまいます。
例えば、社員食堂の補助が月額数千円に及ぶ場合、非課税枠を超える部分は課税対象となり、結果的に従業員の手取りが減少するケースもあります。こうした状況は「福利厚生の充実を目指す企業」と「負担を軽減したい従業員」の双方にとって望ましくないものです。
制度利用の広がり
食事補助の非課税制度は、大企業だけでなく中小企業やスタートアップでも導入が進んでいます。特にリモートワークの普及に伴い、従業員が自宅で食事をとるケースが増え、宅配型やオンライン対応の食事補助サービスが拡大しています。
また、健康経営に積極的な企業では、単なる補助にとどまらず、栄養バランスの取れたメニューを提供するなど、従業員の健康促進を重視する動きも強まっています。
まとめ:制度理解が重要
「食事補助の非課税制度」は、企業が従業員に提供する福利厚生の中でも生活に直結する支援策です。しかし、現行の非課税枠は時代の変化に十分対応できていないため、今回の引き上げ議論が生まれています。企業側にとっても従業員側にとってもメリットが大きい制度であり、改正されればより多くの企業が活用しやすくなることは間違いありません。
次章では、なぜいま「非課税枠の引き上げ」が求められているのか、その背景と理由について詳しく見ていきます。
なぜ非課税枠の引き上げが議論されるのか?
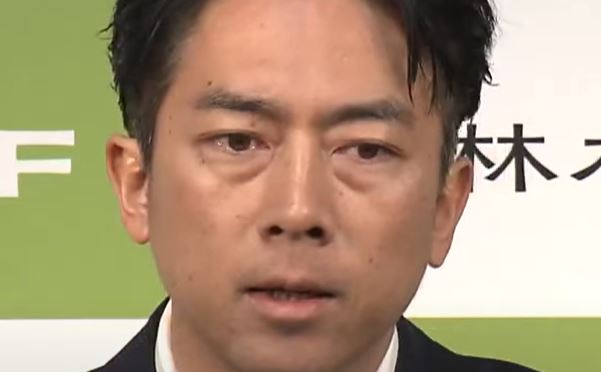
企業の食事補助における非課税枠の引き上げが、今なぜこれほど注目を集めているのでしょうか。その背景には、物価上昇による生活費負担の増大、福利厚生の重要性の高まり、そして働き方改革の推進といった社会的要因が密接に関わっています。本章では、その理由を3つの視点から詳しく解説します。
① 物価高騰と生活費負担の増加
2020年代に入り、世界的な原材料費やエネルギー価格の高騰、円安の影響などによって、日本国内でも食品価格が大幅に上昇しています。総務省の家計調査によれば、2024年の食品価格は前年比で平均5%以上上昇しており、家庭の家計を直撃しました。
特に外食費や弁当、総菜などは値上げが顕著で、毎日の昼食代が月額数千円単位で増えているケースも少なくありません。従業員にとって昼食費の負担は軽視できない支出であり、食事補助制度が重要な生活支援策となっているのです。
しかし現行の非課税枠は長年据え置かれているため、物価上昇に対応できず、実質的に「制度の目減り」が起きています。このため、非課税枠の引き上げは従業員の生活を直接支える施策として求められているのです。
② 福利厚生の充実と人材確保
企業にとって、優秀な人材の確保と定着は経営課題のひとつです。そのため、給与以外の福利厚生が果たす役割は年々大きくなっています。特に若い世代の就職希望者は「給与の多寡」だけでなく「働きやすさ」や「会社のサポート体制」を重視する傾向が強まっています。
食事補助は、従業員の健康維持や生活の安定につながる実感しやすい福利厚生のひとつです。しかし非課税枠が低いままでは、企業が十分な補助を行いにくく、福利厚生としての魅力が損なわれかねません。
非課税枠が拡大されれば、企業はより積極的に食事補助を導入・拡充でき、人材確保や離職率低下といった効果も期待されます。そのため、経済界からも制度見直しを求める声が高まっているのです。
③ 働き方改革と健康経営の推進
政府が推進する「働き方改革」では、労働時間の短縮や多様な働き方の実現とともに、従業員の健康維持も重視されています。食生活は健康に直結する要素であり、企業による食事補助は従業員の生活習慣病予防やパフォーマンス向上にも効果的です。
また、リモートワークの普及により、自宅で働く従業員への食事補助サービスが広がっています。宅配弁当やオンライン対応の食事券といった新しい福利厚生が増えている一方、現行の非課税制度はこうした新しいサービス形態を十分にカバーできていません。
非課税枠の引き上げは、こうした多様な働き方を支援し、企業の健康経営を後押しする施策としても重要なのです。
④ 社会的インパクトの大きさ
食事補助の非課税枠引き上げは、単に従業員の昼食代が軽減されるというだけの話ではありません。企業の福利厚生強化、労働市場の活性化、さらには国民の健康促進という幅広い効果を持ち得ます。
一方で、非課税枠の拡大には財政的な影響も伴うため、政府内では慎重な議論が必要です。しかし、家計支援と経済活性化の両面から、社会全体が恩恵を受ける可能性が高いことも事実です。
まとめ:時代に即した制度改革の必要性
非課税枠引き上げの議論は、単なる税制改正にとどまりません。物価高騰、働き方の多様化、企業経営の課題といった社会全体の変化に対応する「時代に即した制度改革」と言えるでしょう。
次章では、小泉進次郎氏がどのような立場からこの政策を推進し、「骨太の方針」への明記を主張しているのか、その意義について詳しく見ていきます。
小泉進次郎氏の提案の意義
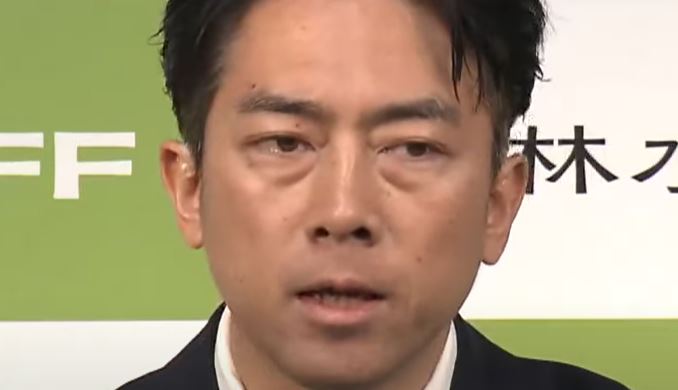
小泉進次郎氏が「食事補助の非課税枠引き上げ」を提案し、さらに政府の経済財政運営の基本指針である「骨太の方針」に明記する考えを示したことは、大きな注目を集めました。本章では、この発言が持つ政治的・社会的意義について解説していきます。
① 「骨太の方針」に盛り込む意味
「骨太の方針」とは、政府が毎年策定する経済財政運営と改革の基本方針のことです。予算編成や政策の方向性を定める重要な文書であり、ここに盛り込まれた施策は実現可能性が極めて高まります。
小泉氏は「骨太に明記し必ず実現する」と明言しており、単なる提案ではなく、政府方針として政策を推進する姿勢を示しました。これにより、食事補助の非課税枠引き上げは、与党内外での議論が加速することが予想されます。
② 生活支援政策としての強調
物価上昇によって国民生活が圧迫される中、政府には生活支援策の拡充が求められています。小泉氏の提案は、直接的に国民の生活に寄与する「実感できる支援」としての性格を持っています。
従来の経済政策は抽象的なものや長期的効果にとどまるものが多く、国民が実感しにくいケースも少なくありません。その点、食事補助の非課税枠拡大は、毎日の昼食代や家計の支出に直結するため、国民にとって分かりやすく受け入れられやすい政策といえます。
③ 政治的立場と発信力
小泉進次郎氏は、若手政治家の中でも知名度と発信力が高く、国民への影響力を持つ人物です。彼の発言はメディアに取り上げられやすく、世論を動かす効果も期待されます。今回の提案も、多くの報道機関が速報として扱い、社会的議論を喚起しました。
また、小泉氏は環境政策や働き方改革など、これまでにも「生活に身近なテーマ」に積極的に取り組んできた経歴があります。そのため、今回の発言も単なる思いつきではなく、これまでの政策スタンスと一貫性を持っていると評価されています。
④ 経済界・労働界へのメッセージ
企業にとっても従業員にとってもメリットの大きい制度改革を政府が主導することで、経済界と労働界双方へのメッセージ性が高まります。企業にとっては「従業員を支援しやすくなる環境づくり」、労働者にとっては「生活支援の強化」として歓迎される内容です。
小泉氏の発言は、経済団体や労働組合に対して「政府が本気で環境整備に取り組む」という意思を示すシグナルでもあります。これにより、民間からの協力や賛同も得やすくなると考えられます。
⑤ 次世代への布石
さらに、小泉氏の発言は短期的な生活支援にとどまらず、次世代に向けた制度設計の布石という側面もあります。現行制度が長期間にわたり据え置かれてきたことを踏まえれば、非課税枠の見直しは「将来の標準」をつくる改革ともいえます。
今後の人口減少社会においては、限られた労働力を大切にし、働きやすい環境を整えることが不可欠です。食事補助の非課税枠拡大は、その一環として「働く人を大切にする社会」への転換を象徴する政策になり得ます。
まとめ:発言の重みと期待感
小泉進次郎氏の提案は、単なる税制の調整にとどまらず、生活支援・経済活性化・社会改革といった広範な意義を持っています。「骨太の方針」に盛り込むという発言は、実現に向けた強いコミットメントを意味し、国民や企業に対して大きな期待を抱かせています。
次章では、この制度改正が実現した場合、企業側にどのようなメリットがあるのかを具体的に見ていきましょう。
企業側のメリット
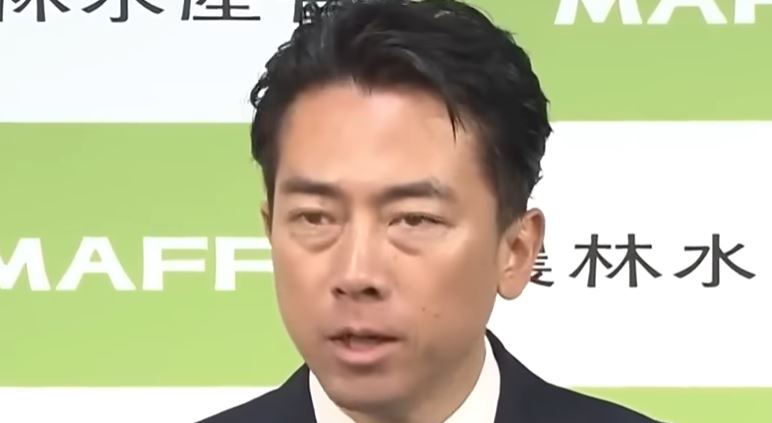
食事補助の非課税枠引き上げが実現すれば、最も恩恵を受けるのは従業員だけではありません。実は企業にとっても大きなメリットがあります。福利厚生の充実による人材確保や離職率低下、税制優遇によるコスト削減など、経営面での効果は計り知れません。本章では、企業が得られる具体的なメリットについて詳しく見ていきます。
① 福利厚生の強化による企業イメージ向上
企業にとって「働きやすい環境」を整えることは、採用活動や従業員の定着に直結します。特に近年は、求職者が企業を選ぶ際に「給与」だけでなく「福利厚生の充実度」を重視する傾向が強まっています。
食事補助は、従業員が日常的に恩恵を実感できる制度であるため、福利厚生の中でも満足度が高いとされています。非課税枠が拡大されれば、企業は従業員に負担をかけずに補助額を増やすことが可能になり、結果として「従業員思いの企業」というイメージを強化することができます。
② 採用力の向上と人材確保
少子高齢化が進む日本では、優秀な人材の確保は今後ますます難しくなります。そこで、福利厚生の充実は採用活動における重要な差別化要因となります。
たとえば、同じ給与水準の企業であっても、食事補助や住宅補助といった生活支援制度が整っている企業の方が、応募者に選ばれやすい傾向があります。非課税枠が広がれば、企業は食事補助を強力な採用ツールとして活用でき、競争の激しい労働市場で優位に立つことが可能となるのです。
③ 従業員の定着率向上とモチベーションアップ
食事補助は、従業員が日々の生活で「会社から支えられている」と感じやすい制度です。そのため、非課税枠の拡大によって補助額を増やせば、従業員満足度が高まり、離職率の低下につながります。
また、昼食代の補助が充実することで、従業員は栄養バランスの取れた食事を選びやすくなり、健康状態や仕事のパフォーマンスも向上します。これにより、結果的に生産性が高まり、企業全体の業績改善に寄与する効果も期待できます。
④ 税制優遇によるコスト削減
現行制度でも、一定の条件を満たせば企業が負担する食事補助費用は非課税として扱われます。非課税枠が引き上げられることで、より多くの補助費用を「経費」として処理できるため、法人税の負担軽減にもつながります。
これは特に大企業だけでなく、中小企業にとってもメリットが大きい点です。限られた予算の中で従業員に実質的な支援を行いつつ、同時に経営コストを抑えられるため、経営基盤の強化につながります。
⑤ 健康経営の推進と生産性向上
食事補助は、単なる福利厚生にとどまらず「健康経営」の観点からも重要な役割を果たします。従業員が栄養バランスの取れた食事を取りやすくなることで、生活習慣病の予防や健康維持に寄与します。
健康な従業員が増えることで、病欠や医療費の削減につながり、結果的に企業の労働生産性が向上します。非課税枠引き上げは、こうした健康経営を後押しする施策としても意義が大きいのです。
⑥ 社会的責任(CSR)の強化
企業が従業員の生活を支援する姿勢は、社会的責任(CSR)の一環としても評価されます。特に昨今は「従業員を大切にする企業」が投資家や消費者から高く評価される傾向が強まっています。
非課税枠の拡大を活用し、従業員への支援を強化することは、企業ブランドの向上にもつながり、長期的な経営戦略として有効です。
まとめ:企業にとっても大きな追い風
非課税枠の引き上げは、企業にとって「コスト削減」と「従業員満足度向上」という二重のメリットをもたらす施策です。採用力の強化、離職率低下、生産性向上、ブランド価値の向上など、多方面でプラスの効果が期待できます。
次章では、この制度改正が従業員にどのようなメリットをもたらすのか、働く人の立場から詳しく見ていきましょう。
従業員側のメリット
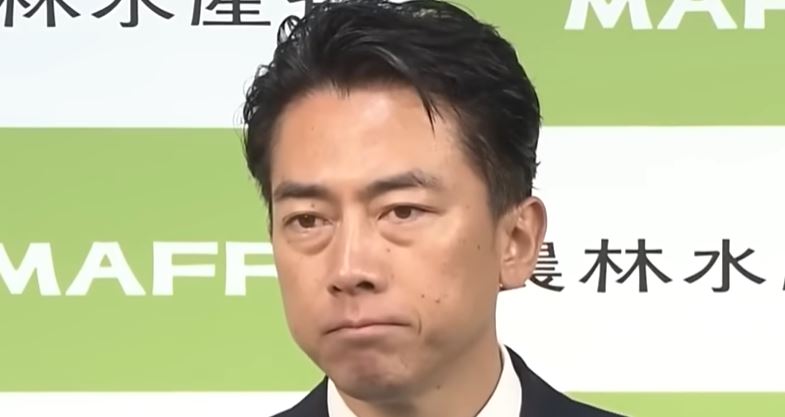
企業による食事補助の非課税枠引き上げは、従業員にとっても大きなメリットがあります。毎日の生活に直結する制度であり、実質的な手取り増、健康的な食生活の実現、さらには精神的な安心感の向上など、多方面に好影響をもたらします。本章では、従業員が享受できる具体的な利点を整理して解説します。
① 実質的な手取り収入の増加
最も分かりやすいメリットは、非課税枠の引き上げによる実質的な手取り増です。通常、給与として受け取る現金は所得税や社会保険料の対象となりますが、非課税扱いの食事補助はその負担がかかりません。
たとえば、企業が1食あたり500円の補助を出した場合、現行の非課税枠を超える部分は課税対象となり、従業員の手取りが減ってしまいます。しかし非課税枠が拡大されれば、より多くの補助を課税なしで受けられるため、家計への実質的なプラスとなります。
これは給与アップに比べて企業の負担が小さく、従業員の負担軽減効果が大きいという点で、非常に効率的な支援方法といえます。
② 食生活の質向上と健康促進
非課税枠の拡大により企業が提供できる補助額が増えれば、従業員は価格を気にせず栄養バランスの取れた食事を選びやすくなります。安価な食事に偏ることなく、健康的な昼食を取れる機会が増えるのは大きなメリットです。
栄養不足や偏った食生活は、生活習慣病のリスクを高め、長期的には医療費や労働生産性に悪影響を及ぼします。企業が食事補助を充実させることは、従業員個人の健康維持に直結し、結果的に社会全体の健康コスト削減にもつながります。
③ 家計支援としての安心感
物価高騰が続く中、食費は家計の中でも大きな割合を占めています。特に子育て世代や単身世帯では、昼食代の負担は無視できません。食事補助が手厚くなることは、毎月の支出を確実に減らす効果があり、家計に安定感をもたらします。
さらに、補助が非課税で提供されることで「少しでも節約したい」という心理的負担も軽減されます。従業員にとっては経済的にも精神的にも大きな安心材料となるでしょう。
④ 働き方の多様化に対応
リモートワークやフレックスタイム制の普及により、従業員の働き方は多様化しています。こうした状況において、宅配型の食事サービスやオンラインで利用できる食事券といった制度は非常に有効です。
非課税枠が広がれば、従業員は勤務形態に関わらず公平に食事補助を受けられるようになります。特に在宅勤務者にとっては「オフィスに行かないと補助が使えない」という不公平感が解消され、働きやすさが向上します。
⑤ 職場満足度とエンゲージメント向上
従業員は日常の小さなサポートから「会社に大切にされている」という実感を得ます。食事補助の非課税枠拡大は、まさにその実感を強める施策です。
会社からの支援を身近に感じることで、従業員のモチベーションが高まり、職場へのロイヤリティやエンゲージメントも向上します。結果として、従業員が長期的に働き続けたいと思える環境づくりにつながるのです。
⑥ ライフスタイルに合わせた選択肢の拡大
非課税枠の引き上げにより、企業が提供できる補助の幅が広がれば、従業員は自分のライフスタイルに合った形で支援を受けやすくなります。例えば、健康志向の人には栄養バランスの取れた弁当、忙しい人にはデリバリーサービス、家庭を持つ人には持ち帰り可能な食事券など、多様なニーズに対応できます。
この柔軟性は、従業員一人ひとりの満足度を高める大きな要因となります。
まとめ:生活の質を高める制度改革
従業員にとって、食事補助の非課税枠引き上げは単なる経済的支援にとどまりません。健康的な生活を実現し、家計を安定させ、働きやすさを向上させる「生活の質を高める制度改革」といえます。
次章では、この制度に伴う課題や懸念点についても考察し、実現に向けた課題整理を行います。
課題と懸念点
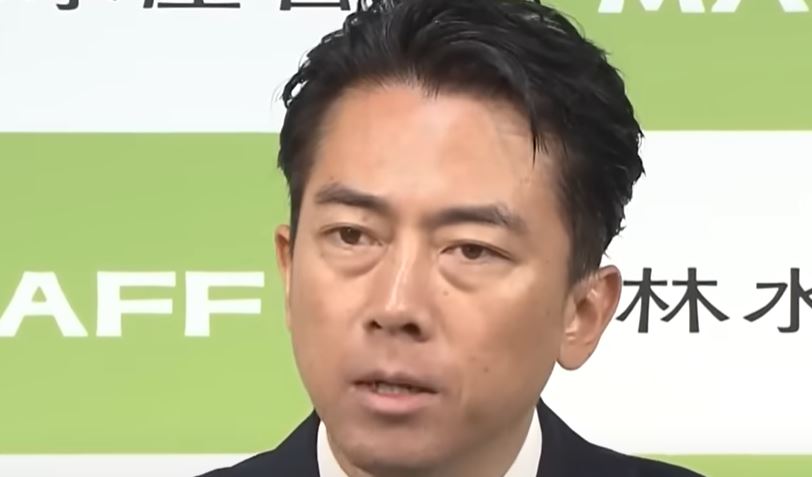
食事補助の非課税枠引き上げは、多くのメリットをもたらす一方で、課題や懸念点も存在します。政策として実現するには、財政的な影響や制度の公平性、運用面での問題をクリアする必要があります。本章では、主に3つの課題に焦点を当てて整理していきます。
① 財源確保の問題
最も大きな課題は、非課税枠引き上げによって税収が減少する点です。食事補助が非課税扱いになる範囲が拡大すれば、その分だけ所得税や社会保険料の徴収額が減少します。これは国の財政に直接的な影響を与えるため、慎重な議論が不可欠です。
政府はすでに社会保障費や教育費など多方面で財源不足に直面しており、新たな非課税措置の導入は「財政規律の緩み」を懸念する声も招きます。特に財務省は税収減を嫌う傾向が強いため、制度改正には政治的な調整が必要となります。
② 制度の公平性
もう一つの懸念は、制度の公平性です。大企業は社員食堂や大規模な福利厚生制度を整備しやすい一方で、中小企業やスタートアップは導入が難しい場合があります。そのため、非課税枠が拡大されても、恩恵を受けられるのは主に大企業の従業員に偏る可能性があります。
制度設計の段階で、中小企業も利用しやすい仕組みを整えることが求められます。たとえば、食事券やデリバリーサービスなど外部事業者を活用できる形での非課税枠拡大であれば、中小企業の従業員も恩恵を受けやすくなるでしょう。
③ 運用面での複雑さ
現行の非課税制度でも、適用条件は細かく定められています。たとえば、社員食堂の場合は「従業員が食費の半額以上を負担していること」などの条件があります。制度が複雑すぎると、企業が正しく運用するのが難しく、結果的に利用が広がらない可能性があります。
非課税枠の引き上げを実効性のある制度とするためには、企業が分かりやすく使いやすいルール設計が不可欠です。特に中小企業では専門部署を持たないことも多いため、シンプルで実行可能な仕組みが求められます。
④ 不正利用や形骸化のリスク
非課税制度が拡大されると、一部の企業で制度を不正に利用するケースも懸念されます。例えば、実際には食事補助として提供されていないにもかかわらず、制度を装って課税逃れを行うケースです。
また、制度が形骸化し「単なるコスト削減手段」として扱われてしまうと、本来の目的である「従業員支援」が薄れてしまいます。これを防ぐためには、適切なガイドラインや監査体制の整備が欠かせません。
⑤ 格差の拡大懸念
企業規模や業種によって、食事補助の導入や活用のしやすさには差があります。その結果、制度改正が格差を広げる要因となる可能性もあります。特に飲食業や医療・介護業など、現場に縛られる業種では導入の自由度が低く、恩恵を受けにくいケースがあるでしょう。
制度を公平に機能させるためには、業種や規模に応じた柔軟な対応策も必要になります。
まとめ:実現に向けた課題整理
食事補助の非課税枠引き上げは、従業員と企業の双方にメリットが大きい制度ですが、実現には財源問題や制度の公平性、運用の簡便化といった課題を解決する必要があります。これらを克服できるかどうかが、政策の成功を左右します。
次章では、こうした課題を踏まえつつ、今後の展望と制度が社会に与える影響について解説していきます。
今後の展望とまとめ
小泉進次郎氏が提案する「食事補助の非課税枠引き上げ」は、従業員と企業双方に大きなメリットをもたらす制度改革として注目されています。本章では、今後の政治スケジュールや実現可能性、社会全体への影響を整理しながら、総まとめを行います。
① 政治スケジュールと実現可能性
小泉氏は「骨太の方針」に明記すると発言しており、これは実現可能性を大きく高める要素です。骨太の方針は政府の予算編成や政策運営の指針となるため、ここに盛り込まれれば実際の法改正や税制改正に直結する可能性があります。
今後の流れとしては、以下のプロセスが想定されます。
- 与党内での税制調査会や政策会議で議論
- 政府の骨太の方針に正式に明記
- 翌年度の税制改正大綱に盛り込み
- 国会審議を経て実施へ
これらのプロセスを踏めば、早ければ数年以内に実現する可能性が十分にあります。
② 企業と従業員への期待効果
非課税枠の拡大が実現すれば、企業にとっては福利厚生の強化、採用力向上、税制優遇による経費削減といったメリットがあります。一方、従業員にとっては実質的な手取り増、健康的な食生活の実現、家計支援としての安心感などの恩恵があります。
このように双方にとって「ウィンウィン」の関係を生み出す制度であるため、導入後は労働環境の改善や生産性の向上にも寄与することが期待されます。
③ 社会全体への波及効果
食事補助の非課税枠引き上げは、単なる企業内の福利厚生強化にとどまりません。国民の健康促進、労働市場の活性化、そして消費の拡大といった社会的波及効果を持つ可能性があります。
特に健康経営の推進や生活習慣病の予防といった観点からは、医療費削減につながる可能性もあり、長期的には国の財政健全化にも寄与する施策となり得ます。
④ 課題解決に向けた提言
ただし、実現にあたっては前章で述べたように「財源確保」「制度の公平性」「運用の簡素化」といった課題を克服する必要があります。具体的には以下のような対策が考えられます。
- 財源確保:段階的な非課税枠拡大や他の税制見直しとの組み合わせ
- 公平性:中小企業やリモートワーク従業員も利用しやすい制度設計
- 運用面:ガイドラインの簡素化やデジタル化による手続きの効率化
こうした工夫により、制度がより多くの人々に恩恵をもたらす持続可能な仕組みとなるでしょう。
⑤ 今後の注目ポイント
国民としては、今後の政治スケジュールや議論の進展を注視する必要があります。特に「骨太の方針」や「税制改正大綱」にどのように盛り込まれるかが大きなポイントです。また、企業や経済団体からの要望がどの程度反映されるかも注目されます。
まとめ:生活と経済を支える制度改革
食事補助の非課税枠引き上げは、単なる税制改正ではなく、国民生活の安定と企業経営の強化、そして社会全体の活性化につながる可能性を秘めています。小泉進次郎氏の提案が現実の政策として結実するかどうかは、今後の議論次第ですが、実現すれば「働く人を支える社会」への大きな一歩となるでしょう。
今後も国民にとって実感できる支援策が増えることを期待しつつ、私たち一人ひとりも制度の動向を注視していく必要があります。
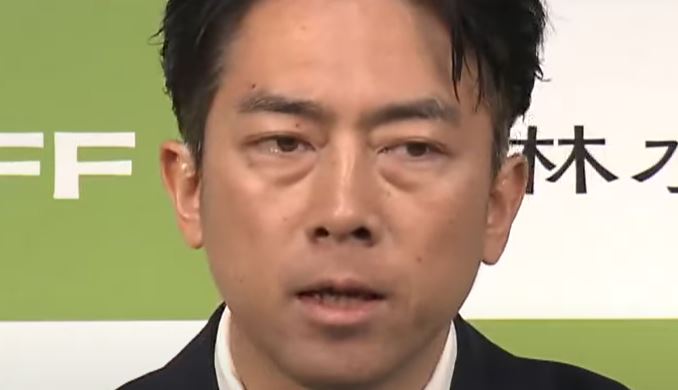






ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] […]