総裁選前倒し なぜ今?国民不在の政治が招く混乱
史上最悪と呼ばれる総裁選、その背景とは
2025年10月4日、日本の政治史において「史上最悪」とも揶揄される総裁選が実施されようとしています。総裁選といえば、政権与党のリーダーを決める重要な政治イベントであり、その結果は日本の未来を大きく左右します。通常であれば、候補者同士が政策を競い合い、国民にとっても「次の日本を担うリーダー」を見極める機会となるはずです。
しかし今回の総裁選は、早くも混乱と不信が渦巻いています。派閥争いの激化、候補者の不透明な公約、さらにはメディアの過剰報道やSNSでの情報操作など、国民の関心を集める要因は「期待」ではなく「不安」となっています。選挙が始まる前から「茶番」「出来レース」といった声が飛び交い、政治不信はかつてないほどに高まっています。
なぜ「最悪」と呼ばれるのか
今回の総裁選が「最悪」と評される最大の理由は、政治そのものが国民を置き去りにしている点です。経済不安、外交問題、少子高齢化といった国民生活に直結する課題が山積しているにもかかわらず、候補者たちの議論は抽象的で、派閥の都合に合わせたパフォーマンスに終始しているのです。国民にとって必要なのは「具体的な解決策」であるにも関わらず、その声はかき消されています。
国民の期待と現実の乖離
総裁選は本来、国民に希望を与えるイベントであるはずです。しかし、世論調査を見ると国民の大多数が今回の総裁選に失望していることが明らかになっています。中には「どの候補にも期待できない」という声すら少なくありません。これほどまでに国民の政治不信が高まった総裁選は、過去を振り返っても例がないでしょう。
本記事で解説する内容
本記事では、この「史上最悪の総裁選」を多角的に分析します。まずは総裁選の基本的な仕組みを整理し、その上で派閥争い、候補者の公約、メディアの影響、国民の不安点などを掘り下げます。さらに、今回の選挙が今後の日本政治にどのような影響を与えるのかを展望し、最後に読者の皆様と「日本のリーダー選び」について考えるきっかけを提示します。
次のパートでは、総裁選の基本情報や仕組みを確認しながら、なぜ今回の選挙がこれほどまでに注目を浴び、同時に批判を集めているのかを解説していきます。
2025年総裁選の基本情報とその仕組み

2025年10月4日に行われる総裁選は、単なる政党内部のリーダー選びにとどまりません。与党の総裁はそのまま日本の首相となる可能性が高いため、実質的に「次の日本のリーダー」を決定する極めて重要な選挙です。ここでは、総裁選の基本的な仕組みや過去との違いを整理し、今回の総裁選がなぜ「史上最悪」と言われるのかを理解する土台を作ります。
開催日とその意味
今回の総裁選は2025年10月4日に実施されます。この日程は一見すると単なるスケジュールの一部に過ぎませんが、実際には政局の流れや派閥間の駆け引きの結果として決まっています。衆議院解散の可能性や国際情勢への対応を考慮すると、この日程の背景には「政権延命」や「派閥の都合」が色濃く反映されていると分析されています。
投票権の仕組み
総裁選では大きく分けて「議員票」と「党員票」の2つが存在します。議員票は国会議員一人につき一票を持つもので、政党内部の力関係を色濃く反映します。一方で党員票は全国の党員や党友に与えられる票であり、国民の声をある程度反映する仕組みです。
しかし問題は、この2つの票が「同じ比率」で扱われていないことです。議員票の比重が極めて大きく、最終的には派閥の意向が強く反映される構造になっています。そのため「国民の声よりも派閥の論理が優先される」と批判され、今回の総裁選が不信感を集める要因となっています。
過去の総裁選との違い
過去の総裁選でも派閥の影響は大きな問題でした。しかし、近年はSNSの普及や有権者の政治意識の高まりにより、透明性や公平性を求める声が増しています。過去には「劇場型選挙」としてメディアを巻き込み、国民の関心を引きつけた総裁選も存在しましたが、今回の選挙は真逆の状況に陥っています。
具体的には、候補者の演説や政策討論が形式的に行われるだけで、中身が伴っていないことが問題視されています。国民の関心が高まるほど、実際の議論の薄さが際立ち、結果として「期待できない総裁選」という評価が広がっているのです。
制度上の課題
総裁選のルールそのものにも課題があります。議員票と党員票の不均衡はもちろんのこと、候補者の選出方法や立候補条件についても不透明さが指摘されています。例えば、立候補するためには一定数の推薦人が必要ですが、その推薦人を集める過程が派閥政治に依存しており、実力や政策よりも「数の力」が優先されてしまうのです。
今回の総裁選が注目される理由
今回の総裁選は「日本の進路を決める重要な節目」であると同時に、「政治不信をさらに加速させる可能性を秘めた危険な選挙」として注目されています。国民生活に直結する課題が山積しているにもかかわらず、その解決策をめぐる本格的な議論が見られないことが、失望感を生んでいるのです。
次のパートでは、この総裁選を「史上最悪」と呼ばせている大きな要因のひとつである派閥争いの激化について掘り下げていきます。候補者選びにおける派閥の力学を知ることで、今回の選挙の本質がより明確になるでしょう。
派閥争いが招く「史上最悪の総裁選」

2025年の総裁選を「史上最悪」と呼ぶ声の大きな理由のひとつが、派閥争いの激化です。日本の政党政治において派閥は長年続いてきた仕組みですが、今回ほどその存在が国民の不信感をあおるケースは過去に例がありません。政策よりも「派閥の論理」が前面に出てしまい、国民が求める課題解決から遠ざかっているのです。
派閥の勢力図と力関係
現在の与党内では複数の派閥がしのぎを削っています。派閥ごとに数十名規模の国会議員を抱え、その数が総裁選の勝敗を大きく左右します。大派閥は「キングメーカー」として圧倒的な影響力を持ち、中小派閥はどの候補を支持するかによってキャスティングボードを握る存在となります。
しかし、この「数の論理」が強すぎるがゆえに、候補者の政策や実力ではなく、どの派閥に属するか、またはどの派閥と手を組むかが最大の焦点となってしまいます。結果として、国民の目線からすると「政策論争が全く見えない茶番劇」と映っているのです。
派閥優先で失われる政策論争
総裁選は本来、次期リーダーが掲げる政策ビジョンを競い合う場です。しかし実際には、候補者同士の討論は派閥間の調整に配慮したものに終始し、国民にとって重要な課題は後回しにされています。例えば経済政策や外交戦略といったテーマであっても、具体的な数字や施策が提示されることは少なく、代わりに「派閥内での合意形成」が優先されているのです。
国民から見える「密室政治」
派閥争いのもうひとつの問題は、政治の透明性を著しく損なっている点です。誰がどの候補を支持するかは事前に派閥内で密室の話し合いによって決められることが多く、そのプロセスが国民には一切見えません。国民からすると「結局は水面下で決まっていた出来レースなのではないか」という疑念を抱かざるを得ない状況です。
こうした「密室政治」が続けば続くほど、国民は政治に対して無力感を覚え、投票や政治参加から遠ざかることになります。結果として、民主主義そのものが形骸化してしまう危険性があるのです。
派閥間の対立が深める分裂
派閥争いは単なる政党内部の競争にとどまりません。候補者同士の対立が深まるにつれて党内の分裂も進み、政権運営そのものが不安定化する可能性があります。特に今回の総裁選は、主要派閥の思惑が大きく食い違っており、選挙後も党内の亀裂が修復できないまま残るのではないかと懸念されています。
派閥政治が生み出す「国民不在」
派閥同士の取引や駆け引きは、国民の生活に直結する問題を置き去りにしています。経済不安、社会保障の行き詰まり、外交リスクといった課題は山積しているにもかかわらず、候補者たちは派閥に配慮して「本当に必要な議論」を避けています。そのため、国民からは「誰が総裁になっても同じ」という諦めの声が強まっているのです。
派閥争いが残す負の遺産
今回の総裁選は、派閥の力学が国民の意思を完全に上回っていることを浮き彫りにしました。これは単なる一時的な現象ではなく、今後の政治全体に深刻な影響を残す可能性があります。もし派閥優先の文化が続くのであれば、政策の実効性はますます低下し、国民の政治不信は取り返しのつかない段階にまで進んでしまうでしょう。
次のパートでは、候補者たちが掲げる公約の不透明さについて掘り下げます。派閥争いと同様に、候補者の公約が「実効性に欠ける」「曖昧すぎる」と批判される理由を詳しく見ていきます。
候補者たちの公約とその不透明さ

総裁選の見どころのひとつは、候補者たちがどのような政策を掲げるかという点です。本来であれば、候補者同士が政策を競い合い、国民にとって最も有益な選択肢を提示する場となるはずです。しかし、2025年の総裁選では公約そのものが「不透明」「実効性に乏しい」と批判され、国民の期待を大きく裏切っています。
主要候補者の公約に共通する問題点
今回立候補した主要候補者たちは、それぞれに経済・外交・社会保障に関する公約を打ち出しています。しかし、その内容を詳しく見ていくと、いずれも具体性に欠け、実現可能性が低いものばかりです。例えば「経済成長率を引き上げる」「安全保障を強化する」といったスローガンは掲げられているものの、どのような施策で実現するのかが示されていません。
また、多くの候補者が「国民生活を第一に」と強調しますが、その裏には派閥の意向や既得権益への配慮が見え隠れします。結果として、公約は「耳ざわりの良い言葉の羅列」にとどまり、国民にとっての信頼性を欠いているのです。
実効性のない経済公約
経済政策は総裁選で最も注目されるテーマのひとつです。しかし今回の候補者たちの公約は、財源の裏付けや具体的な数値目標が欠けており、現実味がありません。例えば「賃金を引き上げる」と訴えても、どの産業にどのような支援を行うのか、また中小企業への影響をどう緩和するのかといった説明が不足しています。
そのため、多くの有権者は「絵に描いた餅」と感じ、実際の生活改善にはつながらないと懐疑的に見ています。
曖昧な外交・安全保障政策
外交・安全保障の分野においても同様に、候補者の公約は曖昧です。特に米中関係や近隣諸国との関係は、日本の将来を大きく左右する重要なテーマですが、候補者たちは「国益を守る」「信頼関係を築く」といった抽象的な言葉を繰り返すばかりです。
実際にどのような外交戦略を描いているのか、具体的な行動計画を示す候補者はほとんどいません。そのため「結局は現状維持に終わるのではないか」という冷めた見方が広がっています。
社会保障政策の不透明さ
少子高齢化が深刻化する中で、社会保障政策は最重要課題のひとつです。しかし、候補者たちの公約はここでも明確さを欠いています。「年金制度の安定化」「医療サービスの充実」といった言葉は並びますが、具体的にどのような制度改革を行うのか、その財源をどう確保するのかは示されていません。
このような状況では、国民にとって公約は「選挙のための道具」に過ぎず、現実に即した政策議論にはなっていないと受け止められています。
世論調査との乖離
興味深いのは、候補者たちの公約と国民のニーズが大きく乖離している点です。世論調査では、国民が最も関心を持っているのは「物価高への対応」「社会保障の持続性」「外交の安定化」など具体的な課題です。しかし候補者の公約は、こうした国民の声を的確に反映していません。
その結果、国民の間では「どの候補者を選んでも変わらない」という失望感が強まっており、総裁選そのものへの信頼を失わせています。
「公約なき総裁選」が意味するもの
候補者の公約が不透明であるという事実は、今回の総裁選が国民のための政策論争の場ではなく、派閥間の力学を調整するための儀式に堕していることを象徴しています。国民にとって必要なのは「耳障りの良い言葉」ではなく、実行可能な政策です。しかし現実には、そのような候補者はほとんど存在しません。
次のパートでは、候補者の公約以上に総裁選の混乱を助長しているメディアと情報操作について詳しく見ていきます。メディア報道やSNSでの拡散がいかに世論を歪めているのか、その実態を掘り下げます。
メディアと情報操作がもたらす混乱

2025年の総裁選が「史上最悪」と呼ばれる背景には、メディアと情報操作の問題も大きく関わっています。本来、メディアは国民に公平で正確な情報を届け、判断材料を提供する役割を担っています。しかし今回の総裁選では、偏向報道や情報の過剰な演出が目立ち、国民の冷静な判断を妨げています。さらに、SNSを中心に誤情報やフェイクニュースが拡散され、混乱は一層深まっています。
偏向報道の実態
テレビや新聞といった従来型メディアは、依然として大きな影響力を持っています。しかし、総裁選における報道の多くは「特定候補を持ち上げる」「特定候補を批判する」といった偏りが見られます。報道機関と政権や派閥の距離が近いため、どうしても中立性を保つことが難しいのです。
結果として、国民に届く情報はバランスを欠き、一部の候補者に有利または不利に働く状況が生まれています。このような偏向報道は、選挙の公平性を損なうだけでなく、国民の政治不信をさらに深める要因となっています。
SNSでの情報拡散とデマ
SNSは国民一人ひとりが情報を発信できる便利なツールですが、その一方で誤情報や意図的なデマの温床にもなっています。候補者に関する根拠のない噂や、切り取られた発言が拡散され、それがあたかも事実であるかのように広がっていくのです。
特に今回の総裁選では、候補者同士を攻撃するようなネガティブキャンペーンがSNSで展開されており、冷静な政策論争がかき消されています。こうした状況は、国民の政治的判断を誤らせる大きなリスクを伴います。
情報操作の影響
メディアやSNSでの情報操作は、単なるイメージ戦略にとどまらず、選挙結果そのものを左右する可能性があります。情報が意図的に歪められることで、国民が本当に必要としている「政策の中身」が見えなくなり、表面的な印象だけで候補者が選ばれてしまうのです。
こうした状況は「民主主義の危機」とも言えます。国民が正しい情報に基づいて判断できない総裁選は、選挙制度の存在意義そのものを揺るがすものです。
メディアリテラシーの必要性
このような情報環境の中で重要になるのが、国民一人ひとりのメディアリテラシーです。偏向報道やフェイクニュースに流されるのではなく、複数の情報源を比較し、事実を見極める姿勢が求められます。特にSNSの情報はスピード感がある一方で誤情報も多いため、冷静に取捨選択する必要があります。
報道機関への信頼の低下
今回の総裁選を通じて浮き彫りになったのは、報道機関に対する国民の信頼が大きく揺らいでいるという現実です。「テレビや新聞を見ても真実は分からない」「SNSの方がまだリアル」という声が増えており、既存メディアの影響力は確実に低下しています。これは、情報の信頼性が揺らぐだけでなく、社会全体の分断を深める危険性を孕んでいます。
「史上最悪の総裁選」を象徴する情報混乱
情報操作や偏向報道がこれほどまでに注目される総裁選は、過去に例がありません。候補者の政策よりもメディア戦略やSNSでの発信力が注目される状況は、「史上最悪の総裁選」という評価を裏付ける要因のひとつです。
次のパートでは、こうした情報操作や偏向報道によってさらに高まっている国民の不安と怒りについて掘り下げます。経済や外交といった現実的な課題と合わせて、なぜ国民が政治そのものに失望しているのかを明らかにします。
国民が感じる不安と怒り

2025年の総裁選をめぐって、国民の間にはかつてないほどの不安と怒りが渦巻いています。候補者の公約が不透明で、派閥争いばかりが目立ち、メディア報道も公平さを欠いている――その積み重ねが「政治への失望感」を極限まで高めています。ここでは、国民が具体的にどのような不安を抱き、なぜ怒りを募らせているのかを整理します。
経済への不安
まず最も大きいのが経済への不安です。物価高や賃金停滞が続く中、候補者たちは「景気回復」「所得向上」といったスローガンを掲げています。しかし、実効性のある政策はほとんど示されていません。国民にとっては「結局、生活は良くならないのではないか」という疑念が強まっています。
特に中小企業や地方経済にとって、総裁選の結果は死活問題です。それにもかかわらず、候補者の多くは都市部や大企業を中心とした政策ばかりを強調しており、地方住民からは「私たちの声は届いていない」という不満が噴出しています。
外交と安全保障への不安
次に大きな不安は外交・安全保障です。米中関係の緊張、近隣諸国との摩擦、そして世界的なエネルギー・資源問題など、日本の立場は極めて不安定です。しかし候補者たちの外交公約は抽象的で、具体的な戦略はほとんど語られていません。
国民は「このリーダーに本当に日本を任せられるのか」という根源的な不安を抱き、結果として総裁選そのものへの信頼を失いつつあります。
社会保障と将来への不安
少子高齢化が進む中で、年金や医療制度の行方も国民の大きな関心事です。しかし、候補者たちは「持続可能な制度を目指す」といった曖昧な表現にとどまり、具体的な改革案を提示できていません。若年層からは「将来、年金を受け取れるのか不安」、高齢層からは「医療や介護サービスが削減されるのではないか」という声が相次いでいます。
このように、世代を問わず国民は「生活の基盤が揺らいでいる」と感じており、その責任を政治に求めています。
政治そのものへの不信感
経済や外交といった具体的な課題に加えて、国民が最も強く感じているのは政治そのものへの不信感です。派閥争いや出来レースといった構図を見せつけられるたびに、「結局は国民不在で物事が決まっている」という認識が広がっています。
この不信感は「怒り」として噴出するだけでなく、「無関心」としても現れています。投票や政治参加を諦める人が増えることで、政治と国民との距離はさらに広がってしまいます。
世論調査が示す深刻な状況
最新の世論調査によると、「今回の総裁選に期待できない」と答えた国民は過半数を超えています。さらに「誰が総裁になっても変わらない」と答えた人も多数にのぼり、政治への期待がほぼ消えかけていることが分かります。こうした状況は、民主主義の根幹を揺るがす深刻な問題です。
「怒り」の背景にある諦めの感情
国民の怒りの背景には、単なる不満だけでなく諦めの感情が潜んでいます。「政治家に何を言っても変わらない」「結局は派閥で決まる」という認識が広がることで、建設的な議論や政治参加の意欲が失われていくのです。これは、社会全体のエネルギーを奪う危険な兆候でもあります。
不安と怒りが意味するもの
総裁選に対してこれほど強い不安と怒りが集まるのは、日本の未来そのものが危うい状況にあるからです。経済、外交、社会保障といった課題が解決されないまま先送りされれば、国民生活はますます厳しくなります。そして政治不信が限界に達すれば、民主主義の基盤そのものが崩れてしまう可能性があります。
次のパートでは、この「史上最悪の総裁選」が日本政治全体に与える長期的な影響について考察します。政権運営の不安定化や外交力の低下など、日本の将来を左右する問題に迫ります。
「史上最悪の総裁選」が日本政治に与える影響
2025年10月4日に行われる総裁選は、単なる与党のリーダー選びにとどまらず、日本政治全体に深刻な影響を与えると見られています。派閥争い、候補者の不透明な公約、メディアの偏向報道、そして国民の政治不信――これらが重なり合った結果、政権運営の安定性や外交力に大きな疑問符が付いています。ここでは、今回の総裁選が日本にどのような影響をもたらすのかを整理します。
内政への影響:経済政策の停滞
総裁選が派閥の論理で進むと、当選した総裁は派閥間のバランスを優先せざるを得ません。その結果、国民生活に直結する経済政策が後回しにされる危険性があります。たとえば物価高対策や中小企業支援といった urgent な課題も、派閥への配慮や政治的駆け引きにより遅延する可能性が高いのです。
経済政策が遅れれば、国民の不満はさらに高まり、政権への支持率低下につながります。その悪循環は、次期衆議院選挙や参議院選挙にも大きな影響を及ぼすでしょう。
社会保障改革の後退
少子高齢化が加速する中で、社会保障制度の改革は喫緊の課題です。しかし、派閥政治が優先される総裁選の結果、具体的な制度改革は後回しにされる可能性があります。年金制度や医療・介護の見直しは政治的リスクが高いため、派閥の支持を失いたくない総裁は「現状維持」に傾くことが予想されます。
その結果、国民にとって重要な社会保障の持続可能性がますます危うくなり、将来世代に大きな負担が押し付けられることになります。
外交への影響:国際社会での信頼低下
今回の総裁選の混乱は、外交面でもマイナスに働く可能性があります。国際社会は、日本のリーダーシップに安定感を求めていますが、派閥政治に左右される総裁は強いメッセージを発信しにくくなります。米中関係や近隣諸国との関係において、日本の立場が弱まる懸念は否めません。
特に安全保障分野では、リーダーの優柔不断さが国の安全を脅かす要因となります。周辺諸国から「日本は決断できない国」という印象を持たれれば、国際社会での影響力は大きく低下してしまうでしょう。
リーダーシップの低下
「史上最悪」と呼ばれる総裁選が示しているのは、日本の政治リーダーシップの低下です。候補者たちが国民のための政策ではなく派閥間の調整に追われている限り、強いリーダーシップを発揮することはできません。その結果、日本は国内外の重要課題に対して「後手後手」の対応を強いられることになります。
国民の政治参加意欲の低下
今回の総裁選が国民に与える最大の影響は、「政治参加意欲の低下」です。派閥争いや出来レースといった構図を見せつけられた国民は、「自分たちの声は届かない」と感じ、投票や政治参加から離れていきます。これは民主主義の基盤を揺るがす深刻な問題です。
長期的な政治不安定化のリスク
今回の総裁選が示した「派閥優先・国民不在」という構図は、今後の政治に長期的な影響を及ぼす可能性があります。短期的には新総裁が誕生するものの、派閥間の対立は解消されず、政権運営の不安定さは続くでしょう。その結果、日本の政治は中長期的に停滞し、国民の生活改善はますます遠のいてしまうのです。
「史上最悪の総裁選」からの教訓
今回の総裁選は、日本政治が抱える根本的な問題を浮き彫りにしました。派閥政治、公約の不透明さ、メディアの影響力、そして国民不在の意思決定――これらを改善しなければ、日本の未来はますます不安定化していきます。逆に言えば、この危機を契機として政治改革を進めることができれば、日本は新たな一歩を踏み出せる可能性もあります。
次のパートでは、これまでの議論を総括し、「史上最悪の総裁選」から日本が学ぶべき教訓と今後の展望をまとめます。
「史上最悪の総裁選」から見える日本政治の未来

2025年10月4日に実施される総裁選は、「史上最悪」と呼ばれるほどの混乱と不信感を招いています。派閥争い、公約の不透明さ、メディアの偏向報道、国民の政治不信――そのすべてが重なり、日本の政治は大きな岐路に立たされています。本記事を通じて見てきたように、今回の総裁選は単なる政党内部の権力闘争ではなく、日本社会全体に深刻な影響を及ぼす可能性を秘めています。
「国民不在」が象徴する危機
今回の総裁選を総括すると、最も大きな問題は「国民不在」です。政策論争よりも派閥の力学が優先され、国民が最も求める具体的な課題解決は後回しにされています。この「国民不在」の構図こそが、国民の怒りと失望を生み、政治不信を極限まで高めているのです。
民主主義の形骸化
本来、総裁選は国民に希望を与えるべき政治イベントです。しかし、今回の選挙は派閥間の駆け引きとメディア戦略に支配され、民主主義の本質である「国民の意思反映」が大きく歪められています。この状況が続けば、国民の政治参加意欲はさらに低下し、民主主義そのものが形骸化してしまう危険性があります。
政治改革の必要性
この「史上最悪の総裁選」が残す最大の教訓は、政治改革の必要性です。派閥政治からの脱却、公約の透明化、メディアの中立性強化、国民の声を反映する制度づくり――これらを実現しなければ、日本政治は同じ過ちを繰り返すでしょう。逆に言えば、この危機を契機に改革を進めることができれば、日本はより健全な政治システムを築ける可能性もあります。
国民にできること
「どうせ変わらない」という諦めが広がる中で、国民にできることは限られているように見えます。しかし、政治に無関心でいることこそが最も危険です。国民一人ひとりが情報を吟味し、声を上げ、選挙で意思を示すことが、政治を変える唯一の道です。SNSでの発信、地域での議論、そして投票行動――小さな行動が積み重なれば、大きな変化につながります。
日本政治の未来への問いかけ
今回の総裁選は、日本政治の課題を浮き彫りにすると同時に、国民に大きな問いを突きつけています。「私たちはどのようなリーダーを求めるのか」「どのような社会を次世代に残すのか」。この問いに答える責任は、政治家だけでなく、国民一人ひとりにあります。
まとめ
「史上最悪の総裁選」と揶揄される今回の選挙は、日本にとって痛みを伴う出来事です。しかし同時に、それは未来を変えるきっかけにもなり得ます。国民が声を上げ、政治が本来の役割を取り戻すために、今こそ私たちは立ち止まり、考え、行動する必要があります。
この総裁選が示した危機を、未来への希望に変えられるかどうか――それは、政治家だけでなく、国民一人ひとりの意識にかかっているのです。
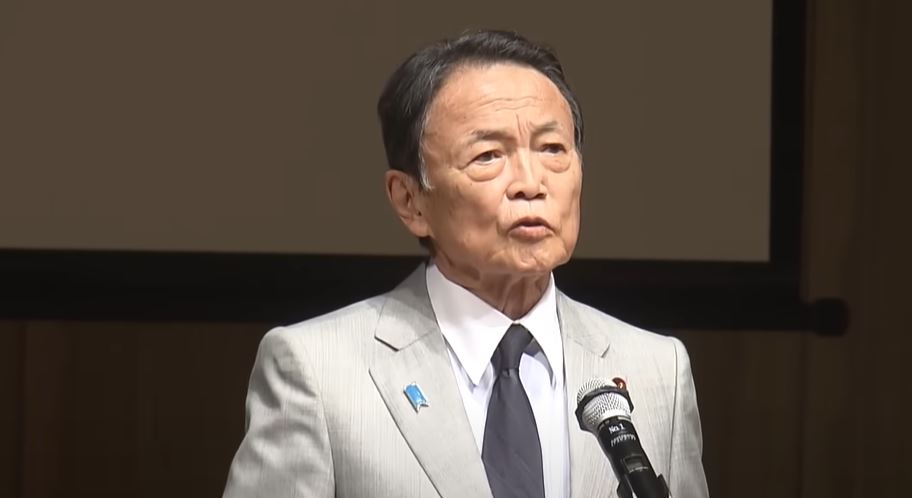
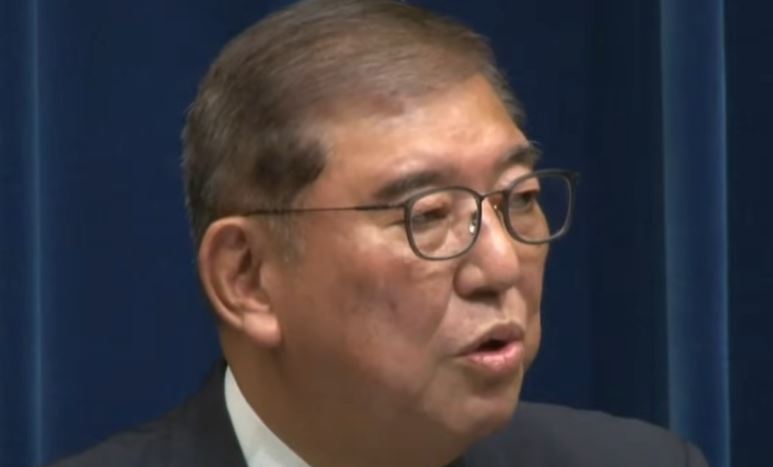





ディスカッション
ピンバック & トラックバック一覧
[…] 総裁選前倒し なぜ今?国民不在の政治が招く混乱 […]