創価学会が動いていた!?自公連立解消の裏側に迫る
公明党「連立離脱」の衝撃 — 政治地図が変わる瞬間
2025年10月、日本の政界に大きな衝撃が走りました。長年にわたり自民党と連立を組んできた公明党が、ついに「連立離脱」を表明したのです。高市早苗総裁の誕生からわずか1週間。政界では「想定外の展開」として波紋が広がりました。
この発表は、高市政権が発足して間もないタイミングで行われました。多くの政治関係者が「高市政権に対する圧力」あるいは「政権方針への牽制」と見ています。特に、公明党の支持母体である創価学会との関係や、中国との外交的な思惑が背景にあるとの指摘も出ています。
政治とカネ問題は“表の理由”にすぎない?
連立離脱の理由として一部メディアは「政治とカネの問題」を挙げています。しかし、これはあくまで“建前”にすぎない可能性が高いと、複数の専門家が指摘しています。実際、公明党と自民党の間では、政治資金の透明化や第三者チェック制度の導入など、すでに合意が進んでいたため、急な決裂の理由としては不自然です。
では、なぜこのタイミングだったのか。政治評論家・三枝玄太郎氏は、YouTube番組「デイリーWiLL」で「背後に中国共産党と創価学会幹部の動きがある」と指摘しています。彼によれば、公明党幹部が高市総理との協議前に中国大使と接触していたという情報もあり、「連立離脱」は単なる内政問題ではなく、外交・宗教を含む複雑な要素が絡む“戦略的決断”だった可能性があります。
自民党内でも予想外の動揺
自民党内部でも、この決断は「突然すぎる」「説明がつかない」との声が多く上がっています。特に、公明党がこれまで自民党の選挙戦で果たしてきた役割――いわば「票の下駄」としての支え――が一気に消えることへの不安は大きいものです。
しかし一方で、「これはチャンスだ」と見る声もあります。安倍晋三元首相の時代から「本当は切りたかったが切れなかった」と言われる公明党との関係。高市政権にとって、それを“自然な形で解消できた”という見方もあります。保守政策の推進において、これまで公明党がブレーキをかけていた分野(スパイ防止法、外国人土地規制、靖国参拝など)で一気に前進できる可能性も指摘されています。
世論の反応とメディアの報道姿勢
今回の連立解消をめぐり、メディア報道は大きく割れています。テレビや新聞などのオールドメディアは「政治とカネ問題による信頼低下」「自民党側の不誠実な対応」といった論調を中心に展開しています。一方、ネットメディアや保守系ジャーナリストの間では「公明党側が中国・創価ラインの意向を受けた」「内外勢力による影響があったのでは」との分析が広がっています。
国民の反応を見ても、SNS上では「ようやくか」「これで自民党が本来の政策を進められる」といった肯定的な声が多く見られます。共同通信の速報によれば、自民党支持率は高市総裁就任時の23%から、連立離脱後に33%へと上昇。逆に公明党は支持率をさらに落とし、過去最低水準となりました。
政治の構造が変わる“転換点”
今回の離脱劇は、単なる政党間の対立ではなく、日本政治の構造的な転換を象徴しているとも言えます。長年続いた「自民+公明」という二重構造が崩れたことで、政策決定のスピードと方向性が大きく変わる可能性があります。
特に、安全保障、外国人政策、憲法改正などの分野で、より保守的・現実主義的な路線に進むと予想されます。一方で、公明党側は独自路線の確立を目指すでしょうが、支持母体の縮小傾向を考えると、その影響力は限定的になりそうです。
つまり「連立離脱」は終わりではなく、新たな政治再編の始まりに過ぎません。これからの焦点は、自民党がどのように政権運営を進めるのか、そして公明党がどの勢力と連携していくのかに移っていくでしょう。
三枝玄太郎氏の指摘 — 背後に中国共産党と創価学会幹部
今回の「公明党連立離脱」劇で最も注目を集めたのが、ジャーナリスト・三枝玄太郎氏の分析です。彼は10月10日に公開されたYouTube番組『デイリーWiLL』の中で、「連立解消の裏には中国共産党と創価学会幹部の意向があった可能性がある」と明言しました。
番組内で三枝氏は、公明党幹部が高市総理との協議直前に「中国大使と会っていた」という事実に注目します。この会談は非公開のはずでしたが、関係者によって存在が明らかにされ、政治的意図が疑われています。三枝氏はこれを「単なる外交儀礼ではなく、中国側からの直接的なメッセージの可能性がある」と分析しました。
公明党幹部と中国大使の接触 — その意味とは
番組の中で語られたのは、斉藤鉄夫国土交通大臣や西田誠参議院議員ら、公明党の中枢メンバーが中国大使館関係者と繰り返し接触していたという情報です。タイミングは高市早苗氏が自民党総裁に選出された直後。つまり「新政権発足前夜」に起きた外交的動きだったわけです。
これが事実であれば、連立解消は単なる党内事情ではなく、日中関係の変化や創価学会を通じた中国とのパイプを背景とした「国際政治的決断」とも言えます。特に中国共産党は日本の右傾化に強い警戒心を持っており、高市政権によるスパイ防止法の推進や外国人土地規制の強化を嫌っているとされます。
創価学会幹部の人事と政治判断の関係
三枝氏はさらに、創価学会内部の人事異動が今回の政治判断に影響した可能性も指摘しています。2024年末、創価学会では「政治部長」と呼ばれる要職が交代。新任の副会長クラスが政治方針を主導する体制に移行しました。三枝氏によれば、この人物が「中国寄りの姿勢を強めている」との観測があるといいます。
これまで公明党は「平和外交」「日中友好」を旗印に活動してきました。しかし、それがいつしか「中国への過度な配慮」へと変化しているのではないか──。番組内では、斉藤氏や西田氏が「創価学会幹部の意向をそのまま受け入れている」とのコメントも飛び出しました。
自民党から見た「不可解な行動」
自民党関係者の間では、「なぜこの時期に離脱するのか」という疑問が渦巻いています。高市政権が発足して間もなく、外交・安全保障政策を固めようとしていたタイミングでの連立解消。公明党にとってもリスクが大きく、通常であれば避けるべき判断です。
しかし、三枝氏はこう述べています。「高市政権の政策方針──特にスパイ防止法や外国人土地規制の強化が、創価学会や中国共産党にとって“脅威”となった可能性がある。彼らにとっては、今この瞬間に“歯止め”をかける必要があった」。
この指摘が事実であれば、「政治と宗教」「国内と国外」の複数の軸が交錯する極めて複雑な構図が浮かび上がります。つまり、連立離脱は単なる政局の一コマではなく、国際的な思想対立の表面化という側面も持つのです。
メディアが触れない“外交ルート”の存在
注目すべきは、この問題を大手メディアがほとんど報じていない点です。テレビや新聞の多くは「政治とカネ問題」「高市政権との政策不一致」といった表面的な解説に終始しています。一方で、YouTubeやSNSなどの独立メディアが、こうした裏側の動きを少しずつ明らかにしています。
日本の政治報道は依然として“タブー”が多く、宗教団体や外国政府の影響に踏み込むことを避ける傾向があります。しかし、今回の連立離脱を理解する上で、創価学会と中国共産党の関係性は避けて通れません。三枝玄太郎氏の発言は、その封印された構造を可視化したと言えるでしょう。
今後の焦点は、こうした「外交ルート」がどのように日本の内政へ影響を及ぼしていくのかです。公明党の動きが一つの前兆に過ぎないのか、それとも新たな政治再編の引き金になるのか──。その答えは、これからの政局で明らかになっていくでしょう。
公明党の凋落 — 支持母体と組織票の変化

長年にわたり自民党と連立を組んできた公明党は、かつて日本政治において「安定のパートナー」と呼ばれてきました。しかし近年、その勢力は明らかに縮小しています。選挙データを見ると、支持基盤である創価学会を中心とした組織票にも変化が生じています。
組織票のピークと現在の落差
公明党の得票数のピークは2005年の郵政選挙でした。当時の比例代表票は約898万票。ところが2022年の参院選では約521万票まで減少し、わずか17年間で約4割減という結果になりました。最新の2024年衆院補選でも、都市部を中心に支持率の低下が顕著に見られます。
背景には、有権者の高齢化と若年層の離反が挙げられます。創価学会の信者数は公式発表がないものの、各種調査によると減少傾向にあります。特に20〜40代では「宗教活動を通じて政治に関わること」への関心が薄れ、投票行動も多様化しています。
「組織動員型」から「個人判断型」へ
かつて公明党は、選挙のたびに学会員による緻密な戸別訪問や電話連絡網で支持を固めてきました。しかしSNSやオンライン政治運動が一般化した今、その手法は通用しづらくなっています。若年層の多くは、政党の宗教的背景よりも政策内容や経済施策を重視しており、「組織による指示よりも自分で考える」傾向が強まっています。
その結果、かつて盤石だった公明党の地方組織にも綻びが見え始めました。2023年の統一地方選では、公明党候補が落選した地域が過去最多を記録。特に都市部では、与党でありながら自民党候補と票を食い合うケースも増えています。
メディア構造と支持層の乖離
もう一つの要因は、情報環境の変化です。かつて公明党が強かった年代層は、新聞・テレビを主な情報源としていました。しかし、近年はYouTubeやX(旧Twitter)などを通じて政治情報を得る層が増加し、「オールドメディア」に依存した広報戦略では支持拡大が難しくなっています。
また、公明党の掲げる「中道・平和・福祉」路線が、現代の安全保障環境とずれ始めていることも指摘されています。中国・北朝鮮の軍事的緊張が高まる中で、国防・スパイ防止法・防衛費増額といったテーマに慎重な姿勢を示す公明党は、保守層から「時代に合っていない」と見られることもあります。
自民党との関係悪化が加速する理由
自民党と公明党の関係は、2010年代後半以降に微妙な距離を見せ始めました。特に安倍政権下で進められた安保法制や憲法改正論議では、公明党が慎重姿勢を崩さず、自民党内の保守派と対立する場面が目立ちました。これにより、連立維持の“接着剤”であった政策協調が次第に機能しなくなっていったのです。
さらに2025年の高市政権誕生によって、自民党がより明確な保守路線を打ち出したことが、両党の距離を決定的にしました。公明党は「現実路線」と「信仰に基づく理念」の間で板挟みとなり、結果的に支持基盤の一部を失うことになりました。
変わりゆく日本の選挙構造
こうした動きを踏まえると、公明党の支持減少は単なる一政党の問題ではなく、日本全体の選挙構造の変化を象徴しています。政党支持が「組織」から「個人」「オンラインコミュニティ」へと移行する中で、従来型の組織政党は再定義を迫られています。
政治学者の間では、公明党の動向は「戦後型選挙モデルの終焉」を示す事例と位置づけられています。これまで“下駄の雪”として自民党を支えてきた組織票が縮小する中で、次の選挙では個人の政策選好が勝敗を左右する時代が本格的に到来するでしょう。
今後の政局展望 — 高市政権はどう動くのか
公明党の連立離脱によって、日本の政治構造は大きな転換点を迎えました。長年続いた「自公体制」が崩壊したことで、高市早苗政権は政策遂行の自由度を高めた一方、議会運営の安定性という課題を背負うことになりました。ここからの焦点は、自民党がどのように政権基盤を再構築するかにあります。
自民党の単独政権化で政策はどう変わる?
高市政権の政策方針は、就任時から明確に「国家安全保障」「経済再生」「地方分権」を三本柱として掲げています。公明党との協調を前提としない現在、特に安全保障・防衛関連の政策が加速するとの見方が強いです。
- スパイ防止法の制定や情報保護制度の強化
- 外国人による土地取得の制限・監視体制の見直し
- 防衛産業支援と技術開発の国内回帰
これらの施策は、公明党が連立にあった頃は慎重姿勢を示していた分野です。離脱により「政策の歯止め」が外れたことで、自民党はより保守的で国家主権を重視する方向へ舵を切る可能性があります。
世論は“離脱歓迎”ムードか
共同通信やNHKの最新世論調査(2025年10月上旬)によれば、「公明党との連立解消を支持する」と回答した人は全体の52%に達し、「反対」は28%にとどまりました。特に30代〜50代の現役層では「自民党が自力で政策を進めるべき」との意見が目立っています。
一方で、参議院では依然として過半数確保が課題です。自民党は国民民主党や日本維新の会との協力を模索しており、「政策ごとの部分連立」や「法案単位の合意形成」が現実的な選択肢になると見られます。これにより、政策実現力を維持しつつ柔軟な政権運営を目指す形です。
公明党の再建シナリオ
連立離脱後の公明党は、独自路線の確立を迫られています。支持母体の再結束を図りつつ、選挙協力の失敗で失った地方組織の立て直しが急務です。党内では「中道路線の再定義」や「若年層へのアプローチ強化」が議論されています。
ただし、比例代表での得票減少や組織疲弊を考慮すると、次期総選挙までに支持回復を果たすのは容易ではありません。専門家の間では、公明党が一定の影響力を維持するには、他の中道勢力との連携や政策テーマの明確化が不可欠だと指摘されています。
高市政権の試金石 — 解散・総選挙の可能性
政局の焦点は「いつ解散するのか」です。高市総理は、2026年度予算案の成立後に衆院解散を行い「信任選挙」に踏み切る可能性が取り沙汰されています。世論調査では自民党支持率が30%台後半に上昇しており、単独過半数をうかがう情勢です。
仮に解散が実施されれば、選挙テーマは次の3点に集約されるでしょう。
- 経済政策と税制改革(減税・可処分所得の拡大)
- 防衛政策・スパイ防止法の是非
- 外国人労働・土地取得規制などの安全保障政策
これらのテーマは、いずれも公明党が慎重だった分野であり、高市政権の独自色を際立たせる選挙戦になると見られています。
まとめ:新時代の政治再編へ
公明党の連立離脱は、日本政治における“戦後体制の終焉”を象徴する出来事です。自民党が単独で政策を進められる環境が整う一方で、連立に依存してきた政治文化が大きく変わろうとしています。
今後の焦点は、国民がどの方向の政治を支持するかです。安全保障を優先するのか、社会保障を重視するのか──。高市政権が次の選挙で信を問う時、日本政治は新しい均衡点を見出すことになるでしょう。
いずれにしても、「自公分離」は終わりではなく始まりです。日本の政治構造は、これから数年で再編の波を迎えることになります。
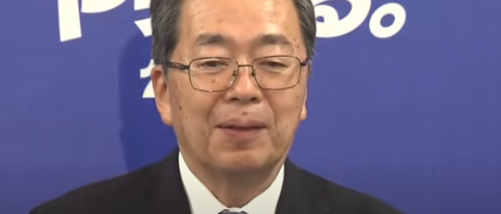


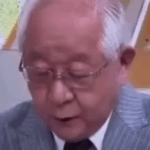



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません