第1章|“解放の日”の衝撃:トランプ政権、わずか72日で世界を揺るがす
アメリカにとっての「独立記念日」は7月4日。しかし2025年、トランプ政権が新たに制定した「アメリカの解放の日」は、それよりも早い4月2日だった。就任からわずか72日、トランプ氏はホワイトハウスでの演説で、長年続いてきた自由貿易体制に終止符を打つことを宣言したのだ。
彼の口から飛び出したのは、聞き慣れない言葉――「相互関税」。そして、全ての国に対し最低10%の一律関税を課すという、明快かつ破壊的な政策だった。
トランプ大統領、就任72日で「経済開戦」の号砲を鳴らす
トランプ氏の演説は、まるで開戦布告のようだった。壇上に掲げられた大型パネルには、各国の対米関税率と、それに対応する「相互関税」の数字が並ぶ。視覚に訴えるそのプレゼンテーションは、政策というよりは“演出”に近かった。
「アメリカは世界最大の市場だ。アクセスするには代償を払ってもらう」――その言葉は、友好国も敵対国も一括りにした、極めて強硬なメッセージだった。
これまでアメリカは、関税を低く保つことで、自由貿易体制の旗振り役を担ってきた。だがトランプ氏はそれを「一方的な譲歩」と見なし、「搾取され続けた歴史」を断ち切るとして、新制度を強行に導入した。
「アメリカの解放の日」とは何か?演説に込めた歴史的メッセージ
この日、彼は単に関税を導入しただけではない。4月2日を「アメリカの解放の日」と名付けた。これは、貿易において他国からの支配・不公平を“解放”する日であり、トランプ流の“経済的独立宣言”とも言える。
その言葉に込められていたのは、かつて工場が立ち並んでいた中西部のRust Belt(ラストベルト)へのメッセージであり、雇用を失った労働者層への宣言でもある。「アメリカン・ドリームを取り戻す」こと――それが、彼の「解放」の中身だった。
このように、トランプ氏の政治的アプローチは、単なる政策ではなく象徴を作り、物語を提示するスタイルであることが再確認された。
一律10%関税が意味する“グローバル秩序の再設計”
では、この**「一律10%関税」**が世界にもたらす影響とは何か。
関税とは、本来「経済の調整弁」である。しかし、今回の措置は、調整ではなく**再編成(リセット)**を意図している。関税を平等に課すことで、「これまでアメリカが一方的に被ってきた不公平」を逆転させようとしているのだ。
これは、WTOやFTAといった多国間ルールに挑戦する動きとも言える。トランプ氏が求めているのは、“対等な取引”ではなく、“アメリカ主導のルール”である。
一律10%と言えばシンプルに聞こえるが、実際には、これをベースに各国の関税率に応じて加算される「相互関税」が上乗せされる。つまり、一律でありながら、相手によって差をつける動的な仕組みになっている。
これにより、米国と関係が悪い国や関税障壁が高い国(例えば中国)には高率の関税が課される。一方で、協調的な国にはそれほどの負担がかからない。一律という名の“選別”政策だ。
相互関税という新しい経済言語の登場
「相互関税(Reciprocal Tariff)」というフレーズは、トランプ氏の発明とも言える新概念だ。過去には「報復関税(Retaliatory Tariff)」という言葉が使われてきたが、それとは意味合いが異なる。
報復ではなく、“鏡写し”のような関税設定。相手の関税が高ければこちらも高く、低ければ低く――公平という名の、力の再分配である。
この概念は、従来の国際貿易の発想を大きく変える。これまでの常識では、関税の撤廃が善とされていた。しかし相互関税は、「善意ではなく均衡」によって取引を成立させる。
この哲学の転換が、2025年の世界経済にどんな波を起こすのか――それは、まだ誰にも予測できない。
第2章|なぜ今、相互関税なのか?「アメリカだけが損をする時代」の終焉
トランプ大統領が掲げた「相互関税」は、突飛なアイデアではない。彼の中では一貫した“アメリカ再興”のストーリーに組み込まれている。だが、なぜこのタイミングで、しかも大統領再登板直後にこの政策を打ち出したのか?その背景には、「もうこれ以上、アメリカが損をする時代を続けさせない」という強い意志がある。
自由貿易から“公正貿易”へ:トランプ流パラダイムシフト
トランプ氏が目指すのは、単なる保護主義ではない。彼が攻撃するのは「自由貿易」そのものではなく、「アメリカだけが不利になる自由貿易」だ。長年、多国間の自由貿易協定(FTAやWTO)によって、アメリカは自国の市場を開放し続けてきた。その一方で、他国は自国の産業を守るために関税や補助金、非関税障壁で防備を固めてきた。
トランプ氏の視点からすれば、それは「不平等な競争」だった。つまり、自由貿易ではなく一方的な譲歩の連続。これに終止符を打ち、「公正な貿易」へと軸足を移すことが、相互関税導入の狙いなのだ。
「関税なき関税時代」に対する逆襲
多くの専門家や政治家が、自由貿易協定の成果としてアメリカの経済成長を評価してきた。だが、その裏で起こっていたのは、中西部の工場閉鎖、職を失った労働者たち、安価な輸入品による産業の空洞化だった。
たとえば日本やEU諸国が、車や農産物に高い関税や複雑な規制を課している一方、アメリカはそれを受け入れ続けてきた。こうした「関税なき関税時代」、つまりルールで不利な立場に置かれてきた状況に、トランプ氏は「もうたくさんだ」と声を上げた。
相互関税は、相手の関税率に応じて「お返し」する制度だ。これによって、**「不公平な慣行には代償を」**という原則が生まれた。
国家緊急事態とIEEPA:法的正当性の裏付け
驚くべきことに、この大規模な関税措置は、議会の承認を経ずに発表された。なぜ可能だったのか。その鍵となったのが、1977年に制定された**「国際緊急経済権限法(IEEPA)」**である。
IEEPAは、大統領に対し、国家的な緊急事態の際に、外国との経済取引を制限する強力な権限を与えている。今回は、貿易赤字やフェンタニル密輸を「国家緊急事態」と位置づけ、IEEPAを根拠として関税の大転換を強行した。
法的にはグレーゾーンも多いが、それでもIEEPAによる「非常事態宣言」は、大統領権限の最大活用であり、政権の覚悟を象徴する行動だった。
数兆ドルの歳入がもたらす財政・政治的インパクト
新制度による関税収入は、ホワイトハウスの試算で今後10年間で数兆ドル規模。これは単なる経済政策ではなく、財政戦略でもある。
アメリカは過去50年で累計19兆ドルの貿易赤字を抱えており、その一因は「安く輸入しすぎた」ことによるもの。今回の制度変更により、国内産業の回帰と同時に、国家収入を直接的に増やす仕組みが動き出した。
この財政的“果実”は、減税やインフラ投資、そして軍事予算の拡充にも転用されうる。つまり関税は、貿易の武器であると同時に、政治の資金源にもなっているのだ。
さらに、収入の増加は共和党内での支持拡大にもつながる。経済保守派にとって、「赤字削減と雇用増加を同時に狙える手段」は、まさに理想的。トランプ氏にとってこの相互関税は、再選を超えた“レガシー”構築の一歩でもある。
第3章|中国との経済バトル:関税とフェンタニル、そして地政学的駆け引き
「相互関税」という旗のもとにトランプ政権が最も強い“パンチ”を放った相手、それが中国だ。これは単なる経済戦争ではない。知的財産、麻薬密輸、サプライチェーン、そして国際政治が複雑に絡み合った、かつてないスケールの対立構図である。
関税をめぐる攻防の中でも、中国への措置だけは桁違い。全製品に20%の基本関税、さらに報復分として34%の追加関税――合計**54%**という異常値が、中国という存在の“特別さ”を物語っている。
関税戦争の本丸:中国との貿易赤字が象徴する“経済戦線”
まず押さえておくべきは、年間約3000億ドル(約45兆円)にも上る米中貿易赤字だ。これはもはや数字ではなく、「象徴」だ。アメリカが世界から搾取されている――そんなトランプ氏の主張を裏付ける最大の根拠でもある。
「中国は長年、我々を利用してきた」
「技術を盗み、価格を操作し、アメリカの工場を廃墟に変えた」
このような強い言葉の背景には、実際にアメリカの多くの製造業が中国との価格競争に敗れ、倒産あるいは国外移転を余儀なくされてきた事実がある。つまり、中国との貿易赤字は、失われた雇用と荒廃した地域社会の象徴でもあるのだ。
フェンタニル密輸と国家非常事態の政治的連動
さらにトランプ政権は、関税措置に麻薬問題を絡めてきた。中国から原料が送られ、メキシコやカナダを経由して違法薬物フェンタニルとしてアメリカに密輸される構造。これが、「国家非常事態」として扱われることになった。
つまり、中国からの全製品に20%の関税が課される理由は、「経済的不公平」だけではなく、生命の安全に関わる問題でもあるとされたのだ。
「関税は経済制裁ではなく、安全保障対策である」――この論理により、トランプ政権はIEEPAの法的根拠をさらに強化している。
対中54%関税の“異常値”が意味するもの
合計54%――これは通常の貿易戦略では見かけない数字だ。WTOのルールや多国間協定を前提とした枠組みでは、ここまでの関税率はまず存在しない。だからこそ、この数値は挑発的かつ象徴的でもある。
そして、トランプ氏が選挙中に公言していた「対中最大60%関税」にほぼ到達している点も見逃せない。これは、選挙公約の“実行力”のアピールでもあるのだ。
この高関税の目的は、中国企業にコストの圧力をかけ、アメリカへの輸出を抑えることだけではない。国内の企業や投資家に、中国依存からの脱却を促す構造転換をも意図している。
中国経済の“抜け道”:第3国経由戦略と米国の警戒
しかし、中国も黙ってはいない。すでにベトナムやカンボジア、インドネシアなどを経由して、アメリカ市場に製品を“迂回輸出”する動きが加速している。いわゆる第3国経由輸出だ。
ホワイトハウス関係者はこれを「ベトナムの問題ではない。中国がそこを利用している」と語っている。この発言は、今後の第3国への波及措置を予告するサインでもある。
つまり、米中関税戦争は「米中2国間の争い」では終わらず、サプライチェーン全体への監視と規制に広がる可能性がある。これは単なる貿易戦争ではなく、経済ブロック形成の火種となりうるのだ。
「まず他国を片付けてから中国に集中する」戦略的余地
エコノミストの謝田教授は、「他国はアメリカの圧力に屈する可能性があるが、中国はそう簡単に折れない」と分析する。なぜなら、中国は単なる“輸出国”ではなく、グローバル経済の中核プレイヤーだからだ。
そして、トランプ氏がまず他の国との不均衡是正を先行し、その後に全リソースを対中戦略に集中する構えである点も興味深い。これは外交交渉の常套手段であり、「外堀を埋める」作戦とも言える。
第4章|味方か敵か?カナダ・メキシコの“例外扱い”に潜む真意
トランプ政権が発表した「相互関税」政策において、明らかに異なる扱いを受けた2つの国がある。それが、カナダとメキシコだ。
彼らはアメリカと隣接し、経済的に深く結びついている“準同盟国”とも言える存在だが、今回の関税措置では特別扱いを受けた。
しかし、その“例外”は本当に善意なのか?それとも、政治的な“人質”なのか――。
なぜ北米二国は対象外?既存制裁とのバッティング
まず明らかになったのは、カナダとメキシコには今回の相互関税が適用されないということ。
理由として挙げられたのは、すでに両国には25%の特別関税が課されているからだ。これらは、主に違法移民問題やフェンタニル密輸に対応するために、個別に導入されたものである。
つまり、「相互関税」は免除されたというより、別の制裁メニューがすでに実行中なのだ。これを上乗せすれば、二重課税になりかねないという配慮、あるいは戦略的調整があると見られている。
それだけではない。アメリカ・メキシコ・カナダ協定(USMCA)によって、一部の製品には関税免除が適用されてきた。しかし、その免除期限は4月2日で切れた。つまり、現在は再び関税の空白地帯に突入しているとも言える。
USMCAとその期限切れが示す交渉カード
USMCA(いわばNAFTAのアップデート版)は、アメリカ、カナダ、メキシコの三国間で結ばれた貿易協定だ。これにより、自動車部品や農産物など、複雑なサプライチェーンの維持が可能となっていた。
だが、その一部特例が失効した今、トランプ政権は新たな条件提示を模索している可能性がある。すなわち、「違法移民対策やフェンタニル取締りに積極的に協力すれば、新しい相互関税制度にソフトランディングできる」といった外交カードとして関税を活用する戦術だ。
これはまさに、“飴と鞭”の典型。つまり、制裁を解除する余地を残すことで、圧力と交渉の両方を可能にしているのである。
「例外」は恩赦か、条件付き猶予か?米政府のシグナル
ホワイトハウス側は、今回の特例扱いについて「一時的な措置であり、状況次第では制度に組み込まれる」と述べている。つまり、カナダとメキシコが関税から“完全に逃れた”わけではない。
むしろ、「今後の行動を監視中である」という政治的シグナルとしての意味合いが強い。
特に注目すべきは、カナダからのエネルギー製品に適用されている10%の関税軽減措置が維持されるという点。これは、カナダとのエネルギー依存関係が依然として重要であることを示している。
つまり、アメリカは“敵に回したくない味方”に対して、関税という鎖を緩めたり締めたりしながらコントロールしようとしている。
対抗措置を示唆するカナダ首相の発言から読み解く今後
カナダのマーク・カーニー首相は、この「例外」措置に対してすぐさま反応を示した。
「米国が導入する相互関税は、世界の貿易体制を根本から変えるものだ」
という強い懸念を表明し、必要であれば対抗措置も辞さないと語った。
これは表向きの抗議であると同時に、国内向けのパフォーマンスでもある。カナダ国内では、アメリカに依存しすぎているという批判も根強く、こうした強い姿勢を見せることで、政権の主権アピールに繋げているのだ。
とはいえ、現実的にはカナダ経済はアメリカとの貿易に大きく依存しており、報復合戦が長期化すれば、自国へのダメージも甚大になる。つまり、脅し合いであっても、どちらも本気では崖を飛び越えたくない状況にある。
第5章|関税は国防だ:安全保障としての経済戦略という新しい論理
「関税は経済の話じゃない。国の安全保障の話なんだ」――トランプ大統領がこう断言したとき、多くの専門家やメディアは困惑した。だが、それは彼にとって真実だった。
この章では、関税を“防衛政策”として捉えるトランプ政権の新しい世界観を掘り下げていく。もはや、関税は経済手段ではなく、“武器”としての意味合いを強めているのだ。
経済政策から“経済安全保障”へ:関税の役割が変わる瞬間
これまでの通説では、関税とはあくまで市場調整や産業保護のための経済ツールだった。しかし、トランプ政権はその常識を根底から覆した。
製造業が空洞化し、サプライチェーンが海外に流出すれば、それは経済的ダメージに留まらない。**マスクや半導体の例に見るように、重要物資が海外依存であれば、緊急時に“手も足も出なくなる”**のだ。
この危機意識こそが、「経済=国防」という新しい公式を生み出した。そして、相互関税の導入はまさにその第一手であり、**「自国のサプライチェーンを取り戻すための砦」**でもある。
トランプ氏が語る「外国のずる賢い連中」—レトリックの効果
トランプ氏は演説の中で、貿易相手国を「ずる賢い連中(sly foreign nations)」と痛烈に批判した。普通の政治家なら避けるような表現だが、彼にとってはこれが“共感を生む魔法の言葉”だ。
このような強い言葉づかいは、怒れる労働者層やラストベルトの有権者にダイレクトに響く。なぜなら、彼らこそが過去30年のグローバリズムの敗者であり、正規雇用や地域経済の崩壊を経験してきたからだ。
「我々の町から工場を奪ったのは誰だ?」
その問いに対し、「ずる賢い外国の連中だ」と答えることで、トランプ氏は敵の顔を明確にし、自らを“戦う味方”として位置づけることに成功している。
NAFTAによる製造業衰退と失われた500万人の雇用
1994年に発効した北米自由貿易協定(NAFTA)は、一見、北米経済を一体化し、互恵的な成長をもたらしたように見える。しかし、その裏でアメリカ国内では製造業の海外流出と雇用喪失が進行していた。
トランプ氏はこれを「史上最悪の取引」と断言し、過去に500万人の雇用を失ったと具体的な数字を挙げて批判。さらに「19兆ドルもの貿易赤字を生んだ元凶」とも語った。
そして今、彼は相互関税を通じて、“過去の誤った取引”の精算に乗り出したのである。つまりこの政策は、単なる未来志向ではなく、過去への決着と復讐の意味合いも持つのだ。
「取引ではなく防衛」であるという政権の強い姿勢
相互関税の導入にあたり、記者団から「関税交渉に柔軟性はあるのか?」という質問が飛んだ。これに対し政権幹部はきっぱりとこう答えた。
「これは交渉ではない。国家的な緊急事態であり、表面的な妥協では問題の本質は解決しない」
ここに、“非交渉主義”という異質な論理が顔を覗かせる。これはつまり、「相手の譲歩を待つのではなく、自らルールを変える」という覇権型のアプローチだ。
貿易協定の細かい交渉を延々と続ける旧来のスタイルではなく、**「まずこちらが動く。嫌なら来るな」**という“市場主導権の強奪”に近い。
関税は、トランプ政権にとって“関所”である。誰を通し、誰を跳ね返すかを自ら決める。その背後には、経済の自由ではなく、経済の主権という考え方がある。
第6章|関税の本当の勝者は誰か?市場・雇用・物価…経済へのリアルな影響
トランプ政権が放った“相互関税”という強烈な一手は、確かに世界の注目を集めた。だが、そのインパクトが最も色濃く現れたのは、マーケットだ。
株式市場は激しく揺れ、企業は投資判断に慎重さを増し、そして一般家庭には“物価”という形でじわじわ影響が忍び寄る――。では、この政策で**本当に得をするのは誰か?損をするのは誰か?**現実を見ていこう。
株式市場はどう反応したか?NASDAQとS&P500の動き
2025年第1四半期、アメリカの株式市場は大きな不安に包まれた。
S&P500は4.6%下落、NASDAQに至っては約10%の下げ幅を記録。これは2022年以来最大の四半期下落であり、明らかに“異常値”だ。
市場がここまで敏感に反応した理由は明白だ。トランプ氏の関税政策が、単なる関税導入ではなく、ルールそのものの再定義であり、企業活動の前提条件を揺るがす“構造転換”を意味するからである。
とりわけ、グローバル展開しているIT・製造業の株は大打撃を受けた。サプライチェーンが複雑に絡み合っている現代の企業にとって、関税は“血管を詰まらせる血栓”のような存在だ。
関税=インフレか?賛否分かれるエコノミストの視点
「関税をかければ、当然モノの値段が上がる」――これは経済学の教科書的な常識だ。しかし、ことはそう単純でもない。政策の全体像を見ると、“関税=インフレ”は必ずしも成立しない。
たとえば、トランプ政権が同時に打ち出しているのが法人税の減税や規制緩和。これらは企業コストを下げ、物価上昇圧力を相殺する効果を持つ。また、国民の可処分所得を増やす減税パッケージも、実質的な物価負担を和らげる設計になっている。
ミルケン研究所のウィリアム・リー氏は、
「関税でモノの値段が上がっても、手取りが増えれば実質負担は変わらない」
と語っている。
一方で、経済学者のイアン・フレッチャー氏は真逆の視点を示す。
「関税の規模よりも、将来に対する“見えない不安”が消費と投資を冷やす」
とし、市場心理への悪影響が長期的に尾を引くリスクを指摘する。
つまり、経済の“勝ち負け”は、数字よりも“空気感”で決まる面が大きいのだ。
購買力と減税政策の相殺効果は本当に機能するのか?
たとえ減税や投資インセンティブが導入されたとしても、それが物価上昇を打ち消すだけの効果を発揮するかは未知数だ。
特に、日用品や食料品といった庶民の生活に直結する分野では、関税の影響がよりストレートに出る可能性がある。輸入野菜や家電製品が値上がりすれば、所得が増えても体感としては“生活が苦しくなった”と感じる人は少なくないだろう。
この点について、謝田教授は
「所得の増加が先か、物価上昇が先か、タイミングが重要」
と指摘しており、政策間の“時間差”がもたらす痛みに注目している。
投資家心理と企業の計画変更:不確実性という最大の敵
企業の視点で最も厄介なのは、“コストの増加”ではなく“未来の不透明さ”だ。
関税率が突然引き上げられたり、第三国経由の制裁対象が広がったりする状況では、長期的な投資判断が極めて難しくなる。設備投資や人材確保を控える動きが広がれば、結局は雇用や賃金の伸びにもブレーキがかかる。
ゴールドマン・サックスは、このような不確実性を背景に、アメリカが今後12か月以内に景気後退に陥る確率を20%→35%へ引き上げた。
つまり、関税の“中身”よりも、“続くかもしれない”という不安こそが、経済の最も大きな敵なのだ。
第7章|新関税時代の読み解き方:「雇用統計」と「消費者の財布」が語る未来
相互関税の導入から間もなくして、経済メディアの論調は二極化した。
「これはアメリカ経済の再建だ」という期待と、「世界経済の地雷だ」という警戒。
だが、どちらが正しいのかを決めるのは、評論家ではない。数字だ。
本章では、政策の“その後”を見極めるために、注目すべき経済指標とその“読み方”に迫っていく。
実体経済に影響が表れるのは“これから”
関税政策は、発表した瞬間に株価を揺らすほどのインパクトを持つ一方で、実体経済に作用するまでには時間がかかる。工場が戻り、雇用が生まれ、物価に影響が出て、消費者がそれを感じる――そのプロセスには最低でも数カ月から1年のラグがある。
だからこそ、重要なのは「一過性の数字」ではなく、継続的な動きを見ることだ。
雇用統計の変化をどう読み解くべきか?
まず注目すべきは雇用統計だ。特に、製造業の新規雇用数と失業率の推移。これらが改善していれば、関税によって国内回帰の動きが始まっている証拠となる。
ただし、注意すべきは“数の増減”だけではない。どこに雇用が生まれているかが肝心だ。中西部や南部など、かつて製造拠点だった地域で雇用が戻れば、それはトランプ氏の「アメリカ再興」路線が機能している証となる。
一方で、労働市場が全体的に“横ばい”であったり、サービス業など他の分野ばかりが伸びている場合は、関税の狙い通りには進んでいないことを意味する。
実質所得と物価:生活者目線での「関税の実感」
庶民が最もシビアに反応するのが、「財布の中身」だ。
物価が上がれば文句が出る。だが、そのとき手取りも増えていれば、文句は減る。
つまり、注目すべきは実質所得の伸び率とインフレ率の関係性だ。
ウィリアム・リー氏のように「所得が増えれば問題ない」という楽観派もいる一方で、イアン・フレッチャー氏のように「市場の心理的ショックが問題だ」と警鐘を鳴らす声もある。
実際のところ、国民が「得している」と感じるか「損している」と感じるかは、経済そのものよりも“生活の実感”によって判断される。
スーパーでの買い物が1割高くなったら?光熱費が2割上がったら?
それに対して給与が追いついていなければ、関税政策は「失策」として記憶されるだろう。
エコノミスト2人の対比:リー vs フレッチャー、正反対の未来予想図
この関税政策に対する専門家の見解は、まるで正反対だ。
**ウィリアム・リー氏(ミルケン研究所)は、相互関税を「戦略的な所得向上策」と位置づける。彼にとって関税は、サプライチェーン強化、国内投資促進、技術革新という成長の“点火スイッチ”**だ。
「アメリカ経済は強くなる。インフレは一時的。本質は“自己修復力”にある」
と語り、関税は新しい産業モデルの始まりとする。
一方、イアン・フレッチャー氏はより懐疑的だ。
彼は関税の中身よりも、それがもたらす「心理的ショック」に着目し、企業投資の冷え込みや消費の停滞を懸念している。
「もしこれが5年かけて段階的に導入されていれば、ショックは最小限に抑えられた。だが今のやり方では、爆弾に近い」
と、導入プロセスそのものに問題があると指摘する。
消費者の財布の動きが真の先行指標だ
トランプ氏が関税を「正義のハンマー」として振るった以上、その成果は国民の生活の中に表れなければならない。
ウィリアム・リー氏はこう語る。
「経済を読むには、GDPや株価ではなく、“消費者の財布”を見るべきだ」
具体的には、**国内産品の消費割合が増えているか?消費者の購買行動に変化があるか?**が重要だという。
そして、もし物価上昇が定着してしまえば、インフレリスクが現実化する。
そうなれば、中央銀行の金融政策にも影響が及び、利上げ→景気冷え込みという流れも視野に入ってくる。
未来は“体感”が決める時代へ
政策の是非は、理屈では決まらない。
数字でも決まらない。
「暮らしが良くなった」と感じたかどうかで決まる。
関税政策がこの先どう評価されるかは、統計データだけでなく、街角の声、レジの前のため息、給料日の安心感といった、日々の実感にかかっている。
そしてそれこそが、今の時代の経済政策に求められている“新しい通貨”なのかもしれない――**“体感経済”**のはじまりだ。
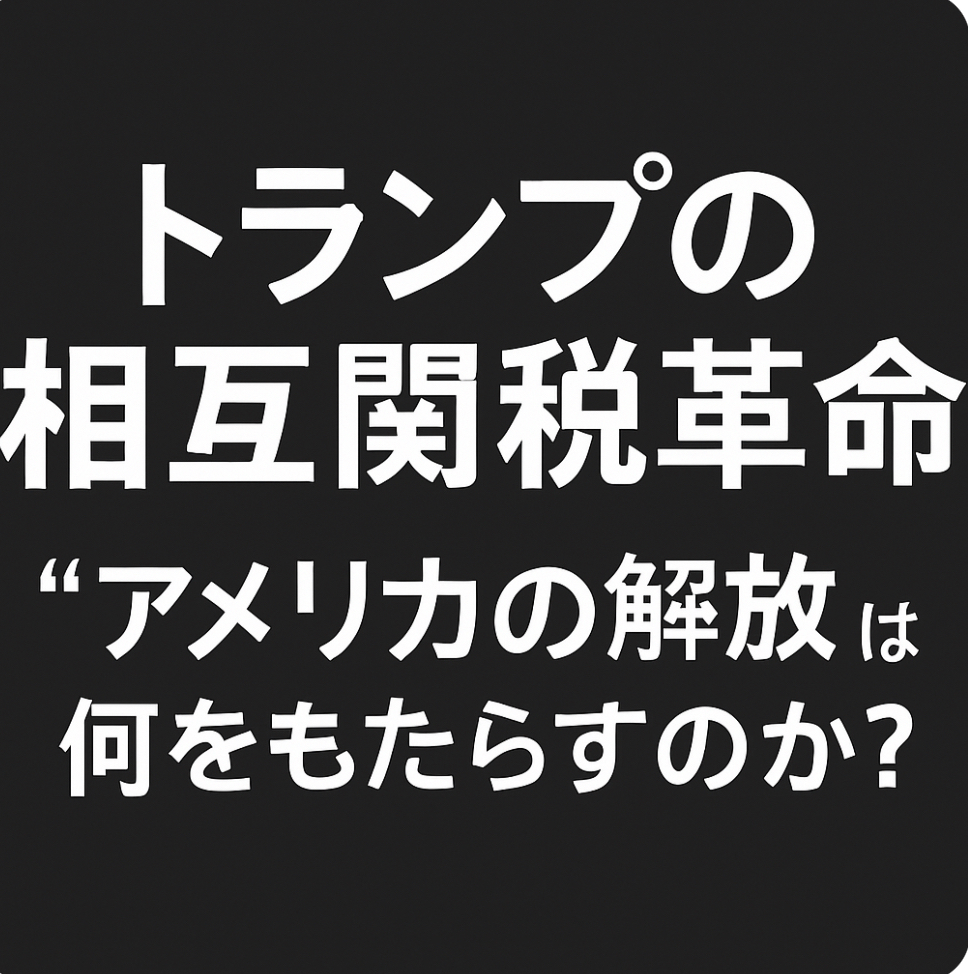
コメントを残す